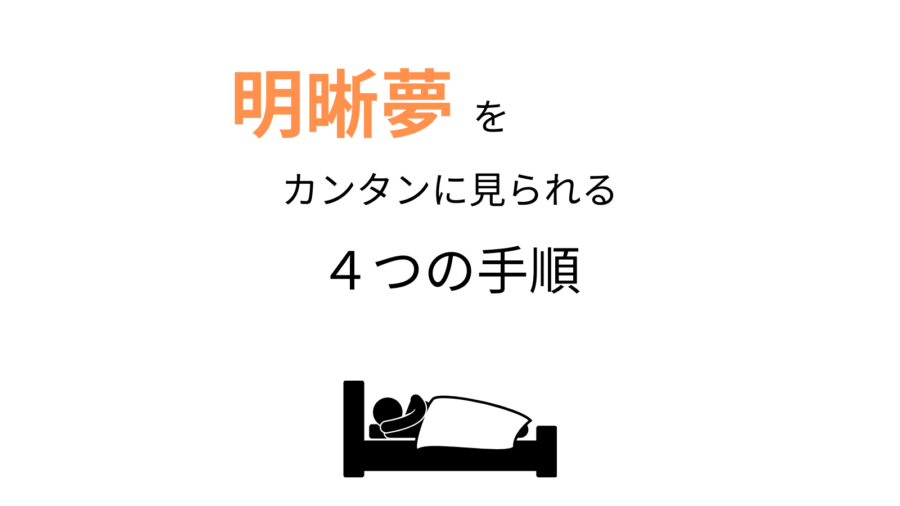心理療法士と教師は経験年数が能力に繋がらない

心理療法の分野では、長い間「経験豊富な心理療法士のほうが効果的な治療ができる」と信じられていました。
こうした職業では、様々なクライアントと接し、多くの症例を扱うことで技法が磨かれ、判断力が高まるというのは当たり前のことのように思えます。
しかし、実際の臨床現場では、ある心理療法士のクライアントの改善度が、別の心理療法士と比べて一貫して高いとは限らず、「優秀な心理療法士とは何か」というのが曖昧でした。
またいくつかの小規模な研究では、経験年数と治療効果に一貫した結果が得られておらず、経験豊富なベテラン心理療法士ほど効果的な治療が出来る、という考えについて疑問がでていました。
そこでウィスコンシン大学マディソン校(University of Wisconsin–Madison)の心理学者サイモン・B・ゴールドバーグ(Simon B. Goldberg)博士らの研究チームは、2016年に「心理療法士は経験を積むことで本当に効果的な治療者へと成長しているのか?」を検証する調査を行ったのです。
彼らは、アメリカ国内の5つの医療施設から6,591人の患者と170人の心理療法士を対象に、治療の前後で患者の心理的症状がどれだけ改善したかを「d値(Cohen’s d)」という統計指標を用いて分析しました。
すると驚いたことに心理療法士は経験年数が増えても、患者の改善効果はほとんど向上していなかったのです。むしろ、ごくわずかに効果が下がる傾向すら見られました。
なぜそのようなことが起きるのでしょうか?
ここには、心理療法士という職業が、仕事の成果に対する正確なフィードバックを得づらい点にあると考えられます。
今回は研究のためにクライアントの治療前後の心理状態が詳細に調査されましたが、通常の臨床現場ではこうした測定は行いません。
心理療法には守秘義務があるため、セッション内容を他者が評価することは通常難しく、患者の状態も本人の主観的な申告に頼らざるを得ません。結果として、心理療法士自身が自分の仕事がどれだけ効果的だったかを把握できず、外部からのフィードバックも受けにくい構造になってしまうのです。
これは何も心理療法士だけに起きる問題ではありません。
別の研究では教育の現場でも、似たような課題があることが報告されています。
ハーバード大学の経済学者ジョナ・ロックオフは、2004年の研究で、ニュージャージー州の小学校教師と約1万人の生徒の標準化テストのデータを用いて、教師の経験年数と生徒の成績向上の関係を調査しました。
この研究では、教師ごとに「その年度に担当した生徒のテストスコアが1年間でどれだけ伸びたか」を測定し、その「伸び」に教師の経験年数がどう関与しているかを統計的に分析しました。
結果として、教師の効果(生徒の成績向上への貢献度)は1〜3年目で急速に伸びるものの、それ以降はほぼ横ばいになることが示されました。つまり、初期の数年間で指導技術は向上するものの、継続的な経験だけでは、それ以上の上達や効果の増加は期待できないというのです。

しかも、この研究は「教師によって生徒の成績の伸びに明確な差がある」ことも示しています。ある教師Aは1年間で平均+10点の成績向上を引き出せるのに対し、教師Bは+15点というように、効果にばらつきがあります。
そして重要なのは、経験を重ねたからといって、その差が縮まるとは限らないという点です。つまり、教師Aが5年、10年と継続して教え続けても、必ずしも教師Bの水準に近づくわけではないということです。
教師の場合、生徒のテスト結果という形で一見明確な成果のフィードバックが得られるように見えます。しかし、実際にはその成績が指導の質によるものか、生徒個別の事情によるものかの判別することは難しく、教師自身が自分の教え方の何が良かったのか、何が問題だったのかを把握するのは容易ではありません。
また、授業は他者の目が届かない閉鎖空間で行われることが多く、客観的なフィードバックを受ける機会も限られています。
そのため教師は学び直しや改善への意欲が薄れる傾向も指摘されており、経験を重ねるほど自己流に走りやすくなると考えられるのです。
このように、フィードバックはあっても、それを活かす仕組みや環境が整っていないことが、教師の成長を妨げる要因の一つになっているようです。
私たちは、経験の長い人を無条件に信頼してしまう傾向がありますが、これらの研究報告は、「経験=上達」という単純な図式で能力を捉えるべきではないことを警告しています。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)