いたずらに「第6の大量絶滅」という単語を出すべきではない
研究チームは以上の点を踏まえ、「第6の大量絶滅が起きている」とする科学的根拠には疑問が残ると結論付けました。
その上で、安易にこの表現を用いることへ警鐘も鳴らしています。
著者らは「科学的根拠が不確かなまま『第6の大量絶滅』という表現を使い続けることは、保全生物学や科学全般の信頼性を損ねかねない」と述べています。
実際、現在のデータから推定される将来的な種の喪失率は約12〜40%程度と見込まれており、これは壊滅的な損失ではあるものの「75%以上」という大量絶滅の定義には遠く及びません。
(※たとえばIPCC 第6次報告書 WG2 (2022)によれば、温暖化が中程度のペース(+3℃)で進んだ場合は約12〜29%の生物が絶滅し、最悪のシナリオ(+4℃)で進んだ場合には最大で39%の生物が絶滅する可能性があるとされています。)
研究者らは、「数千年スケールで75%の種の消失を食い止める」といった遠い目標よりも、現在進行中および近い将来の最大の脅威を突き止め、それらを軽減することや、絶滅の危機が差し迫っている種を優先的に保全することに注力すべきだと提言しています。
今回の研究は、地球規模の生物多様性危機に対して科学的根拠に基づいた冷静な評価を促すものであり、効果的な保全策を講じる上でも重要な視点を提供しています。




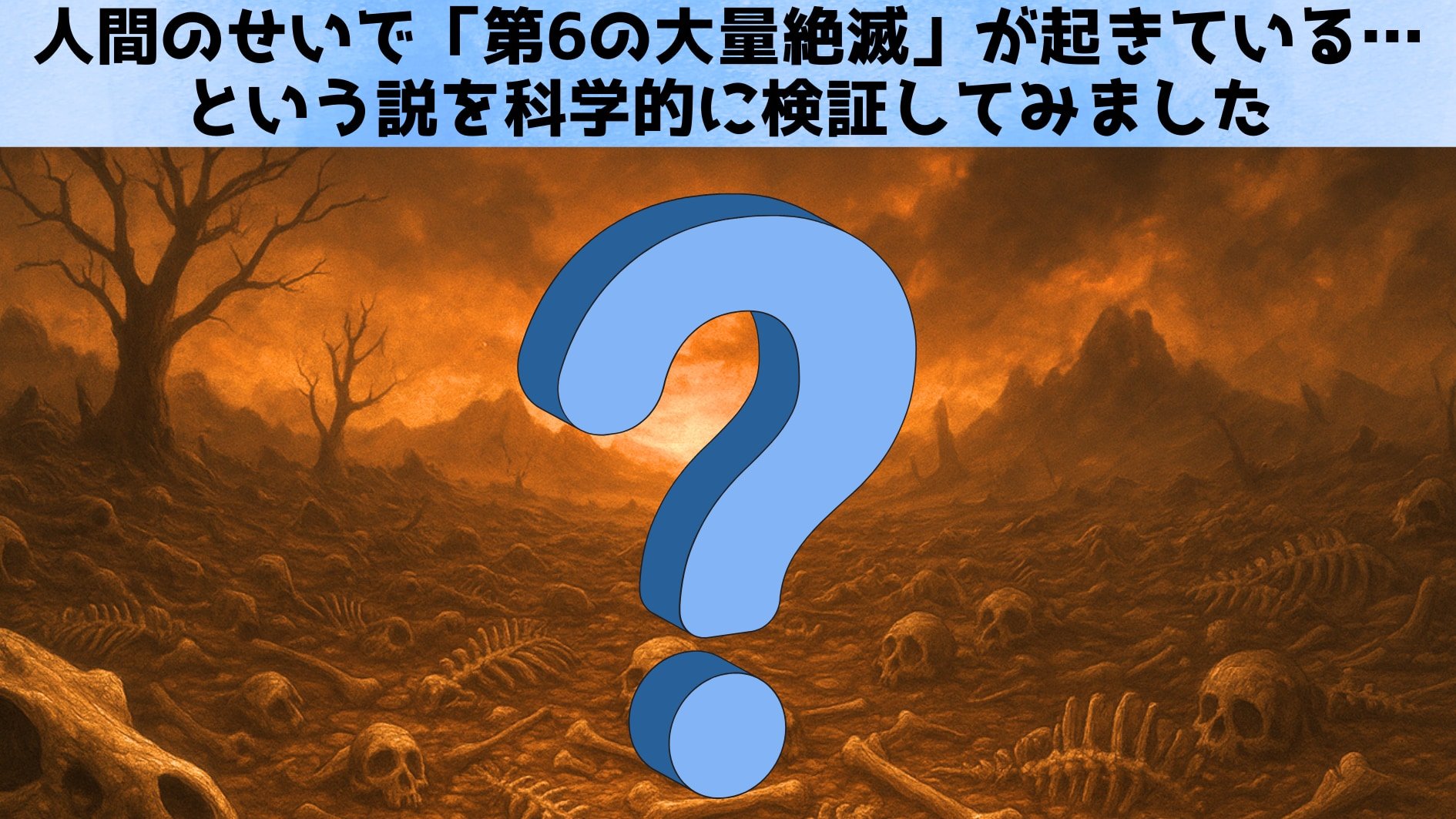

























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)




























完新世は終わり人新世に入っていると言われ、現時点でのプラネタリー・バウンダリー6項目は危険水準を超え、主要16エリアでのディッピン・エレメントのうち6エリアについてはティッピング・ポイントを超えているのではと言われている中で、現在の人為的で急激な地球温暖化によって4℃上昇シナリオ(RCP8.5)では2100年には世界の平均気温が産業革命前から3.2〜5.4℃上昇する可能性が高いと言われています。
川勝氏は、これらの多くの科学者による可能性言及についても、「第6の大量絶滅」の可能性と同様に懐疑的な立場で今回の投稿をされているのでしょうか?
「第6の大量絶滅」にはならない可能性もあるとの研究報告は、昆虫をはじめ詳細な検証を行う余地が多数あることを示唆するもので、検証結果が出るまで我々は今のままのくらし方を何食わぬ顔をして続けてもよいという正常化バイアスを正当化すべきものでもありません。
生物多様性と生態系サービスとの密接な関係を考慮した場合、人新世が「第6の大量絶滅」を招かないよう、どのような行動(くらし方)に改めるべきなのかまで言及することが求められているのではないでしょうか。
科学は時にイデオロギーに利用されるので、こういう冷静な視点を投げかけるというのは正に科学そのものの姿勢で、素晴らしいですね。
この研究が、温暖化会議論者や行政などに都合よく利用されないことを願います。
単に言葉の定義じゃないですかね?
全生物種の75%という現在の定義が、そもそもあまりに破滅的な歴史イベントを参照して設けられてるだけで、
一般人目線では40%どころか12%でも十分大量絶滅ですよ。