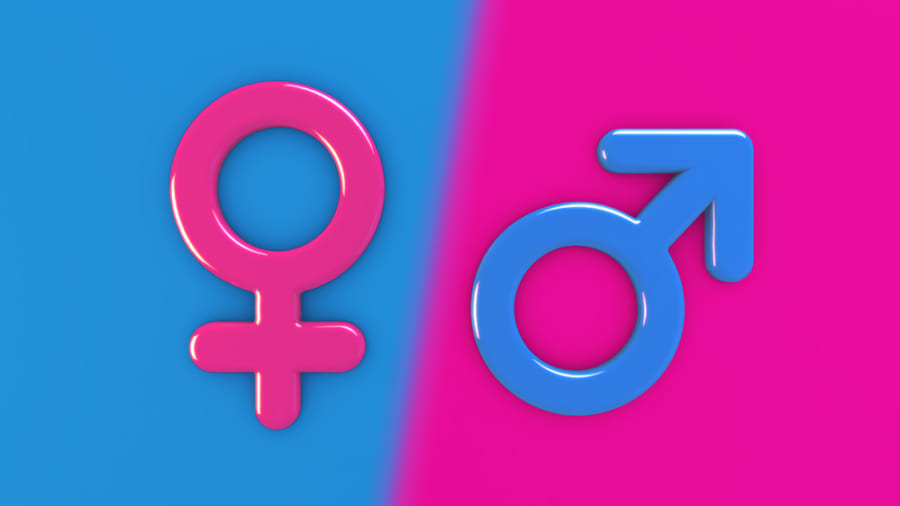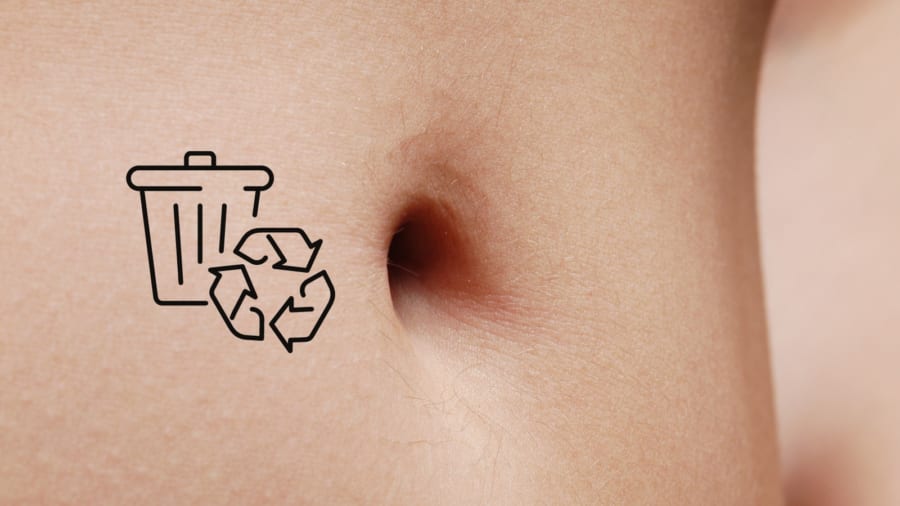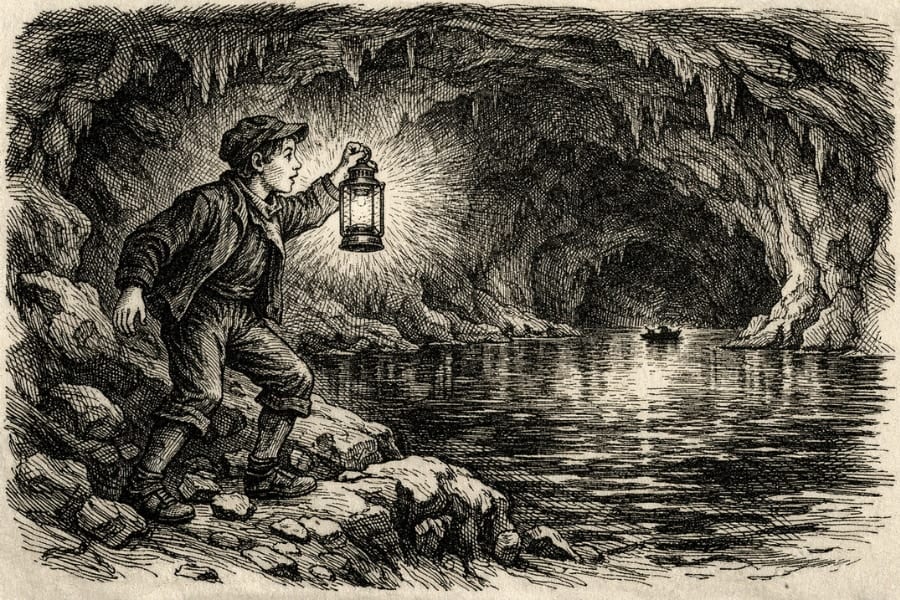感染力が弱いBA.2.86が世界同時に現れた本当の理由を探る

新型コロナウイルスが世界的に流行している間、人々の暮らしは大きく変わりました。
そして流行中にはさまざまなウイルスの変異株が登場し、その多くは感染力を高める方向に徐々に進化するものでした。
ところが、ある日突然、まるで階段を一気に何段も飛ばして上がるような、大きな変異ジャンプを示す株が現れることがあります。
オミクロン株がまさにそれで、特に2021年末に出現したオミクロン株BA.1系統は、スパイクタンパク質に約30個もの変異を一度に獲得し、世界中を瞬く間に席巻しました。
しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。
「一体どうやって、短期間にこれほど多くの変異が生じたのだろうか?」と。
これまで研究者たちは、この問いに対していくつかの仮説を立ててきました。
ワクチン接種が広がり、人々がウイルスに対して免疫を持ち始めたため、ウイルスがその免疫から逃れようとして徐々に変異を重ねたという説が一つ。
また、免疫が弱い患者の体内でウイルスが長期間生き延び、その間に変異が蓄積されたという説もあります。
このほか、人間から動物に一度感染が広がり、そこでウイルスが変異を繰り返した後、再び人間に戻ってきたという説もありました。
ところが、これらの仮説にはそれぞれ課題がありました。
免疫の弱い患者の体内で起こる変異は、過去の観察からおよそ10個程度までであり、オミクロン株のように約30個もの変異が一気に蓄積するとは考えにくかったのです。
動物由来の説も魅力的でしたが、当初の新型コロナウイルス(武漢株)はマウスには感染しにくい性質があることが知られており、「そもそもマウスにどうやって感染したのか?」という根本的な疑問が未解決のままでした。
つまり、オミクロン株BA.1の起源をめぐる謎は、未だ明快な結論には至っていません。
そのような状況の中で、2023年の夏、再び科学者たちを驚かせる変異株が登場しました。
それがオミクロン株BA.2.86系統です。
BA.2.86は、その祖先株であるオミクロン株BA.2系統から突然約30個の変異を持って現れました。
変異の数だけを見れば、BA.1と似たような大きなジャンプです。
しかし、興味深いことにBA.2.86系統は、BA.1のように世界中で爆発的な流行を引き起こすことはありませんでした。
むしろBA.2.86自体の感染力はそれほど強くなく、その後にさらに変異を重ねた「JN.1系統」という新たな株が出現した後にようやく感染が広がった程度でした。
ここで研究者たちは新たな疑問に直面しました。
感染力が強くないBA.2.86系統が、なぜ地理的に遠く離れた複数の国で、ほぼ同時期に散発的に検出されたのか?
これは自然に起こり得る現象なのだろうか?
それとも何らかの人為的な要素が絡んでいるのだろうか?
この奇妙な拡散パターンを説明するためには、BA.2.86がいつ、どこで、どのように出現したのかを詳しく調べる必要があると考えました。
そこで筑波大学の研究チームは、このBA.2.86系統の起源を明らかにするため、ウイルスが検出された時期と場所、そして変異の特徴を詳しく調べることにしました。












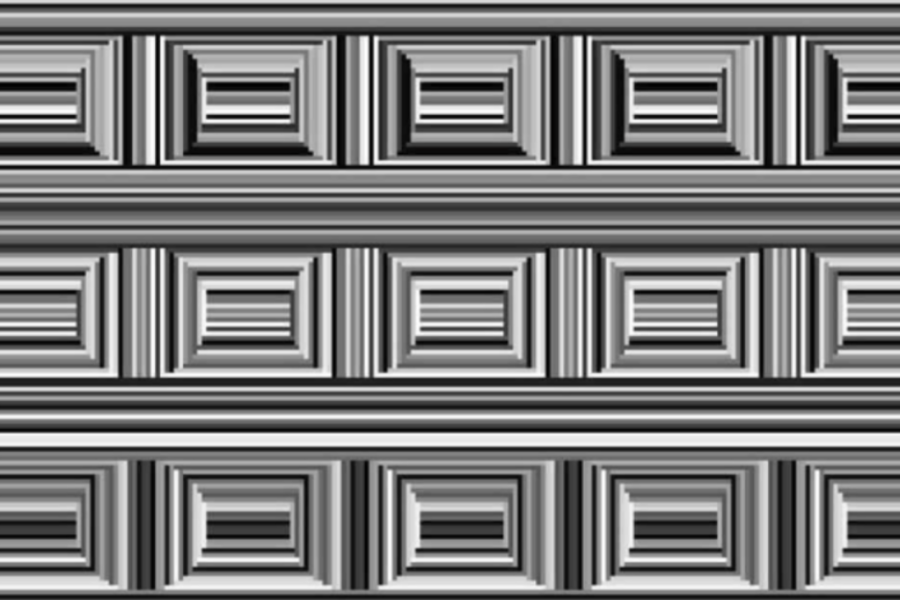
















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)