逆進化を引き起こした「4つのアミノ酸」
この不思議な現象を解明するカギとなったのが「GAME8(ゲームエイト)」と呼ばれる酵素でした。
トマトなどの植物がアルカロイドを作る際、この酵素が重要なステップを担っているのです。
通常、トマトのGAME8酵素は25S型のアルカロイドを作りますが、ナスのGAME8では25R型になります。
この違いは、たった4つのアミノ酸の違いによって決まっていました。
チームは、ガラパゴスの野生トマトからさまざまな場所のサンプルを採取し、酵素の遺伝子配列と化学成分を分析。
その結果、ガラパゴス諸島の西部に位置する火山島に生えるトマトでは、GAME8酵素に古代型の変異が起きており、それが25R型の毒を再び生み出していたのです。
しかもこの変異は、島の位置や年齢とぴったり一致していました。
ガラパゴス諸島の東側に比べて、地質的に若く、乾燥し土壌も貧しい過酷な西部の島々でだけ、祖先型の毒が復活していたのです。
なぜそんなことが起きたのか?
チームは、こう推測します。
「古代型のアルカロイド(25R型)の方が、過酷な環境での防御力に優れていたのかもしれない」と。
つまり、ガラパゴス西側の過酷な島々に暮らすトマトたちは、生き残るためにあえて失われたはずの遺伝子を“再起動”したというのです。

さらなる実験では、この4つのアミノ酸を人工的に入れ替えるだけで、トマトの酵素がナス型の毒を作り出すようになることも確認されました。
逆にナスの酵素からそれを取り除けば、トマト型の毒に戻ることもできます。
わずか数個の分子スイッチで、進化を巻き戻す――。生命の柔軟さには、驚かされるばかりです。
この発見は、単なる植物の不思議な話では終わりません。
進化とは一方通行だという前提を見直すきっかけとなり、「逆進化」もまた自然な選択の一形態であることを示しています。
もしトマトで起きたなら、人間や他の生物でも、環境の変化次第で“過去の遺伝子”が目を覚ますことはあるのかもしれません。
生命は時に、過去に手を伸ばすことで未来を切り拓く――。
ガラパゴスの火山島で静かに進むトマトの逆進化は、そんな可能性を私たちに教えてくれているのです。














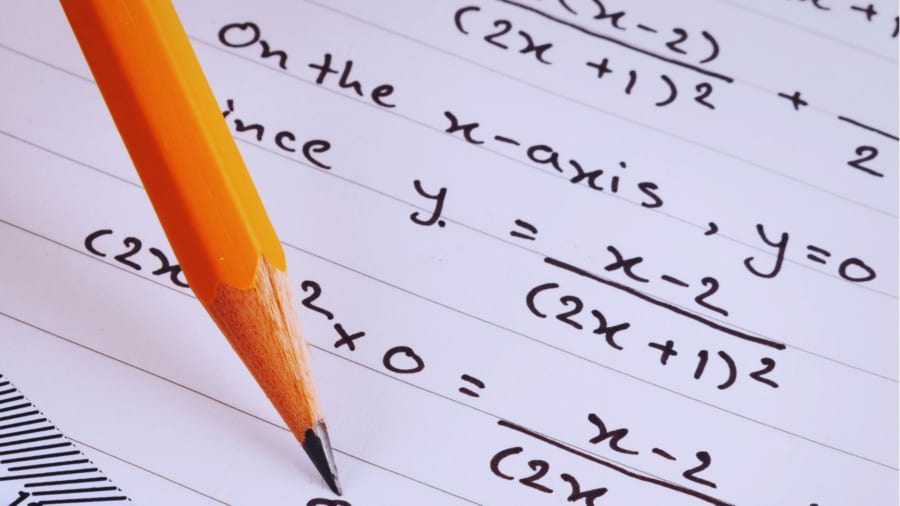














![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























「進化が前に進むと誰が決めたんだぁ?」
「なるほど、それであなたは諦めてしまわれたのですね?私は諦めません。前に進むことができないのなら一度後ろに戻って違う道を進むだけです。」
言ってみたかっただけです。
かっこいいセリフを謎に発見してしまったw
気になったからちょっと調べてみたら、普通のトマトも熟した実以外は全部毒があるって知って驚いた
適者生存は進化の1パターンだし、守ってくれる人間や楽できる環境がなければ自衛手段の再獲得も普通なんだろう
けどそれを逆進化と呼ぶのは、人間視点を過大評価してるようで違う気がする
進化って結果論であって目標や手段じゃないし、そこに方向性を語るのはお門違いだし
ただのランダムな変異と選択の結果、塩基配列の一部が戻っただけでは……?
(アミノ酸4個の違いとあるが、その四個の変異すべてが必要という記載もないので、1塩基の変異による1アミノ酸の置換で戻るかもしれないし)
逆進化という謎の概念を持ち出すからには、その仕組みを明らかにすべきですよね。
進化という名前は変えた方が良いかもしれませんね。思い込みと誤解が、それこそ科学の進歩の足かせになっているように感じます。生命はもともと、使えるものは何でも使うという適応力に特化した有機体ですから、先祖返りとして古くから認識されているこの現象も、何ら特別な事ではないのは自明です。
進化じゃなくて適応だね。
環境変化に対して、適応してきた。人間も含めて生物は環境変化に対応して変化してきた。
単なる適応なら個体レベルで起きている。それと進化が明確に違うのは遺伝子配列に変化が起き、それが保存されている点。
適者生存、自然淘汰の結果、環境に適した遺伝子が世代を超えて受け継がれていく。
むしろ、トマトの「毒を作る」という能力が人間の手によって退化させられていたのが野生に帰って元に戻っただけのような……
問題はDNAの配列が異なるという点。
変異しやすい部位なのだろうけど、自然淘汰によって選別されなければその変異は保存されない。
環境がそれまでとは反対の苛烈な方向である負の変化があり、それに合わせる為の逆方向進化、即ち負の進化を成し遂げたのであれば、それは合成すると正方向の進化ではないだろうか。
逆進化とは呼べないと考える。
一般的に進化という言葉の定義が曖昧のように思えてなりません。たとえ突然変異が起きても、トマトなら同じトマトとの交配が成り立つなら、進化とは言えず、あくまで種の中のバラエティに過ぎないと思います。
また、自然に適応したのであれば、それも「進化」であって、逆ではないはずです。進化の逆は退化なのでは。
本来の「進化」の定義を超えて、何でもかんでも「進化」という言葉を使うと、科学的には問題ではないでしょうか。
退化は進化の逆じゃありませんよ
進化の結果として持っていた能力や器官を失う事が退化であり進化の一種でしかありません
だからこそ過去の姿に戻る今回は退化ではなく逆進化などと呼んだんです
逆進化?
環境に適応した変化を進化というのだから、これも進化そのものでしょ
進化論自体、進化を進歩とは定義していない
汽車の不勉強が過ぎる
前半部分は同意だが、記者はreverse evolutionという元論文の用語を直訳しただけだと思われるので記者の不勉強というよりは元論文著者のネーミングセンスがないだけかと。
退化 または 適応 環境に合うように動植物はそうなってる
進化、退化、前、後ろ、そんなものは人間が思い付いた概念でしかない。変化が有るだけだ。
進化に意思が働いているような言い方をする記事や番組を見かける事がありますが、偶然環境に適応できた物が今生きているだけですよね?
逆進化で無くて先祖返りって言わんの?
ナス科は基本毒
逆進化があるならば、袋小路に入って絶滅したとされる種は何故逆進化しないのか?
進化論にはその場その場で都合のいい解釈をし過ぎ。
研究者「逆進化って呼んだらバズるやろなぁ」
おれ「進化の過程で特定の性質を得たり、失ったりするんだから、逆ではなく通常版の進化で、あえて言えば『再進化』だよね」
公害としての香害の被害で、合成芳香だけでなく消臭抗菌成分でもかなり深刻な化学物質過敏症を引き起こす人々がでてくるのも、逆進化かも。
逆進化なんて耳馴染み無い言葉より先祖返りで良くないか
変な言葉の方がキャッチーなのか
ピカチュウは進化してライチュウになるというワンパターンしかなかったはずが
いつの間にかピチュウという進化前の存在が明らかになり、これが逆進化と呼ばれるようになったということでしょうか。
そう言えば当時ガラパゴス携帯なるものがありましたが、ガラパゴス諸島に通信ケーブル突き刺して取り除いたものでしょうか。
逆進化という表現が誤解を生みやすい。こういう形態の進化はよくあることで、以前から知られていたこと。ただ、そういった進化の過程を示すものとして、貴重な一事例であることは間違いない。
「逆進化」って表現は人間視点だよなぁ。現地のトマトにとっちゃ進化でしょ。(´・ω・`)知らんがなって言われるだけやんw
逆進化なんんて適当な用語を作らないでください。一般用語の進化と生物学の進化はそもそも意味合いが違います。他の人も言ってるように機能の喪失も獲得も同様に進化です。
逆(reverse)とか書いてあるから、遺伝子変化の抑制する遺伝子の発見とか、かと思ったら普遍的に起こっていることがただ書いてあるだけだった、身売りしたWarner一派だからこの程度か?
どうしても(マス)描きたいなら、再進化(re-elovution)くらいにしてほしいね、まだ許容できる