『酔い方タイプ』が分かれば病気や依存症も防げる

今回の研究によって、日本人の「お酒の酔い方」は大きく3つのタイプに分かれ、その違いが遺伝子によって決まっていることが科学的に示されました。
お酒に強いか弱いか、ということはよく話題になりますが、これまでは漠然と「体質の違い」と説明されることがほとんどでした。
しかし今回の研究では、そうした曖昧な説明をよりはっきりと具体化することができました。
また興味深いことに、アルコール摂取後の「時間経過」によって、影響を及ぼす遺伝子が入れ替わる現象も見つかりました。
飲んだ直後はALDH2のタイプによる影響が強く出ますが、数時間経つと、ADH1Bのタイプの違いが徐々に重要になってきます。
つまり、「酔い方」には瞬間的な反応だけでなく、飲んでからしばらく経った後の状態も遺伝子によって左右されているのです。
この発見は、単にお酒に強い弱いを分類するだけでなく、「酔い方」の時間的な変化や特徴を把握する上でも画期的なものと言えるでしょう。
さらに研究チームは、他の遺伝子(ALDH1A1、ALDH1B1、GCKR)についても調べました。
これらは近年、飲酒習慣との関連が指摘されていた遺伝子ですが、今回の研究では特に目立った影響は見られず、酔い方のタイプ分けにおける役割は限られたものでした。
今回の研究成果を応用すると、将来的には自分の遺伝子タイプを調べるだけで、「どの程度の飲酒で体にどのような影響が出るか」を予測できるようになるかもしれません。
これによってアルコールに関連した病気や依存症のリスクを早期に発見したり、防ぐためのアドバイスをしたりすることが可能になるでしょう。
自分のお酒の強さを知っておくことは、健康管理や上手なお酒との付き合い方にも大きな意味を持ちます。
「すぐ酔うから安心」あるいは「酔わないから安心」と安易に考えるのではなく、それぞれのタイプに特有の健康リスクがあることを意識することが重要です。
さて、あなたは自分がどの「酔い方タイプ」に当てはまると思いますか?




















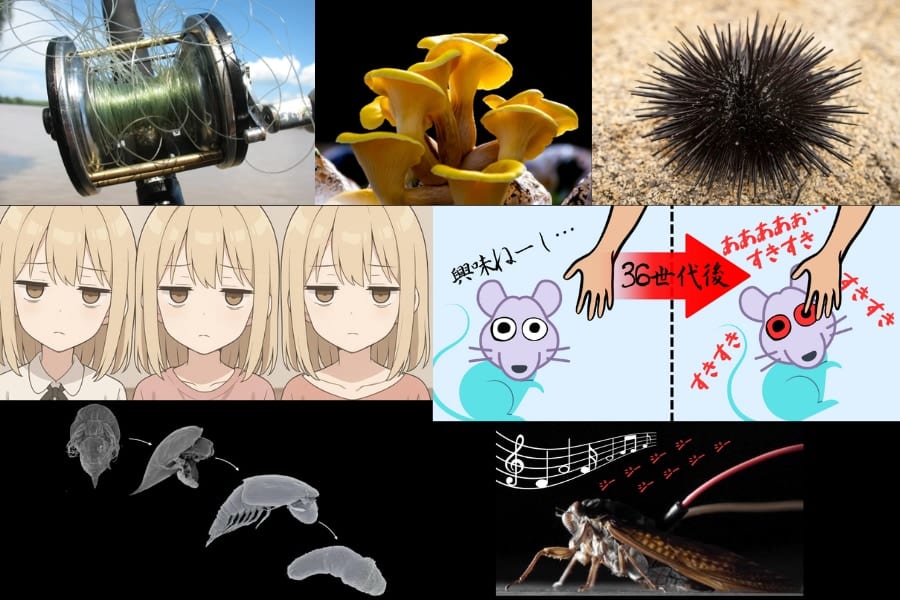








![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)





















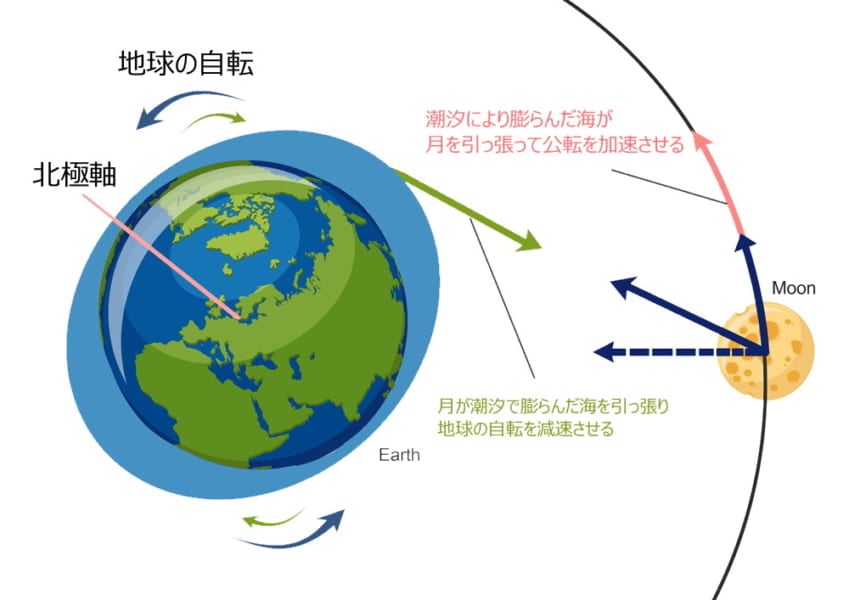






少し時間を置いてからガツンとくるタイプですね。
フランベした調理酒やビール酵母でも二日酔いできる才能の持ち主ですから。
ビール酵母で酔える人ってかなり珍しいと思うんですよ、だってあれ反応しきったやつを使いますからね。
20年近く前の学生実験で自分のALDH2のタイプを調べる実験やりましたが、当時から「正常型」「中間型」「変異型」の3タイプに分けてましたよ
(ALDH2だけ見ても正常型と変異型があれば組み合わせの数が3通りなので当たり前)
この研究のポイントは「分類が二つではなくて三つだった」ではなく「遺伝型と表現型が一致していることを統計的に確かめた」ところでしょう
少しだけ調べましたが、
・日本人の醉い方が大まかに3つだとはっきりと絞れた
・日本人の醉い方別に遺伝子型の割合に特徴があった
という話と認識しました。
醉い方がわかって色んな人の集団分けができるようにので、遺伝子型(アリル)の組み合わせごと特徴が更新されていくかもしれませんね。
実際の個人の遺伝子型がどうとか、習慣の影響がどうとか、細かくわかってくるのが楽しみです。