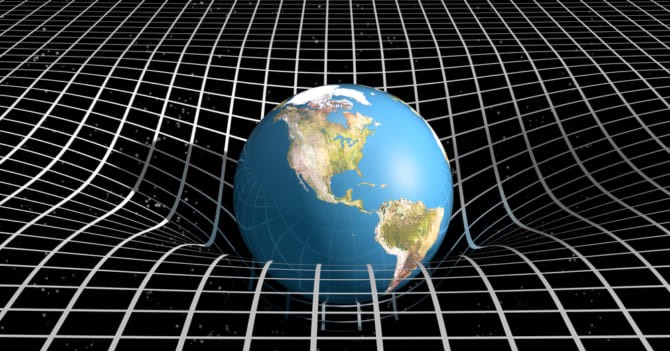『クール』の歴史と人々が求める理由

私たちは日々の生活の中で、SNSや街角、学校や職場で「クールな人」を見かけることがあります。
「この人、なぜか惹かれる」「なぜか目が離せない」と感じたことはありませんか?
多くの場合、そんな「クールな人」には、外見や持ち物だけでなく、他の人とは違う特別な雰囲気や態度があります。
けれども、そもそも私たちはなぜそれを「クール」と感じるのでしょうか?
そして、その感覚は時代や国を超えても共通しているものなのでしょうか?
実は「クール(cool)」という言葉には古い歴史があります。
もともと1940年代のアメリカで、アフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャンやビートニクと呼ばれる若者たちが使い始めた言葉だとされています。
当時の「クール」は、苦しい状況や社会の圧力に対しても動じることなく、自分らしさを貫き、静かな反骨精神を持つ態度のことを指しました。
それは一種の反体制的な表現であり、既存の常識や価値観に囚われない自由な生き方の象徴でした。
その後、この言葉は世界中に広まりました。
1950年代や60年代の映画や音楽、そしてファッションを通じて「クールさ」は一般的な概念となり、現代ではほぼ全世界で通じるほど一般化しています。
しかし一方で、多くの人々が使うようになり、商品や企業の広告にも頻繁に使われるようになったことで、「クール」の概念が本来持っていた反骨精神や尖った部分が弱まったという意見もあります。
それでも研究者は、「クールさはその本質を失ったわけではなく、むしろ時代に合わせて変化し、社会的な影響力を強める新たな機能を獲得している」と指摘しています。
とはいえ、「クール」という言葉の意味は、人によって少しずつ異なります。
ある人にとっては「クールな人」は誰にでも好かれる善良な人気者ですが、別の人にとっては少し危険で反抗的、あるいは独特な個性を持つ人かもしれません。
つまり「クール」の定義は曖昧で、私たちが「なぜクールだと感じるか」についても明確な基準がありませんでした。
そこで今回の研究研究者たちは「クールな人」に共通する価値観や性格特性を明らかにしようと考えました。
私たちが無意識に感じ取っている「クールさ」とは、具体的にどんな要素によって決まるのでしょうか?














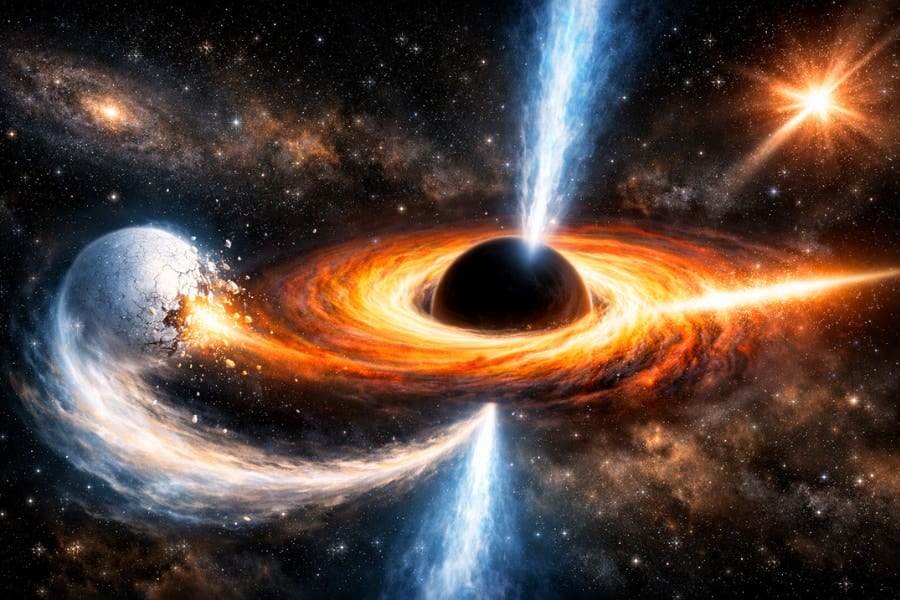






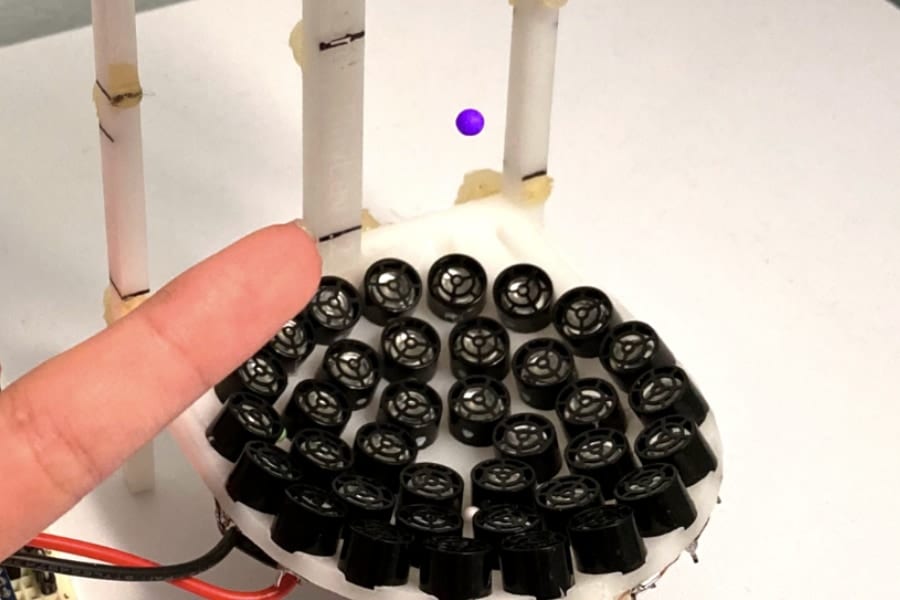








![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)