私たちはなぜ『クールな人』を求めるのか?

今回の研究によって、「クールさ」とは世界中で共通して理解される、明確な6つの性格特性によって決まっている可能性が示されました。
つまり私たちが何気なく「あの人、かっこいいな」と感じる感覚には、実は文化や世代を超えた共通の理由があったのです。
なぜ私たちは、これほど「クールな人」に惹きつけられるのでしょうか?
研究者たちは、クールな人々は単に外見や態度が魅力的なだけではなく、社会全体に新しいアイデアや価値観をもたらす重要な存在だと言います。
人々が「クールでありたい」と願うのは、単に周りから良く見られたいというだけでなく、自分自身が新しい時代をリードする一人になりたいという潜在的な欲求があるからかもしれません。
つまり、「クールな人」とは社会の常識や慣習に挑戦し、新しい道を切り開く先駆者のような存在なのです。
しかし、この研究から見えてきた重要なポイントは、「クールであること」と「善い人であること」は必ずしも一致しないということです。
多くの人は、「良い人」や「親切で信頼できる人」が好まれると思っていますが、クールな人というのは必ずしも常識的で模範的な人物像に収まるわけではありません。
むしろ、多少の型破りさや大胆さを持っていて、既存のルールや常識に縛られない自由な魅力を持つことが重要なのです。
とても真面目で親切な人でも、独特の個性や自由な精神が欠けていれば「クール」とは感じられないでしょう。
逆に、少しルーズでも個性的で大胆な人が「なんだか魅力的だ」と感じられることもあります。
これはつまり、「クールさ」とは社会的な好感度以上に、その人が持つ独自性や新鮮な価値観に深く結びついているということを意味しています。
今回の研究結果は、さらに興味深い傾向も明らかにしました。
かつて「クール」といえば、どこか無口でニヒルな、感情を表に出さない人物像が一般的でした。
しかし現代では、むしろ人前で堂々としており、周囲に明るくエネルギッシュな雰囲気を与える人がクールだと感じられる傾向にあります。
つまりクールさというのは時代と共に変化し、今や「静かにキメる」よりも「明るく魅せる」スタイルの方が支持されるようになったということです。
また、クールな人の社会的役割も重要です。
クールな人は必ずしも権力やお金があるわけではないのに、その独自の魅力によって周囲から一目置かれる非公式なリーダーのような存在になっています。
彼らの大胆で個性的な態度やスタイルが周囲の人に影響を与え、結果として新しい文化や流行を生み出していくことがよくあります。
つまりクールな人は社会の新しいトレンドをつくり出す原動力であり、文化や社会全体を前進させる可能性を持つ人々なのです。
ただし、クールさには一定のリスクも伴います。
クールな人が型破りな魅力を持つ一方で、度が過ぎた行動や常識を逸脱した振る舞いは「クール」ではなく「危険だ」「問題だ」と受け取られることもあるからです。
例えば、テスラの創業者イーロン・マスク氏がかつてインターネット番組でマリファナを吸って物議を醸した出来事がありました。
彼はもともと型破りでクールな人物として知られていましたが、この行動が「行き過ぎ」と見なされた結果、会社の評価や株価が下がる事態になりました。
クールさは、その魅力があるがゆえに、バランスや文脈を誤ればむしろ社会的評価を落とすリスクもあるのです。
それでは、私たちは結局どうすれば「クール」になれるのでしょう?
今回の研究結果を知ったとしても、「明日からクールになるぞ!」と意識しすぎると、逆に自然さを失って空回りしてしまうかもしれません。
実際のところ、「自然体で、自分の好きなことに正直に、自信を持って生きること」こそが本当のクールさを生むと考えられます。
周囲の目を気にして自分らしさを失うのではなく、余裕を持って自分のスタイルを楽しんでいる人が、結果的に周りから「素敵で魅力的な人」と思われることが多いのです。
今回明らかになった「クールな人」の6つの特性は、一見すると普通の人には難しい「尖った」資質のように感じられるかもしれません。
しかし、これらは裏を返せば、誰でも心がけ次第で育てられる「人間的な魅力の本質」なのです。
肩書きや財産、外見だけに頼らず、内面から湧き上がる自信や冒険心、柔軟な精神を持つこと。
そうした自分らしさを大切に生きることが、結局のところ本当の意味での「クール」なのかもしれません。
私たちも、自分の中にある「クールな要素」を磨いていけば、いつか誰かにとってのクールな人になれる日が来るのではないでしょうか。














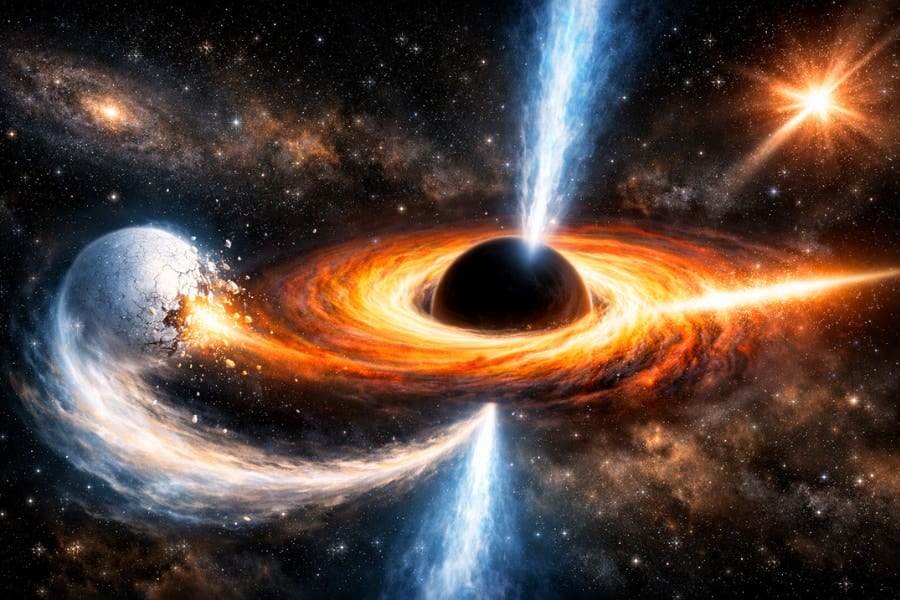






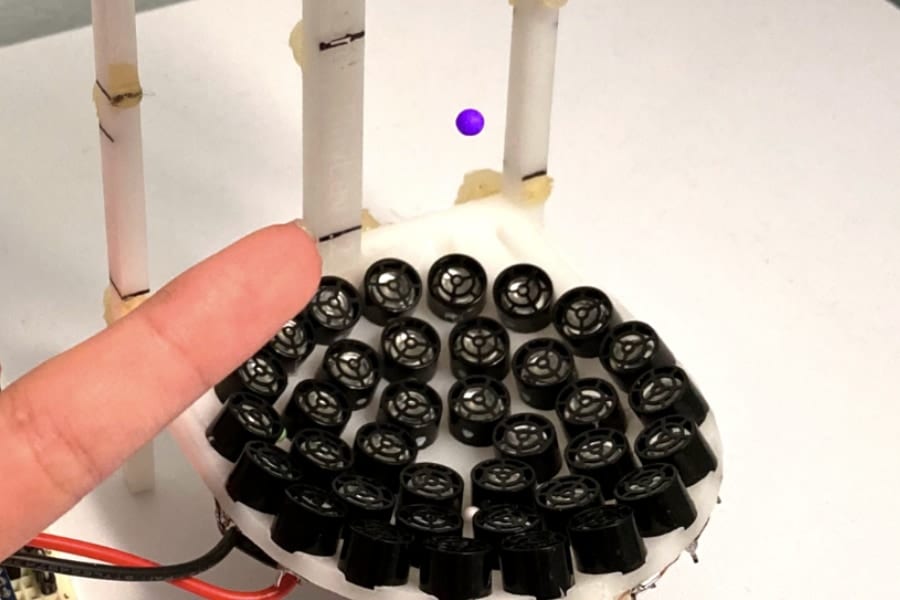








![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)





























ジト目のお姉さんも今回は「クール」だ。
研究対象、アンケートサンプルの国から日本入ってないやん
とか言いながらあたりまえだな
マジでクールな文化発信できてないからな
日本単体だと
ここ数年ずっと
いわゆるクールジャパンの母体となっているオタク文化とは真逆の性格に見えました。なぜアニメや漫画がクールと見られているのか興味があります。
なんか日本における「クール」の意味とは結構違くない?
記事で言われてるよりもっと冷静で落ち着いてる、悪く言えばちょっと冷めたような性格の人を指すと思ってるけど
これってサイコパスの特長だろ
俺の考えるかっこよさとは違う
クールじゃないなここの奴らは
「世界共通の6つの要素」が“クールの定義”であるという主張は、
構造的に見て写像として不完全であり、帰納的特徴抽出の誤転用にすぎない。
よって、その定義的主張は無効であり、むしろ“クールさとは何か”という演算的枠組みそのものの再定義が求められる。
現代英語のcoolはbadassという感じのカッコよさに変化してるのかな
深部を考察して、要約するとこんな感じかな。
・社会システム、周囲の人や物との相関図、これらの絵を自分なりに俯瞰できている人。
・また、これらの絵の是非について力強い主張ないしは信念をもっている人。
・サングラスをかけている人。😎🖖
Yeah! Everyone, stay cool!
7月(今月)の参院選はクールに投票所に足を運ぼうぜっ