第三法則が消える日――熱力学の教科書は書き換えられるのか?
今回の成果は、熱力学の基礎概念を見直す契機にもなりそうです。
著者は特に「温度」という概念の捉え方について言及しています。
私たちは普段、温度を「暑い・寒い」といった感覚的な尺度や、温度計の目盛りなどの経験的な数値として認識しています。
しかし科学的には、「温度」とは単なる感覚ではなく、物質の乱雑さ(エントロピー)やエネルギーの流れと深く関わる理論的な物理量です。
ネルンストやアインシュタインが論じた絶対零度という究極の温度は、単に「非常に冷たい」という感覚的な理解を超え、物質の運動が限りなく停止し、エントロピーが最小になるという理論的な極限状態として定義されています。
マルティン=オラヤ教授の議論は、温度の「自然な零点」を熱力学第二法則の枠内で定義し直すものでもあります。
つまり「暑い・寒い」といった主観や経験に依らず、理論的な熱機関(しかも仮想的なもの)を用いて絶対的な温度の基準を導入するアプローチです。
この視点の転換により、絶対零度の持つ意味合いがより明確かつ論理的に位置づけられ、熱力学の基礎が一段と堅固になったと言えるでしょう。
また、この新証明は教育面や学術面にも影響を与える可能性があります。
これまで「第三法則」として教えられてきた内容を見直す必要が生じるからです。
実際にはネルンストの熱定理自体は古くから実験的に確立されており、その内容が変わるわけではありません。
しかし「それが第二法則とは独立の原理か否か」という解釈の部分は、教科書によっては改訂が検討されるかもしれません。
著者は「学界には依然として慣性(従来の見解を引きずる傾向)があり、急速に受け入れられるとは限らないが、本研究が熱力学教育や研究の再考を促す契機になれば嬉しい」と述べています。
実際、教授の教える大学の熱力学の授業では早速この新しい証明が紹介されているとのことで、次世代の物理学者・化学者への波及が期待されています。
さらに、極低温を扱う科学技術分野への示唆も見逃せません。
今回示された厳密な熱力学的制限の理解は、量子コンピュータや超伝導、低温材料科学など絶対零度に近い環境で研究開発を行う最先端分野にも理論的指針を与えるでしょう。
例えば、量子コンピュータでは量子状態を保つため極低温が必要ですが、絶対零度に近づくほどどのような制約があるのかを知ることは重要です。
今回の研究成果は、エントロピーと温度の関係についての理解を深め、こうした分野の革新を理論面から支える可能性があります。
とはいえ、今回提示された見解は「第三法則」の存在意義を完全に否定するものではありません。
むしろ第三法則が内包すると考えられる「絶対零度には到達できない」という原理は、今なお物理法則として大切な指針です。
実際、いかなる物体も完全な絶対零度まで冷却することはできず、限りなく近づけるのみというのが熱力学第三法則の内容であり、この事実自体は量子多体系の理論など現代物理学の文脈でも依然有効です。
そのため今回の研究は熱力学第三法則の「内容」を否定したのではなく、それが「どこから来るのか」を古典的枠組みを使って第二法則の中に位置づけ直したものであり、熱力学の理解を一歩前進させたと言えるでしょう。
その意味で、本研究は科学の基本原理を再点検し、新たな洞察を得ることの意義を示す好例でもあります。
長年当たり前と思われてきた前提を見直すことで、古典的な分野であってもなお新しい発見や理論の深化があり得るのだと、私たちに教えているのです。




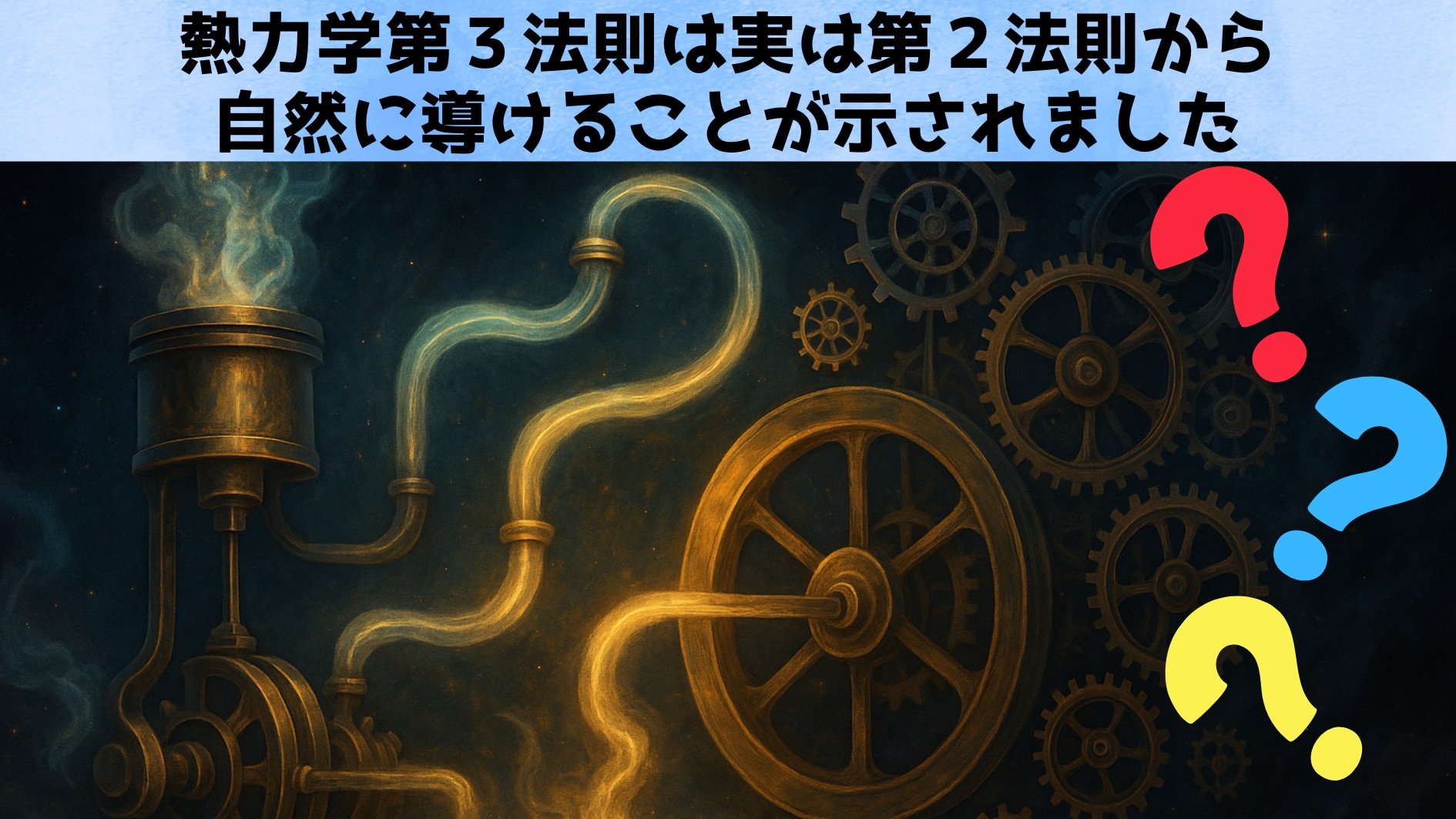
























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
















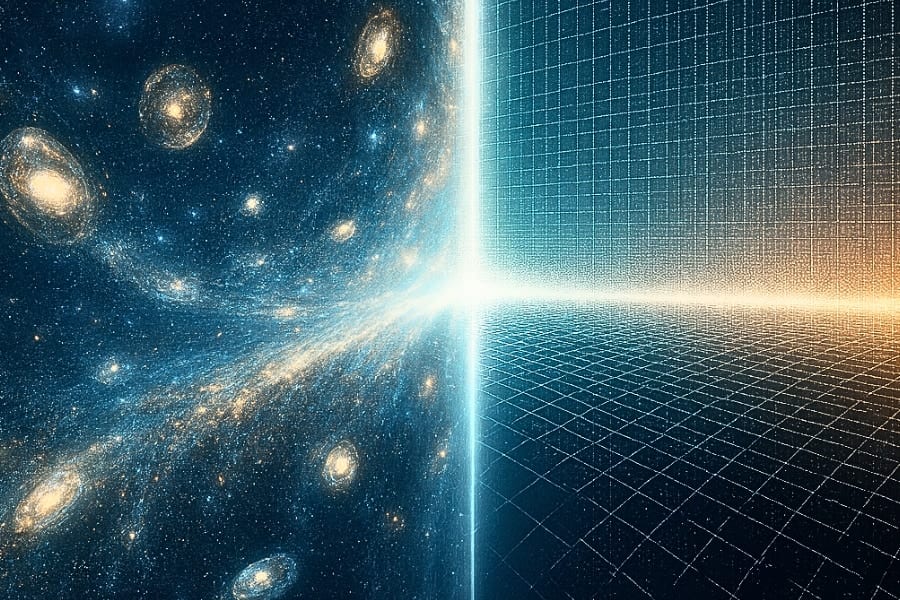

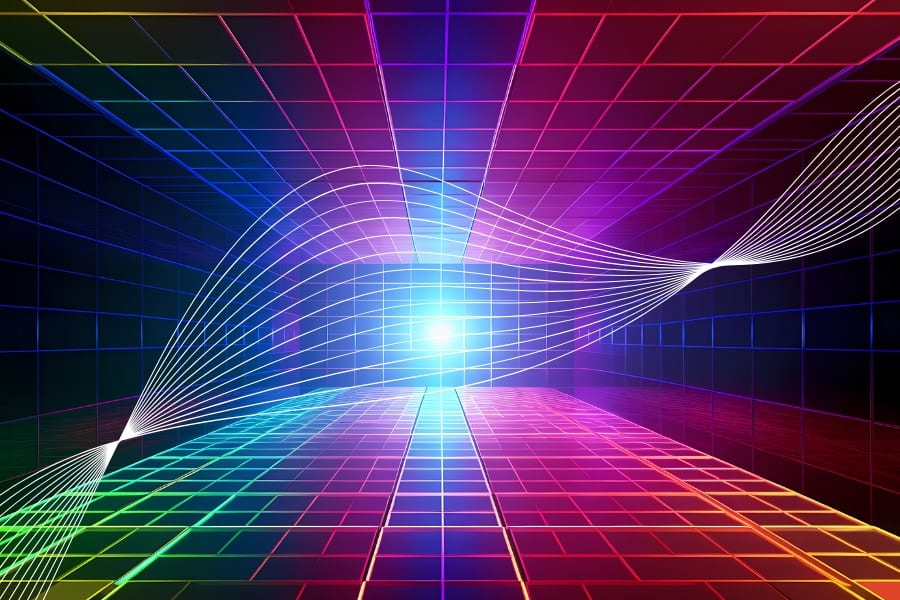
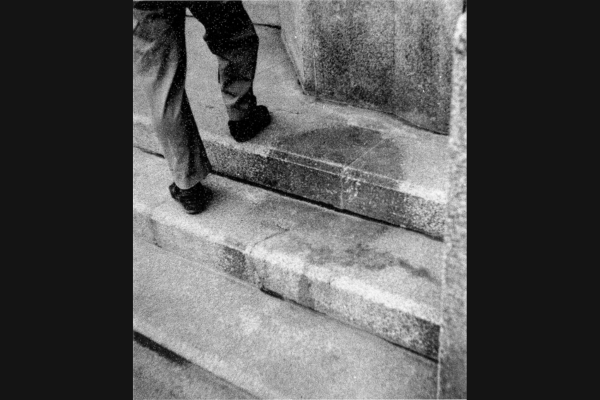








絶対零度にすることが出来ないってなんだか光速には絶対にすることができないみたいな感じですね。
光速の方は慣性質量の増加で光速にするために必要なエネルギー量が無限大になるという壁があるからでしたっけ?
絶対零度も同じように温度を下げるのに必要なエネルギー量が無限大になるのでしょうか…。
物体が光速になると外からは時間が停止したように見えるはず。
絶対零度も停止した世界なので同じと言えるかも。
すべての原子を基底状態にしないと絶対零度になりませんが
宇宙は背景放射やニュートリノが飛び交ってるからある程度基底状態の原子の割合が高くなった時点でそれ以上冷える前に別の原子が励起されるから無理
セビリア大学のこの発表の内容にも、「絶対零度(の近傍)でエントロピーが一定の値に収束する事」までは第二法則と熱機関モデルの仮定から導けるが、「その値が0である」までは導けないという旨が明記されている。
元々のネルンストの熱定理は「系を絶対零度に近づけるに従って、エントロピーの”変化量”であるΔsが0に収束する」という内容として理解される。
これを現在の形の熱力学の第三法則として、「そのエントロピーの値自体も絶対零度(の近傍)で0になる」と書き加えたのはプランクである。
今回の発表でもしっかり釘をさしているように、第二法則にある熱機関モデルを加えた前提から導いたのは、このネルンストの初期定理の方であり、今回の成果がそのまま今日の熱力学の第三法則の書き替えを促すような事にはならない。
そもそも純粋理論的に、ある理論を構成するいくつかの論理的条項から、別の条項を論理的に導けるのかという問題は、各条項の論理的従属性・独立性に関わる話である。
ネルンストらがやったのは古典的熱力学の範囲で自身が考えた新しい理論的拡張の条件(第三法則or初期定理)に対して、既存の頑強な法則(第二法則)と「矛盾しない」条件設定を考えただけである。
この「整合性を与える」という文脈は、「第二法則から第三法則が導ける」というような論理包含・論理的依存性などの議論とは全く異なっている。
これをしばしば物理学のコミュニティでは混同する場合があるのが悪質である。
その意味で当時のアインシュタインの批判(?)は論理的には的外れである事は明らかであり、彼が高名であるが為に話をややこしくしている面も否定できない。
物理理論的に具体性(?)のある(彼なりの)実体性を議論の前提に含めるべきだというのは、彼のある種の美学でしかなかった。
ネルンストの背理法的議論も、第三法則を既存の熱力学に「仲間入り」させる為の弁であって、第三法則が第二法則に論理的に依存している証明にはなっていない。
ただし、このあと1924年以降のアインシュタイン凝縮の理論などによって、ネルンストらが想定していた非量子論的な古典的熱力学よりも広い射程でも第三法則を「確認出来る」あるいは、「説明可能」であると結果的にわかったので、プランクの第三法則定式化および第二法則からの分離的理論記述の流れは妥当だったことになる。
まじでええええ?!?!?
って思ったけど有識者の方がいたので
ズボンをはいてお茶のんだ
機械科だけど熱力学第二法則までは習ったが、そもそも第三法則は習った覚えがないんだが‥
>理論的な熱機関(しかも仮想的なもの)を用いて絶対的な温度の基準を導入するアプローチです。
これって、進化じゃなくて退化なんですが。理想的なカルノーサイクルの熱効率で定義した温度は既に過去のもので、今は統計力学に基づいたエントロピーと内部エネルギーの偏微分で定義している。