「楽観的なカメ」は新しいものにも前向きだった――行動に表れた“気分”と“不安”のつながり
では実際に、カメたちはどのような反応を見せたのでしょうか。
まず、認知バイアス課題の結果では、15匹のアカアシガメのうち多くが、あいまいな位置に置かれたボウルに対しても、ある程度自信をもって近づいていく傾向を示しました。
とくに、ポジティブな位置(エサがある場所)に近い側に置かれたボウルには、より早く反応する個体が多く、ネガティブな側ではためらう個体が目立ちました。
これは、カメたちがエサのあるなしを正しく学習しているだけでなく、あいまいな状況に対して「楽観的」か「悲観的」かの傾向が現れていることを意味します。
次に、同じ個体について実施した「新奇物体テスト(見慣れない物体テスト)」と「新奇環境テスト(見慣れない環境テスト)」でも、個体ごとに明確な違いが見られました。
あるカメは、新しい物体にすぐに近づき、首を大きく伸ばして積極的に探索しようとしました。一方で、別のカメは長時間その場にとどまり、周囲の変化に対して慎重に反応していました。

研究チームはこれら3つのテスト結果を統計的に分析し、認知バイアス課題で“楽観的”な判断をしたカメほど、新奇テストでもより早く動き出し、首を大きく伸ばすなど積極的な行動をとる傾向があることを確認しました。
つまり、「気分が前向きなカメ」は「新しい環境にも自信をもって反応する」という対応関係が観察されたのです。
この結果は、アカアシガメにも我々と同じような「気分」があり、それが判断のしかた(楽観的・悲観的)だけでなく、不安の強さや行動にも影響を及ぼしていることを示唆しています。
これまで爬虫類は、「感情や気分が乏しい動物」と見なされがちでした。しかし今回の研究は、その思い込みを覆す重要な証拠になったといえるでしょう。































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)


















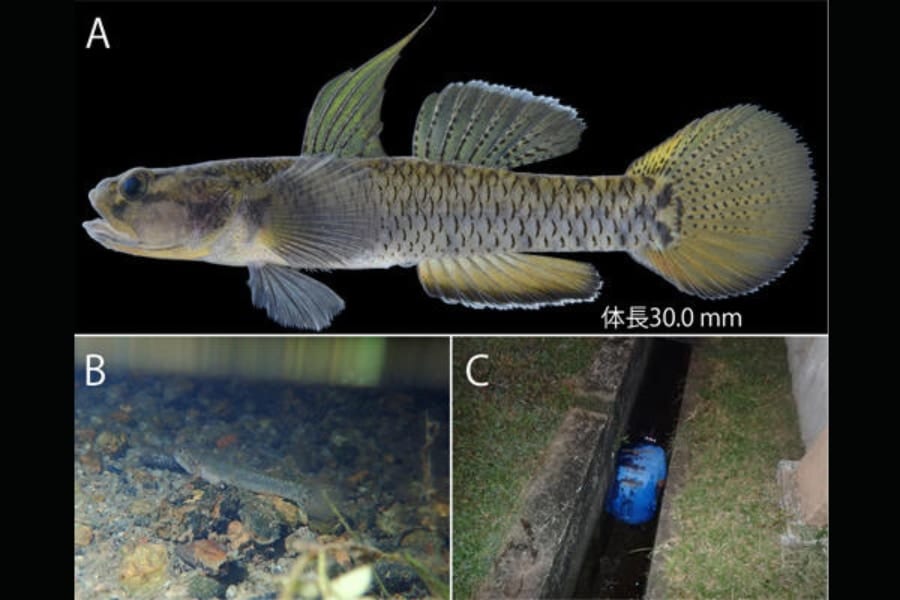


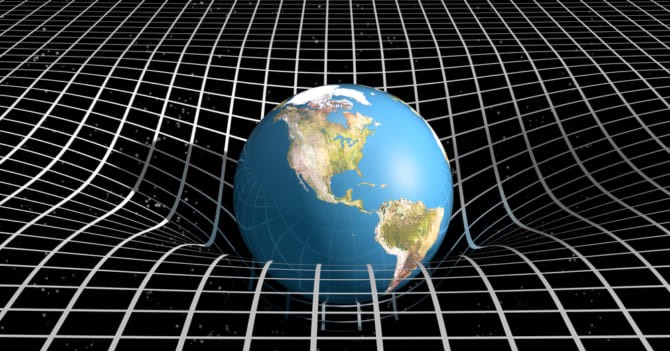






気分というのは同じ個体の中でも時とともに変化する内的状態を指すと思うのだが…。
楽観的か悲観的かの程度に個体差があるということなら、「気分」よりも「性格」のほうが適当な表現ではないかと思う。
元論文にどう書かれていたのかまで確かめる気にはならないけれど。
元論文だとmoodでした
飼い主「この子なに考えてるのかな…。」
亀さん「こいつ食ったらうまいのかな…。でもでかいから狩るのに苦労しそうだ…。」
やたら蚊に刺される私としてはこういう感じですね。
亀たちがみんなそうとは思えんがなぁ
呼べば来るし餌は亀ダンスで喜ぶよ
確かに家の亀もここに来ると餌がもらえるとわかってうるので合図を送ると行動、と目の位置が真っ正面を向く。
期待してるというのは分かる。
顔もなんか嬉しそうだよ。(笑
我が家のアカミミガメは父親に付いていったり、ストーブの前で足を伸ばして寝たりしてたのは楽観的な性格な子なんだな~
リクガメ以外でも実験して欲しい。
我が家にはフトアゴヒゲトカゲもいるので次はトカゲでお願いいたします笑
うちの亀さん、人が近づくと餌くださいと水槽に寄り掛かりパタパタしています。餌もらえるとやりません。
カメ、ニシアフ、レオパ、トッケイ、クレス、フトアゴを飼っている体感から言うと「おいしい、おいしくない、お腹すいた、好き、嫌い、怖い、嫌だ、やめろ、好きとは言わないけどまぁ悪くない」って感情はバシバシ伝わってきます
メダカですら、そのくらいの感情は伝わってくるから爬虫類ならさもありなん
アカミミガメを飼ってますが肉、エビなどを見せた時は興奮して指にも噛みつこうとして食べてる時は喜びの表情をします。
そして甲羅の汚れ落としはものすごく嫌な顔しますよ。
亀に気分があるかどうかの実験?クサガメのオスを飼ってるけど気分はすごく伝わってきますよ。子供にちょっかいかけられるとすごくイライラしています笑
我が家の亀、きゅうちゃんはもう5歳になりますが、とてもさみしがりやです。
私の事が大好きで抱っこするとうれションをしてしまいます。
凄い速さで追いかけてもくるし、ずっと見つめています。
猫ちゃんと同じくらいに可愛いです。
個体差があることはわかっても感情や気分がどうこうって実験には見えないんだが
亀は性格でしょ。
びびりも居れば、パリピも居る。
うちのはびびりで、カリカリの餌にさえびっくりして、匂いを嗅いで食べ始めます。
叩いたり、無理やり手足を出したりなどはしたことありませんが、すべての事柄に慎重です。ですが、わからないことが1つ。
アカミミなのですが、水を嫌います。
部屋を走ってる時が1番楽しそう。
他の生物よりもずっと水との関わりが深いと思われてるミズガメだけど、水が嫌いな個体がいると。
他の生物よりもずっと社会的活動が得意な人間でも、社会的活動がヘタクソで嫌いな個体もいるからね。個性、でしょうかね。
うちの近所にはタライほどのデカいリクガメ散歩させてる人がおるな。
ガレージで単車の整備してるとたまに見かける。
好奇心旺盛な子なのかガレージのフェンスを開けてると、
目キラキラさせて亀とは思えん速度でノシノシノシノシってうちの庭に入ろうとするのを、
飼い主がサッカーボール囲うように足でブロックしたら
すごくイヤそうな感覚が伝わってくるな。
渋々従ってる感じは犬も亀もあんまり変わらんように感じる。
ほとんどの生き物は感情も思考もあるでしょ
関心の低い人間には、それが分かりにくいだけで
気分は英訳からの直訳
意訳は個体差による性格的傾向
ちょっとアカミミ飼ってて気になる記事だったけど期待外れだった。
うちの亀は最近は扇風機の前がお気に入りで足を伸ばしてリラックスして数時間は動かないし水槽に戻して欲しそうなときは水槽周りを歩きまくりそして入れてあげると水面をバシャバシャして餌を要求してくる。
リクガメをつい最近まで数十年飼ってたので、哺乳類ほど豊かではないにせよ性格や感情らしきものが確かにあるとは感じていました。
ただ感情の存在を科学的に証明するのは大変難しいことだと思うので、それを極力理論立てて証明しようとしたこの実験はとても興味深いですね。
論文や研究について疎い人がいるみたいなので補足。
研究者にとって、「爬虫類にも性格がある」という概念は、”まだ主観”(実証されていない)情報。
論文の趣旨として、実証実験で確認されていない概念は”使えない”(記事の中でも分野として確認を行った事例がほぼ無いと書いてある)。
だから性格(超長期的な傾向)じゃなくて気分(短期的な傾向)で行動因子を纏めている。
今回は気分が存在することを確認する実験方法の”亀ver.が考案された”結果、亀に気分が有ると実証できた。
今後は別の爬虫類 や 性格などの個体差 の分析に研究が進めるだろうというのが騒がれた理由。
「気分」を確かめるなら同じカメを数日間追わなきゃならないでしょう。
明らかにこの実験は「性格」の実験としか思えないなぁ。
どこかの翻訳の段階でミスが起きてると思うなぁ。
体調によっても違うでしょ
体調が悪ければ動きたくないし、良ければ、ひとっ走りしたい個体も居る
我家のケヅメ陸亀は、障害物が有っても自分の行きたい方向に進みます。庭に有る雑草を食べながら進みます。
家のセマルハコガメは水槽で飼ってなくて放し飼いです。暗いとこが好きみたいで、自分の住処をちゃんと理解してて、餌が欲しい時、喉乾いた時は出てきて欲しがります。満足したら自分の住処に帰っていく、時には散歩したりしてて、それを繰り返してます。
そんな理解力があるのに、感情は持ってるはず。
蛇飼ってるけどしっぽのびーー以外でも感情感じる
コメ欄にこれだけの爬虫類の第一人者が集まってて、研究者相手に当たり前だろと言わんばかりに気分や感情はありまぁす!って御高説を垂れるのに、誰一人として科学的な実証や論文を出さないのはどうしてなの?
あなたの知識が世界を変えるのに
君はちょっと偏狭な気分になってるようだな。
コメント欄の人々が「え?現代の科学でまだそのレベルかよ!」てなるのも分からなくもないやろ?
仕事で年間五千〜一万頭以上、プライベートでは自家繁殖も含めて100頭以上の亀を飼育してきましたが、同種間であっても、個体差は大きく、また気難しい個体や人になれにくい種類はいます。そういう個体を楽観的で人馴れしてると同居させることで、臆病な正確から好奇心旺盛な個体へ変化しやすいことを体感してます。
拒食症の個体は、よく餌を食べてる固体を隣のゲージで飼育してやると、仲間がたべてるのを見て、食欲を回復する傾向も見られます。
話し街にしている陸ガメ達(アルダブラゾウガメ、アカアシガメ、ケヅメリクガメ、ギリシャリクガメ、絵水ムツアシガメ)と一緒にクサガメを放し飼いしていると、陸ガメ達の群れの中へ馴染んで一緒STAUBの前で暖を取り、一緒にキャベツをモリモリ食べていました。栄養が偏るのでクサガメだけは手で小魚を与えていたので、2本足と甲羅の縁の3点で立ち上がり、エサをおねだりするようになりました。
で、時々見ずに入れてやると、泳ぎ方を忘れてしまい、プカプカ浮いてバタバタ足をもがいて溺れそうになっていました。
生活スタイルまで変化して、水ガメであることを忘れているようでした。
学習能力がありますが、環境変化に一度適応すると、中々本来の環境には戻れないのかもしれません。
爬虫類の中でも亀は特にペットにされても、長く飼われる事に適応しやすい種類だと思います。
感情表現も豊かですし、買い主が作った環境に適応能力も高いですし、一度人に慣れると人を信用しすぎて、亀であることも忘れているのでは?と思う事もよくあります。
読者からの有益で面白いコメントを引き出す良いトピックでした。本文自体はあまり面白くなかったけど。