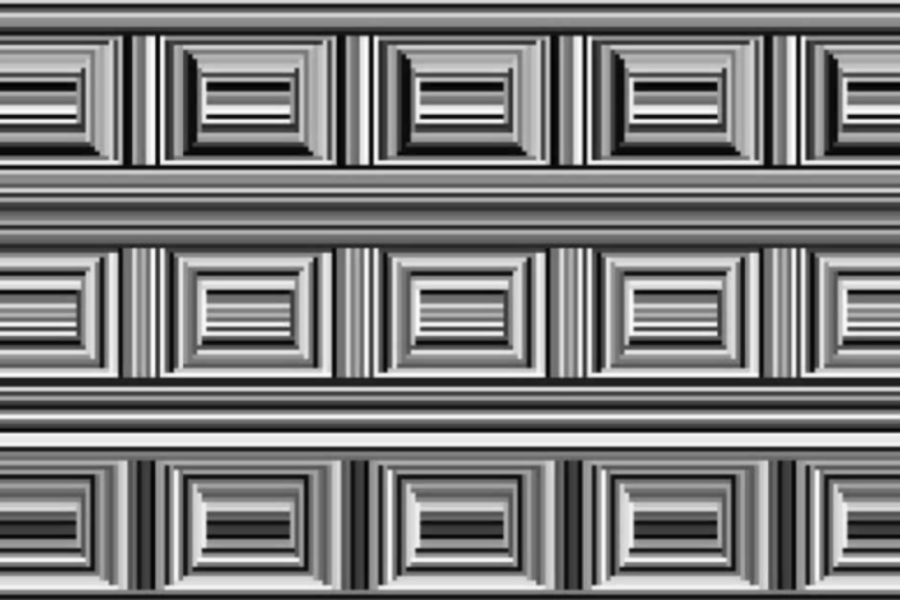fawningとは何か?“いい人”にならざるを得なかった理由
fawningは、他人に合わせて自分の気持ちや欲求を抑え、過剰に気を遣い、波風を立てないようにふるまってしまう心のパターンです。
優しい人、思いやりのある人、媚びへつらう人として評価されることがありますが、fawningには本人も気づきにくい深いストレスが隠れています。
この反応は単なる性格ではなく、子供時代のトラウマや家庭環境によって身についた無意識のサバイバル反応なのです。
たとえば、家庭が不安定だったり、親が怒りやすかったりする場合です。
また暴力や精神的な虐待があったり、親の愛情が「いい子でいること」とセットでしか与えられなかったりすると、子どもは「本音を出すと危ない」「相手の機嫌を損ねないようにするのが一番安全だ」と感じるようになります。
その結果、家族や周囲の顔色を常に気にして、「自分の意見や希望を言わずに我慢する」「相手の期待に応えようと無理をする」「衝突や対立を恐れて言いたいことも飲み込む」といった行動が、無意識のうちに身についていきます。
「相手に合わせすぎる」「いい人すぎる」「へつらう」といったふるまいは、自分を守るために体が自然に覚えた自動的な反応である可能性があるのです。
このような反応は、「意図的に八方美人になる」こととは異なり、「生き延びるための本能的な適応」といえます。
とくに幼い頃から、家庭内で「いい子でいること」や「自分を消してでも相手に合わせること」を求められた人は、大人になってもこのパターンから抜け出しにくくなります。
こうした「相手に合わせすぎる」反応が根付くことで、自分の感情や欲求を押し殺し、本来の自分を見失ってしまうのです。
では、大人のfawningは、どんな行動や考えとしてあらわれるのでしょうか。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)