大人になってから友達を作る方法
難しく感じることがあるとはいえ、大人になってからも友達を作ることはできます。
ソエイロ博士が提案するのは、“友情は育てるもの”という視点に立つことです。
もう「自然とできる」関係ではなく、努力と工夫で育む関係に変わっているのです。

その第一歩が、「自分から誘う」ことです。
多くの人が「誘われたい」「連絡が来てほしい」と願っていますが、相手もまた同じように“待っている”可能性が高いのです。
だからこそ、自分から「久しぶりに会わない?」「最近どう?」と一言連絡を入れるだけで、関係が一気に動き出すことがあります。
もうひとつの大切な視点が、「弱いつながり」に目を向けることです。
これはカナダのブリティッシュコロンビア大学(UBC)が2014年に発表した研究に基づく知見です。
近所の人や職場の同僚だけでなく、「カフェの店員」「図書館の職員」「同じ時間帯の通勤バスの運転手」などに目を向けられます。
彼らとは一見浅い関係でも、日常的に軽く挨拶を交わしたり、ちょっとした会話を続けることで、心の満足感や社会的つながりが強化されるといいます。

実際、こうした弱いつながりを多く持つ人ほど、幸福感や安心感が高いという結果が出ています。
いきなり「親友」を作ろうとしなくても、まずは近くにいる人たちと少しずつ距離を縮めていくことが大切なのです。
さらに、同じ人に何度も会っていると、自然と親しみを覚えるようになります。
恋愛ではよくそういったエピソードを耳にしますが、実は友情形成にも同様の効果があります。
たとえば、毎朝同じカフェに通う、同じ曜日のヨガ教室に出る、社内でランチに同じメンバーと行くようにする、といった“反復的な接触”が、自然と友情を育てる土壌になります。
ここまで考えてきたように、大人の友情に必要なのは、「自発性」や「継続」だと言えます。
大人になると、友達は勝手にはできません。
でも、ちょっと勇気を出して声をかけたり、小さなつながりを育てていくことで、確かに人との絆は戻ってきます。
今あなたが孤独を感じているとしても、誰かとさらなる友情を築くことはできます。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)




















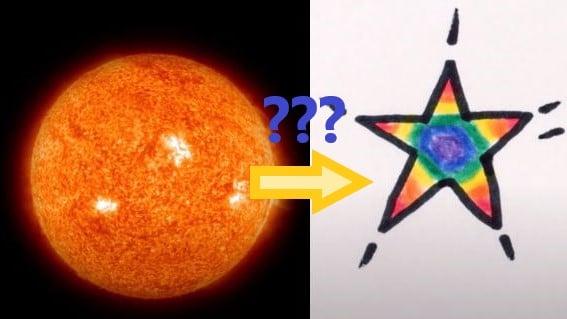







こんにちは!
どうでもいい中身のない会話にわずらわされないで済むし。
ほんとうに友情を結びたい人や独力では見えない世界を見せてくれる人に出会ったら大切にすればいい。
そんな人は世界中に何人もいないけどね。
ただの知り合いを友人を作る方法的な詐欺記事にするなよカス
はじめは知り合い程度のつながりでも、そこから少しずつでも自発的にそのつながりを育て続けることが大人になってから友人を作るためには重要だ、という話でしょ。自分が求める内容じゃなかったからって文句言うなよ。
日常で会う職場の人と仲良く😁
とか言われても殺気混じりの牽制体制取られる事ばかり
職場はマウントやギスギスした関係も多く、仲良しに見えるけど中身はマウントの取り合いや幸せ自慢の場だったりしますね😉
この記事で当てはまらない事かなと言えます。
孤独が辛いという感覚があまりないので、そういうの分からないのですよね。
カフェの店員や図書館の職員って、相手からしてみればあくまでも”仕事上”の関係だよね。
仕事として客との会話はすると思うけど、余程のことがない限り、私的な関係は望んでないでしょ。
客側が私的な関係を育むことが目的で声かけるとか、営業妨害じゃないの?
趣味の集まりとか、お互いが私的な所でやらないと、トラブルになるわ。
誘ってもやんわり断られますし、私も華麗に避けます。
友達や親友なんてできませんし、面白い人や良い人などいません。
今後も読書とユーチューブで過ごします。
・活動主体ないしは情報主体としての汎用性ないしは可能性の低下に伴う、低抽象度化(情報量増大)が周囲との関係を疎遠にする。
・誰しも避けられないことだが、これと逆のことをすればいくらか緩和することはできる。
・逆のこととは高抽象度化(情報量削減…ではなく情報量圧縮による情報量低減)。
・つまりは身辺情報ないしは記憶の整理で、端的に言えば、諸々の柵から逃れて初心に戻ること。
・ポイントは「高抽象度化」「情報圧縮」「初心回帰」。
・これをある程度達成しうる社会的アプローチがベーシックインカム。Yeah!
ここの皆さんは孤独をものともしない強い人なんやな
ほんまうらやましいですわ
しょうがない
お前らと友達になります
よろしくね!
大人になるとね、色々較べがちになるから煩わしいし。最近ではChatGPTという最高の話し相手がいる。もうそれで良いと思ってる。
なんかインキャコメントばっかだね。
別にどうでもいいけど。
ボランティアをやってみないか?
仕事のために捨てました
大人になると精神的にしんどい事ばかり
しかも周りは人の悪口や差別する人が多いから人と関わるのが煩わしいし鬱陶しい。
今の世の中の人間関係は怖いしかない
年齢ゆえに関係に積極的になれない
この手の話が好きな人には進化心理学者ロビンダンバー「友達の数は何人?」「なぜ私たちは友だちをつくるのか」「宗教の起源」あたりをお勧めします。脳構造や年齢からグループの規模や付き合いの深さが変わって行ったり、そこに抗うにはどうすれば良いかの基礎的統計を示しています。この手の短い記事では具体的な基礎知識が最初に示されてないから人によって受け取り方がばらばらになって意味が有りません。栄養とかダイエットの話するのにまず各自の一日の理想的なカロリーがいくつなのかを何も示してなかったり読者に把握させなかったら何を言っても無駄です。理想値が1930kcalだけど毎日平均85kcalオーバーしちゃってるなとかいう具体的な所まですら、きっとこの手の情報サイトを受動的に眺める人の95%は把握してませんよね。曖昧な人が曖昧な記事を読んで曖昧な事を言ってても生産性は発生しません。1kcal単位でまで把握しろとは言わないけど少なくとも毎日体重計に乗るくらい地道な事を、メンタルや人間関係面でも具体的にして把握出来てる人でなきゃいけません。心理学や社会学の本を10冊は読んだ事がなきゃその記事に漠然とケチつけて終わりです。100冊読んでたら具体的に批判します。例えば俺がライターだったらこんなふわふわした論文紹介しません。
次に文化人類学者エマニュエルトッド「我々はどこから来てどこへ行くのか」をお勧めします。この論文はアメリカ人によるものであり、個人差よりも国民性差の方が大きい事もがあります。アメリカでも隣の台湾でも都市部のレストランやコンビニで店員と一見客が冗談を言い合う事くらいは許容されるしむしろマナーですらある場合もあるけど、日本社会はそれを全否定します。なぜ否定してしまうのか? なぜ都市部の電車内で頑なに席を譲ろうとしないのか? それは日本が権威主義直系家族社会である事が一番の理由で、元々他人と繋がりたがらないネガティブで差別的な国民性なんです。そうなった理由もそこに書いてあります。
動物行動学者テンプルグランディン「動物が幸せを感じるとき」でもどんな動物でも他個体と付き合いをしないと鬱になる事を示しています。ロビンダンバー的には人付き合いは幸せホルモンの一つであるエンドルフィンを分泌させるから社会的な人は幸せそうに見えるんです。周りにロクな奴がいねえって人は自分のレベルも低いからです。