量子トンネルの中は想像以上にダイナミックだった

本研究によって、長らくブラックボックスとされてきた量子トンネル内部での電子ダイナミクスが明らかになりました。
電子がトンネル内部で何もせず「瞬間移動」しているのではなく、実際には内部で障壁の壁との相互作用を起こし、エネルギーを獲得していたという事実は、量子世界が私たちの想像以上に豊かな物理現象で満ちていることを示しています。
この発見は基礎科学として興味深いだけでなく、応用面でも大きなインパクトを持ちます。
電子トンネルの過程を詳細に理解できたことで、今後は電子の動きをより精密に制御できる可能性が開けました。
例えば半導体や量子コンピュータ、超高速レーザーなど、トンネル効果に頼る先端技術の効率や性能を一段と高めるための新しい指針となるかもしれません。
実際、研究チームは、この研究成果は電子が原子内の障壁を通過する際の挙動を理解する重要な手がかりになると評価しており、今後のさらなる制御技術の発展に期待を寄せています。
最後に、今回の成果が教えてくれるのは、「トンネルの中」は決して空っぽの空間ではないということです。
従来ブラックボックスと考えられていたトンネル内部は、実際には電子が行き来してエネルギーを蓄えるという豊かな現象が繰り広げられていました。
ミクロの世界は「何もない空洞」どころか、私たちの想像以上に活発でダイナミックな舞台だったのです。




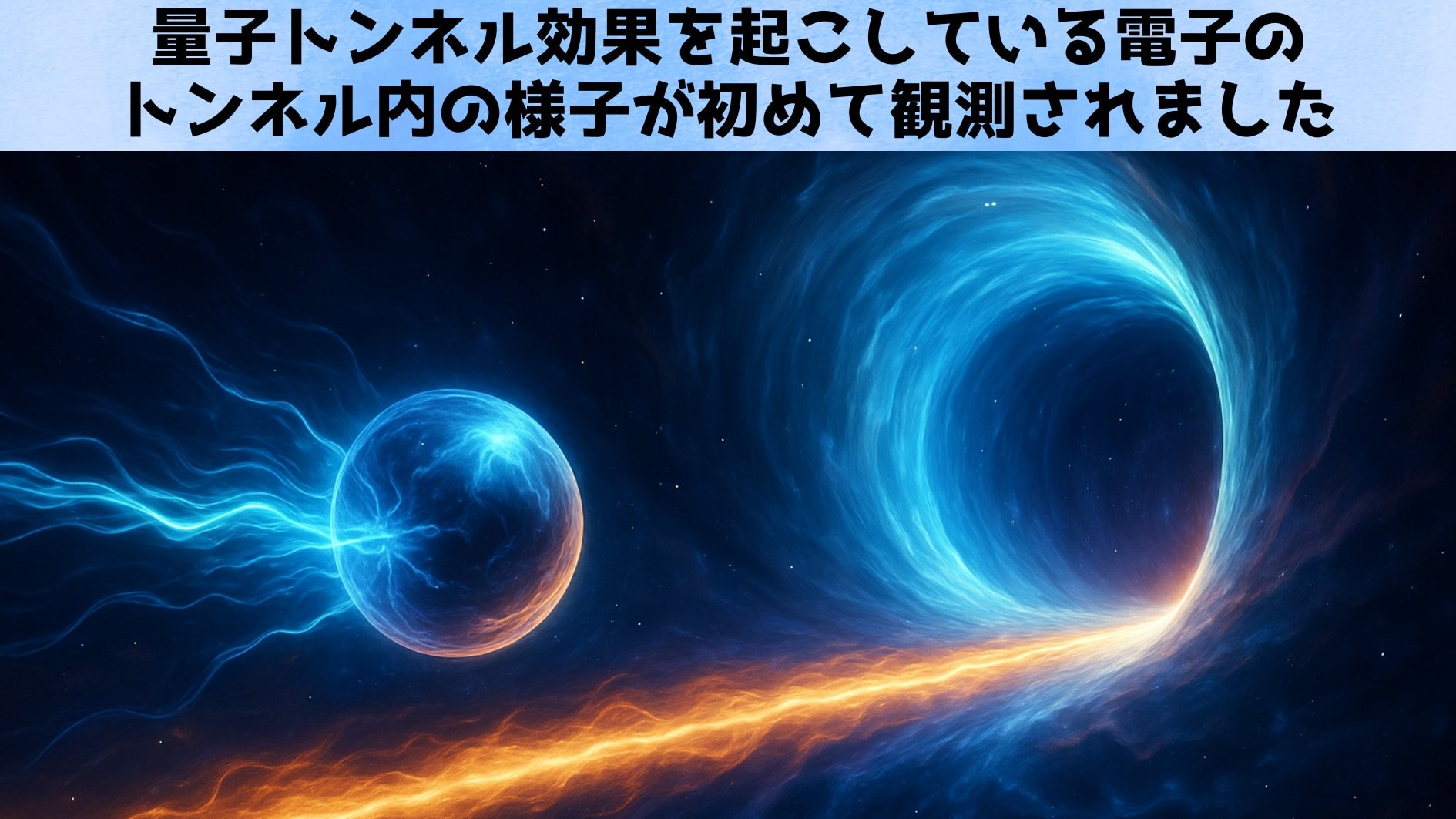

























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)















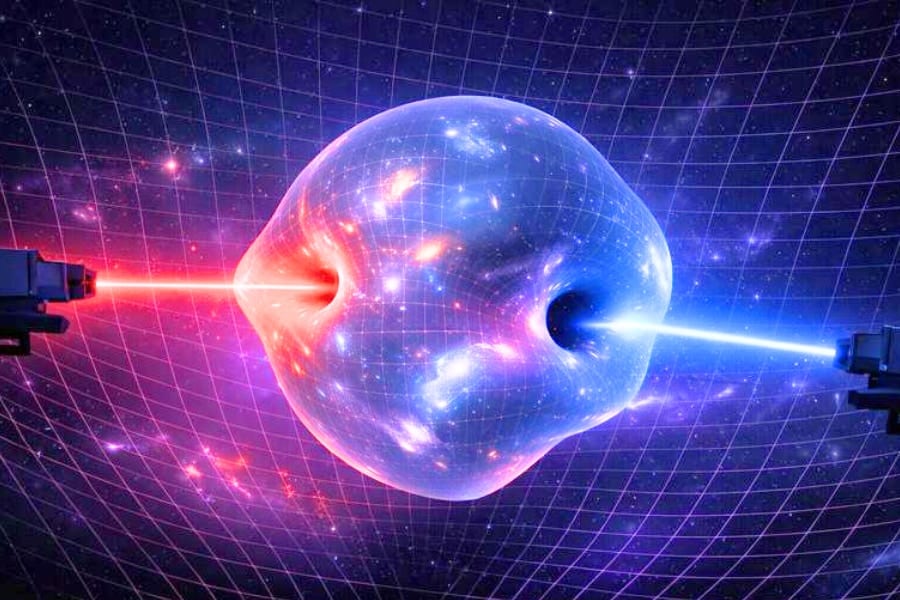












つまり打ち返しくれる親原子核がそこにいないと量子トンネルは成立しなくなりますし、逆に打ち返してくれる原子核をそこに持ってくることができれば確定で起こせるってことでいいのですかね。
マリオの壁ぬけバグ的な感じか
>電子は壁の中で一旦戻るような反射を経験し、高エネルギーの状態へと昇ってから外へと出ている
豊かであるとはどのような状態のことを表現しているのでしょうか
『電子がトンネル内部で何もせず「瞬間移動」しているのではなく、実際には内部で障壁の壁との相互作用を起こし、エネルギーを獲得していたという事実』
これを豊かであると表現することに、違和感というほどではないのですが、なぜ豊かと表現したのかがある気がするのですが
ミクロな世界で情報のやり取りが複雑な感じで、なぜ今まで隠されていたかのようにトンネル効果と認識されていたのか
どのように再認識されて、トンネル内部を記述するに至ったか
今まで通り、瞬間移動のように見える現象とも言っていい解釈になっているのか
詳細をサラッとでも説明が欲しく思う。その内容は著作権か何かで閲覧できないのでしょうか
論文であるなら、中身を見れなくとも題名と、できれば参照先を付けてほしい
なぜそこはスルーなのか。知りたきゃ自分で調べろ感。知る人はおのずと知りえるから別にいいし
あまり、興味のない人は、詳細の欠落にすら無関心だから成立することを期待しているのか
それが、このサイトの効率化なのですね
この記事に付いているリンク先に、論文名など 書いてありましたよ(以下)
Unveiling Under-the-Barrier Electron Dynamics in Strong Field Tunneling
Tsendsuren Khurelbaatar
1,2,*,†,††, Michael Klaiber
3,*,‡, Suren Sukiasyan
3,4,§, Karen Z. Hatsagortsyan
3,∥, Christoph H. Keitel
3,¶, and Dong Eon Kim1,2,**,‡‡
イメージとしては原子核を用いた電子のスイングバイという感じがしました。そうなるとボイジャー探査機の様に、スイングバイ毎に電子はエネルギーを高めて、障壁を超えるに足りるエネルギーを得て初めて外に飛び出すという事でしょう。
であればスイングバイしやすい原子核の種類や、最適な原子核の数、即ち壁の厚みも厳密に規定できそうです。
すり抜けるって表現がよく使われるけど、こうなると飛び込む粒子と飛び出す粒子は同じ人なんだろか?
例えば、玉突き形式、椅子取りみたいに枠があぶれた者がしぶしぶ出ていく形式、一旦エネルギーに変換された後再形成される形式、ってことはないんだろうか
エネルギーって波打つ液体のようなイメージがあるので、何というか、コップいっぱいの液体にビー玉を落とした時に溢れた液体がドロっとビー玉のような何かに成り代わって飛び出すような気味悪い現象が起きてそう
時に、物体が極々低確率ですり抜けるみたいなことが大真面目に議論されてたりするけど、トンネルを「すり抜ける」って前提が間違ってそうだな
個人的にはゲームの壁抜けバグに近い印象を受けました。
ゲーム内で壁内部に出現してしまった物体は、壁に埋まった状態でコリジョンの反発を受けて、想定外のエネルギーを受け取ってふっ飛ばされるんですけど、これと似た状況が現実に起きている?