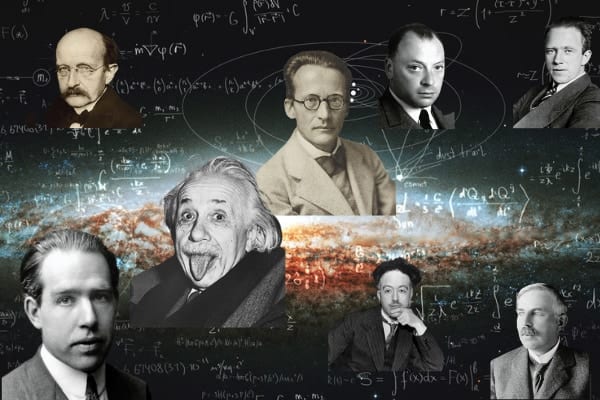なぜ今、「量子もつれ」の再利用が求められるのか?
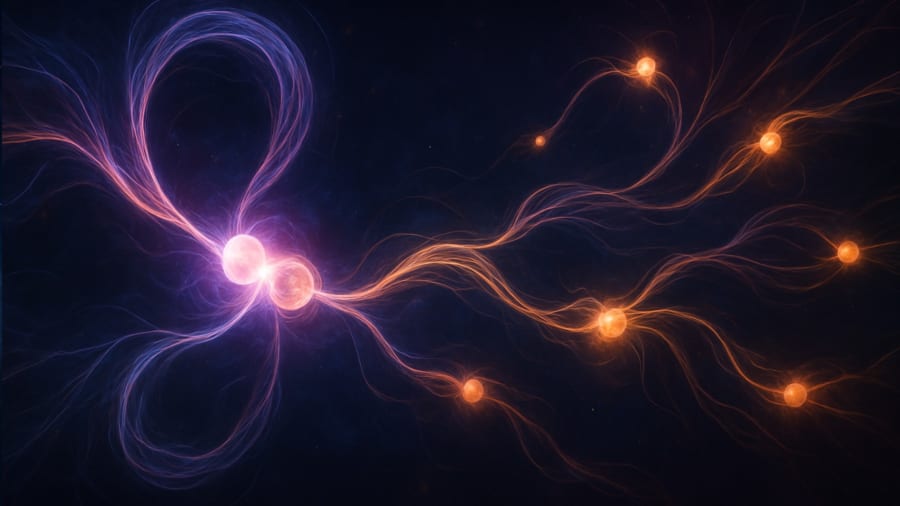
離れていても相手のことを感じられるような不思議なつながりを、誰もが一度くらいは想像したことがあるのではないでしょうか。
実は量子の世界では、粒子同士がまさにそんな見えない絆で結ばれることがあります。
この不思議な現象は「量子もつれ」と呼ばれ、ある粒子に変化を加えると、どんなに離れていてもペアになったもう一方の粒子が瞬時に影響を受ける、という奇妙な性質を持っています。
量子もつれの存在が初めて知られるようになったのは、今からおよそ90年も前、物理学者のアインシュタインたちが量子力学の理論に疑問を呈したときのことでした。
しかし、当初の疑念にもかかわらず、量子もつれはその後の実験で実在が証明され、現在では量子通信や量子暗号、量子テレポーテーションなど最先端技術の基盤となっています。
つまり、量子もつれは量子情報技術においてなくてはならない「資源」なのです。
しかし、この量子もつれという資源は生成するのが簡単ではありません。
一般的には、まず一つの場所で粒子同士を絡ませる特殊な操作を行ってもつれを作り出し、その後、その粒子を離れた二地点に届ける必要があります。
いわば一回の作業で使えるのは一組の利用者だけ、という不便さがありました。
これはちょうど、一度組んだ「糸」はその二人以外の誰とも再び結び直せない、というイメージに近いものです。
こうした現実の難しさがある中で、量子技術の利用が拡大するにつれて、貴重な量子もつれの資源をもっと効率よく、多くの利用者で共有できないかという問題が浮上してきました。
そこで研究者たちは次のような疑問を抱きました。
「すでに作られた一組のもつれを使って、複数のペアに順番にもつれを『分けて』いくことはできないだろうか?」
例えば、量子通信をしたいCさんとDさんがいて、彼らは今すぐにもつれを共有したいけれど自分たちだけではもつれを作り出せない状況を考えてみましょう。
ところが、少し離れた場所にいる別のペア(AさんとBさん)は既にもつれた状態を持っていて、これをうまく利用できるなら、わざわざ新しくもつれを作り直さなくても済むかもしれません。
もしCさんがAさんの粒子に接触し、DさんがBさんの粒子に接触することで、A–B間のもつれを活用しながら間接的にC–D間にもつれを作り出すことができたら、効率的だとは思いませんか?
実はこうしたアイデアは一見簡単そうですが、量子力学の理論的には意外と複雑な問題です。
なぜなら、一度あるペア(ここではC–Dペア)がもつれを受け取ってしまうと、元のA–Bペアが持つもつれは必ず一部失われてしまうからです。
また、もつれを渡す操作の過程では、AさんとCさんの粒子間や、BさんとDさんの粒子間にも新しいもつれ関係ができてしまうことがあります。
ところが、こうして生じた新しいもつれは、別のペアには利用できない性質を持っています。
言い換えると、こうした余計なもつれは「無駄」として蓄積され、貴重な資源が減ってしまうことにつながります。
これが繰り返されると、いつか必ずもつれが底をついてしまい、リレーが続けられなくなってしまう可能性があるのです。
果たして、もつれを渡し続けることには限界があるのでしょうか?
それとも、渡す量を小さくすればどこまでも多くのペアにもつれを渡し続けることができるのでしょうか?
研究者たちは、この問いを解明すべく具体的な理論モデルを構築して検証しました。
その結果、一見矛盾するようですが、理論上はもつれを分ける量を極めて微量に設定することで、多数のペアにもつれを分け与えることができる可能性が示されました。
ただし実際には、もつれを分け与えるペア数を増やすほど、一つ一つのペアに行き渡るもつれの量が非常に小さくなってしまうため、実用面での限界が出てきます。
それでは、このような理論上の可能性は具体的にどのような仕組みで実現されるのでしょうか?




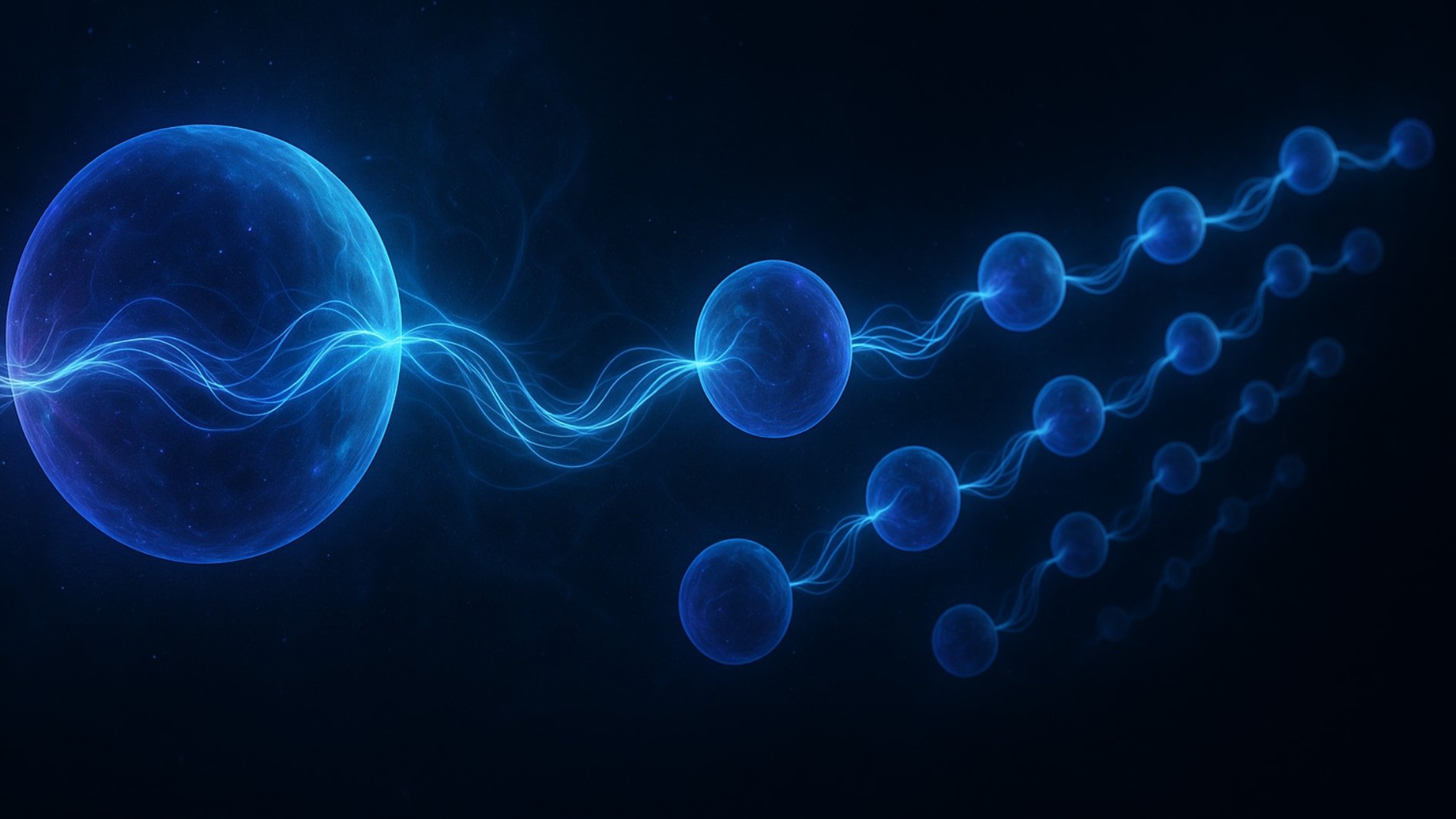


























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)