情報過多と美意識の変化が「虚ろで冷ややかな視線」を生む
Z世代の無表情の背後にある心理の残り2つを見てみましょう。
3. 情報過多と感情の麻痺
Z世代は、SNSやネットメディアを通じて、日々大量の動画、写真、感情的コンテンツに触れています。
こうした過剰な刺激に長期間さらされることで、感情の起伏が乏しくなる「感情の平坦化」が起こりやすくなります。
Z世代の無表情は、情報過多による感情の疲弊が生んだ適応的な反応とも言えるでしょう。
4. 美的価値観の変化

従来のSNSでは、明るく整った顔立ち、加工フィルターによる美しさが“良い写真”とされてきました。
しかしZ世代は、そうした「完璧な美」ではなく、「素のままの自分」に価値を見出しています。
過剰なまでの過剰なまでの華やかさを拒絶して、生々しさ、曖昧さ、ぎこちなささえも受け入れているのです。
Z世代にとっての無表情とは、単に無関心を装っているのではなく、「飾らない強さ」の象徴なのです。
ここまでで心理学者ウェル博士が分析する「Z世代の無表情」の理由を考えました。
彼らの「無感情な視線」は、感情の制御、文化的選択、デジタル疲労への適応、そして美意識の変革という、複合的な背景をもつ非言語的な表現です。
それは、上の世代の常識では測れない、新しい自己表現のかたちなのかもしれません。
Z世代の視線は、静かだけれども強く、「常に露出が求められる時代」を映し出すメッセージなのです。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)





















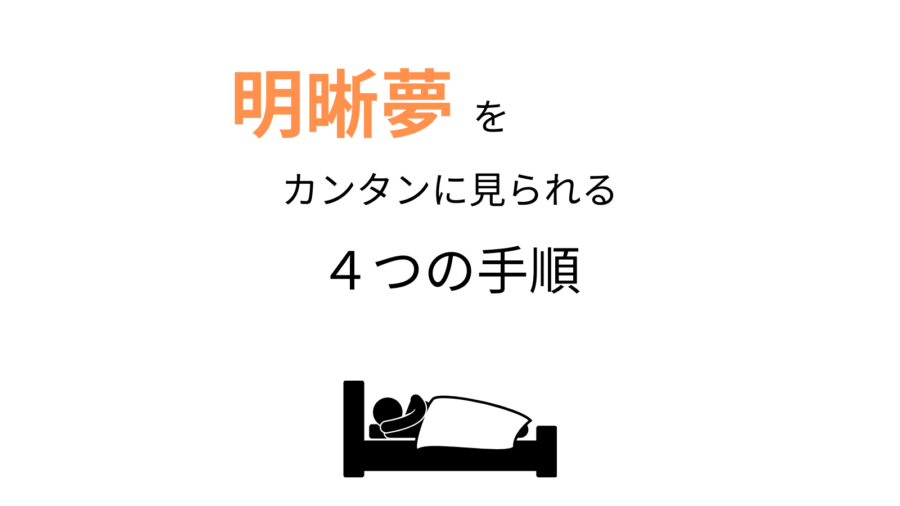






それこそ以前に記事に取り上げていた。『SNSを見る時間が長いほど、日中に「ぼんやり」しやすくなっていた』に繋がるのではないでしょうか。
私はSNSの発展と共に歩んで来ましたが、生まれた時からSNSが存在している世代とでは目に見えるほど違いそうですね。
自己理解ゆえの俯瞰的視点なのか、はたまた本当にただの一種の防衛本能なのか。
まるでソビエト時代のロシアだ。
初対面には無表情、接客でも笑顔なし。
笑顔は本物の信頼にだけ許されるもの。
誰にでも見せる笑顔は、軽薄で偽物と見なされる。
笑えばいいと思うよ、と言ってくれる人はいなさそうではあります。
世代で括ってしまうとまるで人間が変わったかのような印象になってしまうが変わったのは徐々に変わっていく環境であってある年から人間の行動が急に変わる訳ではない
世代でくくるという行為自体が誤解や間違いを招く良くない分析手法であると思う
無表情が過剰な評価や判断から自分を守る役割があると言うなら反省すべきは間違った評価をしてしまう我々、他の世代ではないだろうか
感情の起伏が乏しくなるのは冷静な判断がしやすくなるという意味でそこまで悪い事には思えない
犯罪をするな、詐欺に騙されないように警戒しろと注意喚起をするならば感情の起伏が乏しくなるのは当たり前の話であり彼らから表情を奪ったのはむしろ我々ではないか
もし感情の起伏の乏しさを問題視するのであれば我々他の世代は自分さえ良ければいいという思考をやめて彼らに不必要な警戒は必要ないと思わせる努力をすべきだ
単に発達障害の割合が増えた、という理由はないだろうか。
無表情なだけでは違和感を覚えない。やはりそこには他人への思いやりや配慮の常識的レベル以上の欠如が大きく関係すると思う。
私はz世代ですが今まで会った同世代の中に発達障害の人は2~3人でした。また、私から見ると今の50~60代の人のほうが発達障害を持っていそうな人が多いように思います。つい先日も電車の中で、わめいている人を見かけました。無表情=発達障害と決めつけるのは間違っていると思います。
相手の中で感情が駆動しているので、自分は感情を発動する必要がないという、感情のアウトソーシングの延長