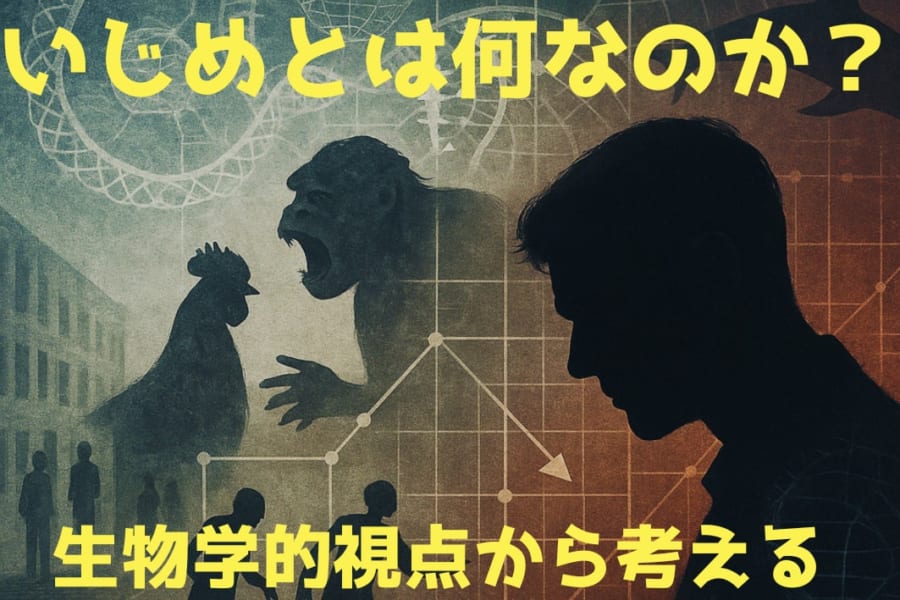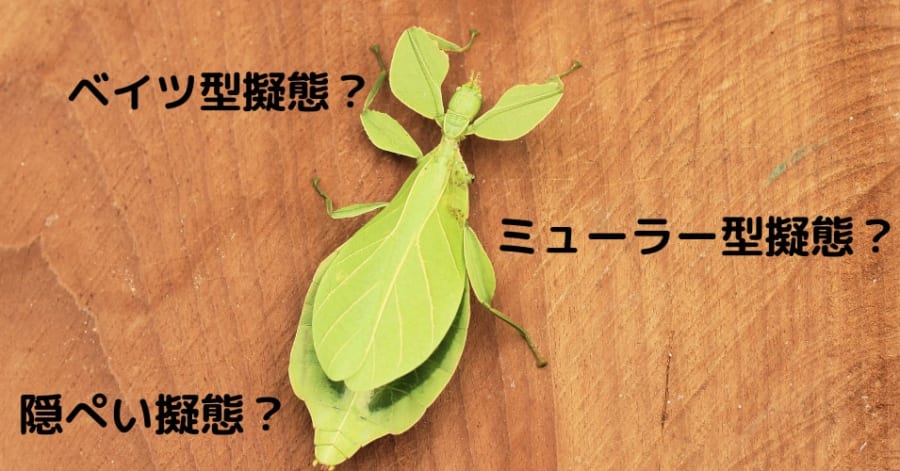なぜ警報の空振りが人々を疲弊させるのか

災害警報は、危険が差し迫ったときに人々の命を守るために発せられる重要な情報です。
確実に人々を安全な場所に誘導するために警報は、被害規模を最悪の状況に併せて見積もる必要がありますし、避難の時間を十分に確保するためにもできる限り早く出す必要があります。
そのため、警報の予想より災害の規模が小さかったり、空振りに終わることもありますが、むしろそれは喜ぶべきことです。
しかしそうした場合、現実には「結局、大したことなかったじゃないか」という批判が繰り返されるようになります。こうした現象は心理学では「オオカミ少年効果(Cry Wolf Effect)」と呼ばれ、警報が外れる経験が続くと、人々が次第に警報に注意を払わなくなるとして警戒されています。
たとえば、1998年に発表された研究では、米国サウスカロライナ州の住民が、ハリケーンに関する避難命令に対して徐々に無関心になっていく様子が報告されています。同様の事例は、2008年に発表されたフロリダ州で繰り返されたハリケーン警報の影響でも報告されおり、多くの人々は空振りし続ける警報に対し、危機に備える意欲を失っていくことが示されています。
このような心の状態は「コンプラセンシー(Complacency:油断)」と呼ばれ、警報が出されても「どうせ何も起きない」と高をくくる気持ちが、災害時の準備や避難の遅れに直結します。
こうした“油断”が起きるのは、警報の持つ「確実性のなさ」に起因します。
たとえば津波や地震の警報は、数分から数十分という極めて短い時間の中で判断を迫られるため、予測には必ず誤差が生じます。気象庁もその点を理解しており、万が一に備えて「念のため」の警報を出すことも少なくありません。
これは、いわば“リスクを最小化するための勇み足”なのですが、一般の人々にとっては「狼が来るぞ」と言い続けて何も起きない状況と同じに見えてしまうのです。
社会学者マイレティらがまとめた報告書では、警報の頻度が高く、かつその多くが空振りだった場合、受け手の「信頼感」や「緊張感」は次第に鈍くなるという現象が詳しく記されています。しかも、それが何度も繰り返されると、「今度も大丈夫だろう」と自己判断してしまい、いざ本当に避難すべきときに行動できなくなるのです。
このようにして私たちの中には、「警報慣れ」や「警戒疲れ」とも言える心理的な反応が育っていきます。それは怠惰なわけでも自己中心的なわけでもなく、私たちの脳が「繰り返しの無害な刺激」に対して自然に生み出す“防御反応”とも言えるものです。
けれど、自然災害においては“1回の油断”が命取りになることがあります。だからこそ、空振りを「無駄だった」と片づけずに、「命を守れたから良かった」と捉えられるようになる必要があります。
また現代ではSNS上の反応も、人々の避難行動を妨げる恐れがあります。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)