避難しない人を正義感で非難する行為の弊害

災害時、あなたが避難しなかったとき、周囲から「なぜ逃げなかったのか」と責められることがあります。逆に、避難した人が「大げさすぎる」「ビビりすぎ」と言われることもあります。
このように、警報への対応をめぐっては、避難するかしないかという「個人の判断」が、社会の目によって評価されてしまうことがあります。特にSNS時代では、この傾向が強まっています。
ある人は「警報が出たから避難するのが当然」と思い、またある人は「状況を見てから判断したい」と考える。そのどちらも一理あるにもかかわらず、他人の行動に対して“正義感”から批判的になってしまうことがあります。
ところが、この“正義”が、次の災害時に思わぬ副作用をもたらすことがあります。
それが「心理的リアクタンス(Psychological Reactance)」と呼ばれる、人が「自分の自由を奪われた」と感じたとき、反発するような態度や行動をとる心理です。
たとえば、「みんな避難しているのに、なぜあなたは逃げないの?」と強く言われた人は、「自分で考えて行動してるのに、押しつけられたくない」と感じ、結果的に警報に従わなくなることがあります。
避難を促す“善意の圧力”が、かえって逆効果になるのです。
過去の研究では、繰り返される警報や避難圧力が「一方的な命令」として受け取られるようになると、人々は警報情報そのものに対して反感や無関心を抱くようになることが報告されています。
これは、「警報に従うかどうか」という単純な話ではありません。重要なのは、人々が納得して行動を選べる環境があるかどうかです。
災害時に適切な行動を取るには、信頼できる情報が必要です。しかしその信頼は、「警報の精度」だけではなく、「自分の判断を尊重してもらえている」という感覚にも左右されます。
誰かに命令されて避難するのではなく、「自分が納得したから避難する」――その心の動きが、次の行動を左右するのです。
また近年の研究では、避難行動の判断は「個人」だけでなく、「家族」「地域」「SNS上の反応」など、社会的ネットワークの中で形成されることが多いと指摘されています。つまり、避難の決断は一人で完結するものではなく、周囲の反応や評価を通じて形づくられているのです。
だからこそ、私たちは災害時に「正解は一つ」という考えにとらわれすぎず、「それぞれに事情がある」「判断の仕方も多様である」という視点を持つことが求められます。
「自分と違う行動をしたからといって、それが間違いとは限らない」そんな寛容さが、次の大きな災害で命を守る行動につながるかもしれません。正義心から安易に人の判断を避難しないようにすることも災害時には重要なことです。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
















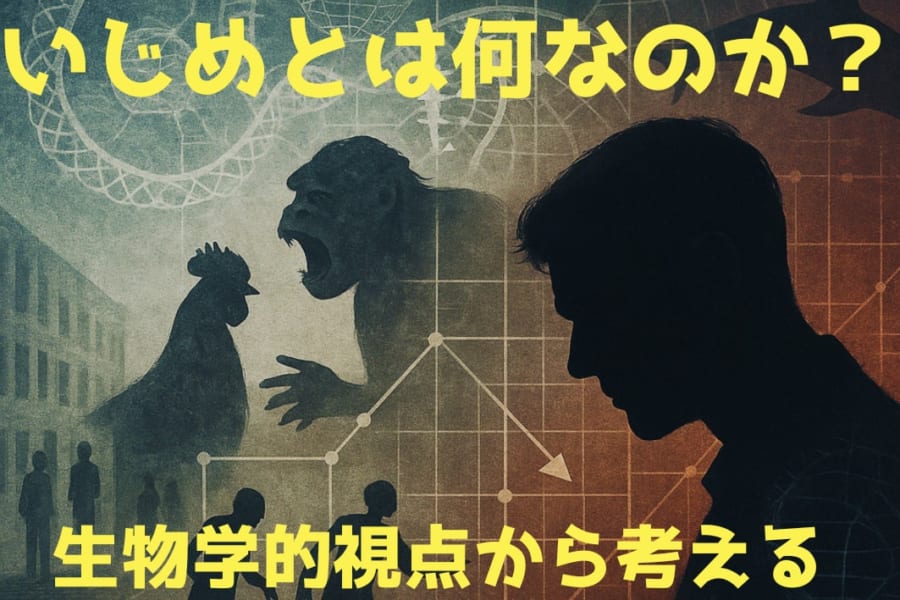











正義感は麻薬ですからね、麻薬である以上、すでに中毒になっている方には何もできることはないわけでして。
なにかに溺れる人はそれ以外溺れるものがないから溺れるわけですから、代わりになるものを用意してあげないとね。
熊谷晋一郎は「自立とは依存先を増やす事」と言います。単一論点政党や独裁国家が長続きしないのはイデオロギーを特定の事に全振りしててハイノスクハイリターンだからだし、個人でも得意苦手や好き嫌いがあると心身病みやすいのは味覚嗜好とも同じですね。しかし人々はノイジーマイノリティに振り回されるのはパランスの良さ≒地味さを低評価してしまうからです。分かり易い事、スカっとする事にはろくな知恵は詰まってません。事件が起きれば「さっさと死刑にしろ」移民話になれば「全員追い出せ」という主張をする短絡的・二極的思考をする奴らに政治を任せたら国があっと言う間に滅びます。「食事はバランス」というのは栄養を万遍なく摂るというよりリスクを万遍なく散らすためです。四毒言ってる奴らも例えば乳製品を割けて腸ばかり大事にしてたら胃に防塩バリアを張れなくなってピロリ菌祭りになって胃癌で逝きます。日中韓はなまじ農業に向いてたために田畑に人が直接食える野菜を植え、酪農地にはしなかった結果、冬の保存食を塩分の塊みたいな漬物に頼って胃癌罹患率柄界トップクラスの地域になりました。塩分摂取量は世界平均レベルなのに、地理条件への過剰適応としての味覚嗜好の偏りで早死にしていたんです。乳製品を割けたいならキムチや漬物も避けなければいけないのに、四毒言いたがる奴は健康意識が高いんじゃなくてナショナリズム感情が強いために自らバランスを崩しています。政治経済などの思想に於いても偏りが強いとリスクも大きくなるよという話です。