やや詳しい解説(専門家向け)
本研究は、単一光子がポンプとなる自発的パラメトリック下方変換(SPDC)において、光の軌道角運動量(OAM)が1量子ごとに保存されることを、自由空間を使ったカスケードSPDCで実験的に確かめたものです。従来は強いレーザーポンプを用いたSPDC実験で平均としての保存しか確認できませんでしたが、今回は「1個の光子」レベルで直接的に保存が成立することを観測した点が大きな新規性です。
SPDCにおける非線形相互作用は、次のようなハミルトニアン(エネルギーを表す式)で記述されます。
H ∝ ∫ d^3r χ(2)(z) E_p^(+)(r,t) E_s^(+)(r,t)† E_i^(+)(r,t)† + H.c.
ここで H.c. はエルミート共役を意味します。各電場はラゲール・ガウス(LG)モードに展開され、角度 φ に対して exp(i l φ) という渦位相を持ちます。そのため、モードの重なり積分は角度方向でデルタ関数条件を生み、次のような選択則が現れます。
l_p = l_s + l_i
つまり、ポンプ光のOAM量子数 l_p が、信号光 l_s とアイドラ光 l_i の和に等しくなる、という保存則です。
OAM演算子は次のように定義されます。
L_OAM = ħ Σ_j Σ_{p,l} l · n_{p,l}
ここで n_{p,l} は「そのモードにいる光子の数」を表す演算子です。このOAM演算子とハミルトニアンの交換関係を調べると、
[L_OAM, H] = 0
となり、OAMが保存されることが理論的に保証されます。重要なのは、これは期待値(平均値)だけでなく分散(ゆらぎ)に対しても成立する点です。
実験では2段のSPDCを組み合わせました。第1段のSPDCでは、波長524 nmの連続波レーザーを入力し、783 nmと1588 nmの非縮退光子ペアを生成しました。1588 nm光子は「到来通知」(ハーラルド)に使い、783 nm光子を第2段SPDCのポンプとしました。このポンプ光には空間光変調器(SLM)で渦位相を与え、l_p = 0, -1, +2 などのOAMを持たせました。第2段のSPDCではリチウムニオベート結晶を用いて1534 nmと1600 nmのペアを生成し、それぞれのOAMを測定しました。
結果として、l_p = 0 の単一光子ポンプでは、168時間の測定で57ペアが得られ、その約76%が「l_s = -l_i」という保存則に従うことが確認されました。また、l_p = -1 の場合には (l_s, l_i) = (0, -1) または (-1, 0) のみが観測され、l_p = +2 の場合には (1, 1) のみが観測されました。これらはいずれも保存則 l_p = l_s + l_i を満たしています。さらに、同じ装置で弱いコヒーレント光(古典的なレーザー光)を使った場合と比較しても、相関分布はほぼ完全に一致し(相関係数は99%以上)、単一光子とレーザー光の違いによる差は見られませんでした。
ただし、実験は非常に効率が低く、単一光子ポンプでの成功率は1時間あたりおよそ1回程度という「干し草の山から針を探す」ような難しさを伴いました。また、生成された光子ペアに量子もつれの兆候は見られましたが、統計的に有意な証明には至っていません。
本研究は、量子光学における「角運動量保存則」が1光子という最小単位でも確実に成り立つことを示した重要なステップであり、将来の高次元・多自由度エンタングルメント生成や量子通信・量子情報処理の基盤となる可能性を持っています。今後は変換効率の高い非線形プロセスや、より高性能な検出器、決定論的な単一光子源、効率的なOAMモード測定技術が組み合わされれば、さらに大きなOAM量子数や複雑な多光子エンタングルメントの検証が可能になるでしょう。




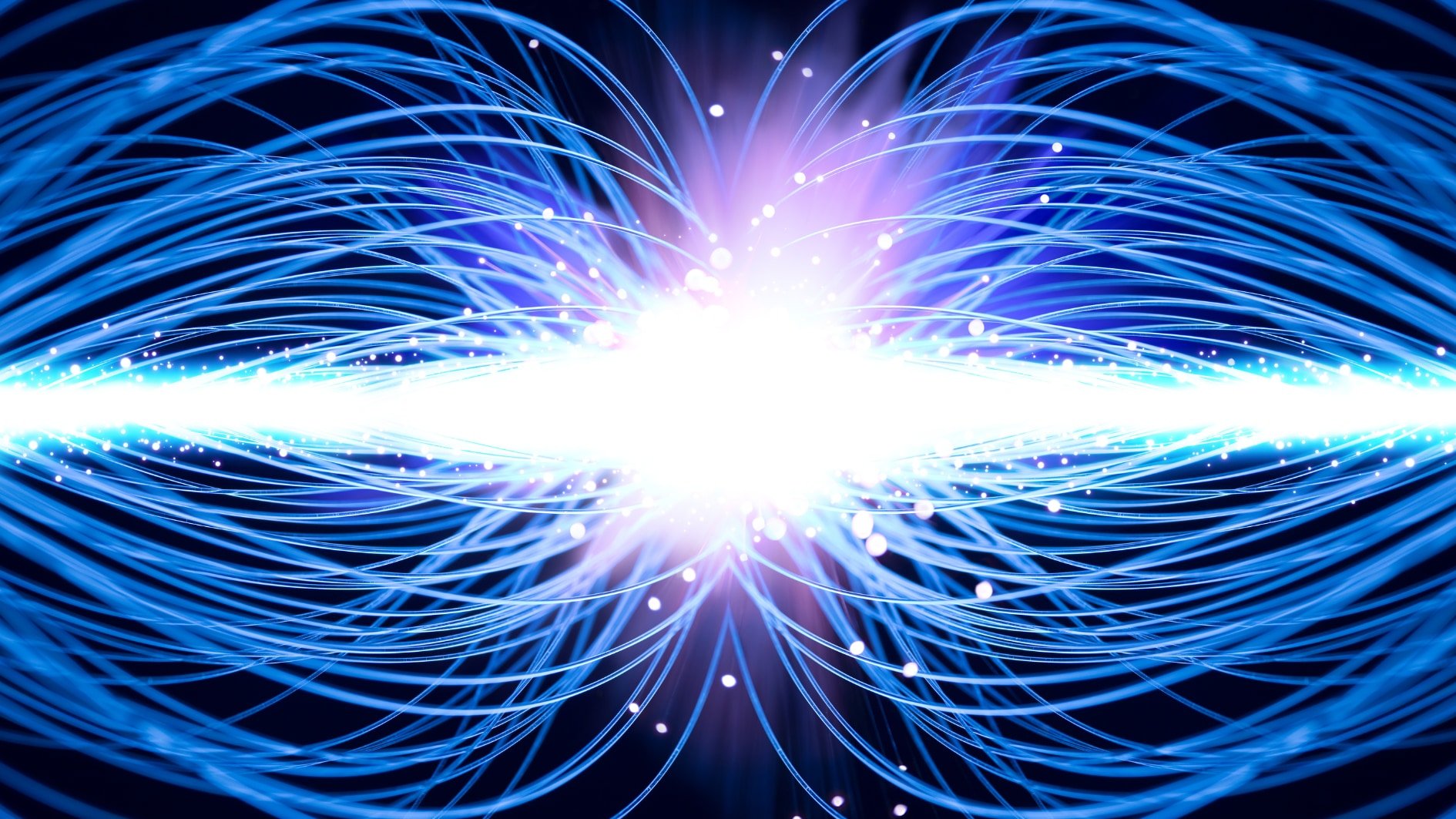























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
















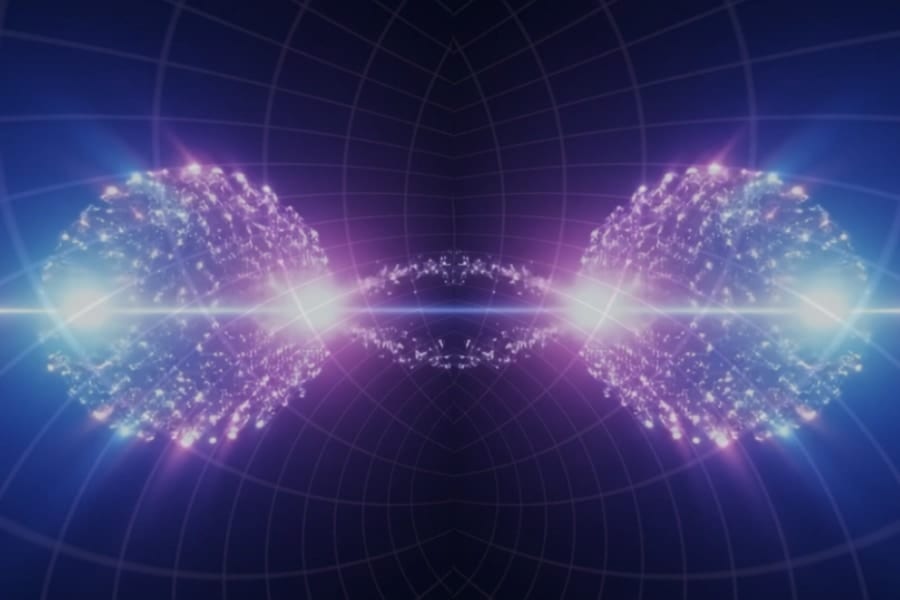

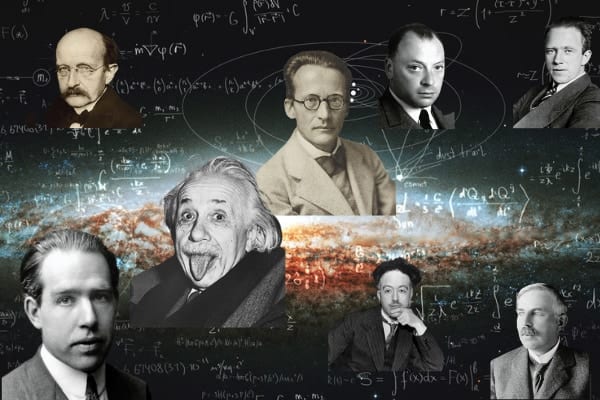









1個のねじれ0の光子が消えて、代わりに2個の光子が生まれた
その2個の光子の「ねじれ」でさえも+1と-1で0になるという辻褄が合う
この宇宙は、1つの粒の動き(今回は回転)ですら「整合性」を裏切らないよう設計されている
この動きは量子もつれを彷彿とさせる
従来は「多数光子で平均的に保存されてるよね〜」という確認止まり
今回は「単一光子レベルで、ガチで保存されてる」ことを確認
数式が「こうなるよ」と宣言し、
そして実験が「うん、実際にこうなった」って感じかな
何でもありな量子論さんにも破れないルールはあるわけですね。