AIの判定はどこまで信用できる?
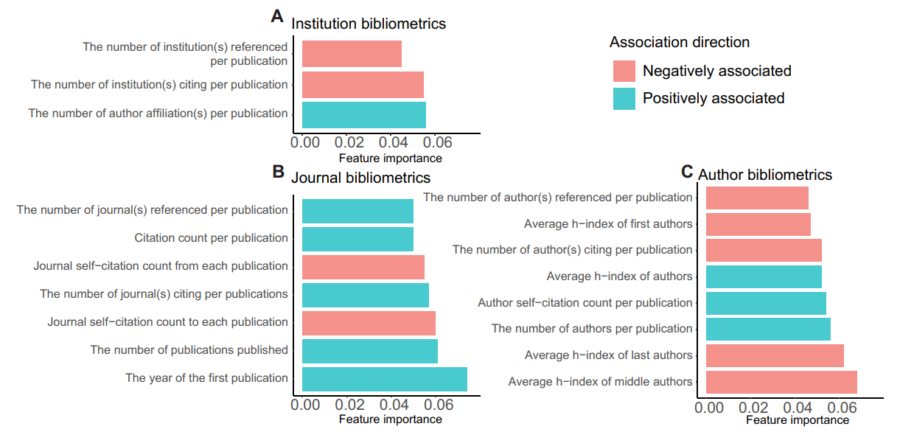
ここまで、AI(人工知能)を使って疑わしい学術雑誌を見つけ出す研究について説明してきましたが、「AIの判定は本当に信頼できるの?」という疑問が湧いてくるかもしれません。
実際にAIが「あやしい」と判定した雑誌を詳しく調べると、必ずしも悪意があるとは言えない雑誌も含まれていました。
例えば、ウェブサイトが一時的に停止したり、雑誌の発行が休止しているなど、単に運営上の問題で「あやしい」と判断されてしまった雑誌もあります。
また、本来は雑誌ではない書籍のシリーズや、学術会議の発表資料(会議録)などが誤って雑誌として扱われ、「怪しい雑誌」として判定されるケースもありました。
さらに、小さな学会が真面目に運営している雑誌でも、ウェブサイトが簡素だったり、あまり目立たないだけで、誤って疑われてしまった例もありました。
こうした状況を見ると、AIの判定結果をそのまま完全に信じることには問題があると言えます。
一方で、AIは「実際にあやしい雑誌」を見逃してしまうこともあります。
AIが正しく見抜ける割合は完全ではなく、実際に存在する怪しい雑誌のうち、6割近くを見逃していることが分かりました。
つまり、このAIは万能の道具ではなく、雑誌のチェックを始めるための最初の段階(一次ふるい)として考えるべきです。
研究チーム自身も、最終的に雑誌が本当に問題かどうかを判断するのは、人間の専門家(例えば雑誌の編集者や、研究費を出す機関など)の仕事だと強調しています。
実際に、このAIが「あやしい」と判断した雑誌を人間の専門家がランダムに取り出して確認してみたところ、AIが指摘した雑誌のうち約4分の1は問題がないと判明しました。
しかし、それ以外の約4分の3はやはり「あやしい雑誌」であることが分かり、AIの判定と人間の専門家の意見がほぼ一致したのです。
この結果は、AIが一定の精度で「あやしい雑誌」を見つける能力を持っていることを示していますが、同時に、AIの判定だけに頼るのではなく、専門家が必ず確認を行う必要があることも明らかにしています。
ここまで説明してきたように、このAIはまだ完璧ではありません。
しかし、人間がすべての雑誌を一つ一つ確認して「あやしいかどうか」を判断するのは、現実的に不可能です。
世界中には膨大な数の学術雑誌があり、それらを人の手だけでチェックするのは時間と労力がかかりすぎます。
そのため、AIを活用することで、多くの雑誌の中から「あやしいかもしれない雑誌」をある程度の正確さで素早く見つけ出し、その後に専門家がじっくりと検討すればよいのです。
AIが雑誌のチェック作業を最初に引き受けることで、限られた人間の専門家が本当に精査すべき重要な雑誌に力を注ぐことができるようになります。
今回の研究チームは、このAIを「科学の防火壁(ファイアウォール)」と表現しました。
防火壁とは、もともと建物で火災が広がるのを防ぐ壁のことで、コンピューターの世界では、外部からの危険な侵入を防ぐためのシステムのことを指します。
つまり、このAIは怪しい雑誌が科学界に入り込んで信頼性を壊してしまうのを防ぐ、最初の防御ラインとして機能するというわけです。
研究チームは、大学や出版社がこのAIを手軽に利用できるようにすることを検討しており、このシステムが普及すれば、怪しい雑誌による科学への被害を防ぐことが期待されます。
もちろん、それはあくまで専門家が最後のチェックを行うという前提のもとですが、AIを上手に使うことで、科学の信頼性を守る新しい仕組みが生まれることになるでしょう。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)















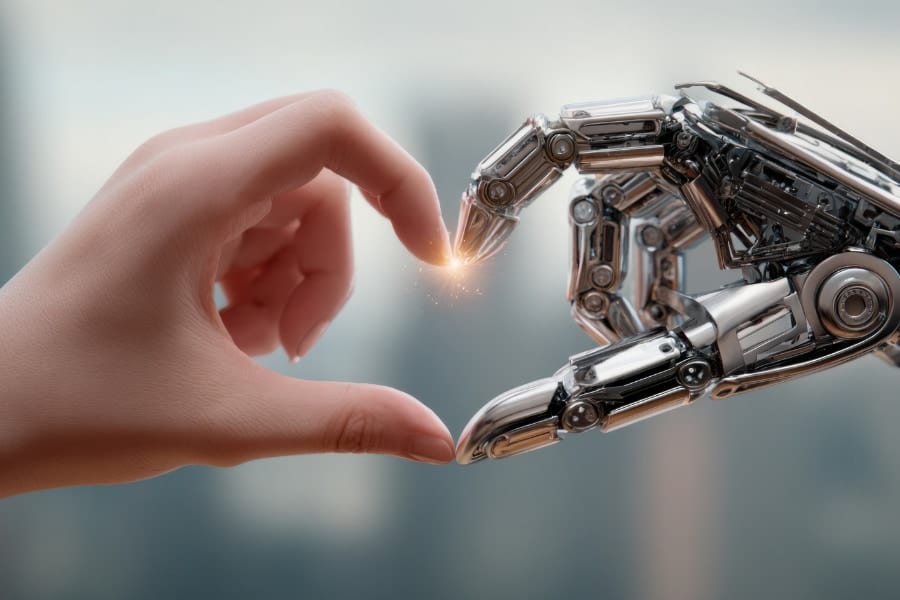


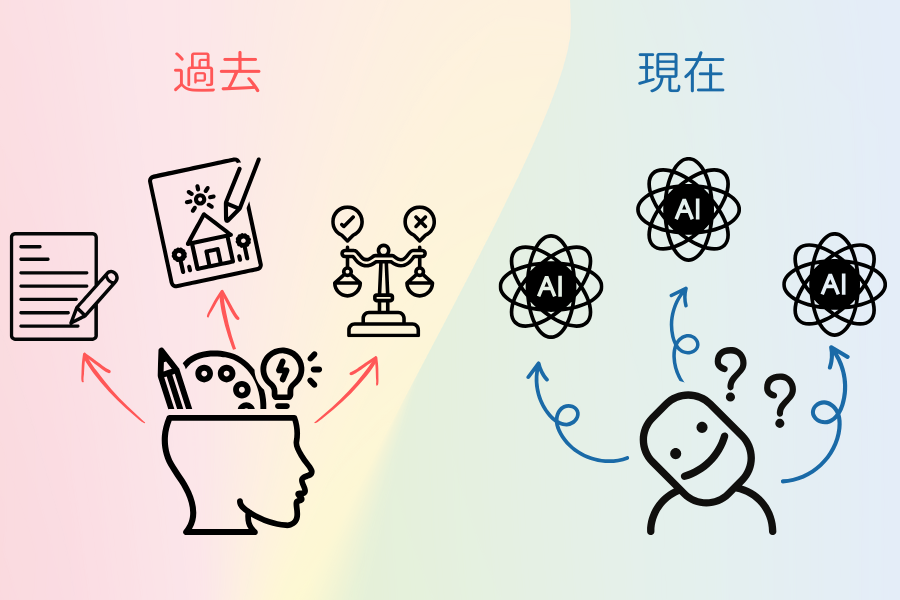









査読というより追試だけをひたすらやる機関が必要かもですね。
追試すればすぐにそれが真か偽かって分かりますからね。
本来論文というのはその追試をするための資料なわけでしょう?
大型加速器が必要な論文設備なしで追試しろといわれても難しいように、追試だけ実施というのも実現は難しいでしょうね。
追試をするにも金と時間と人手がかかるので、どんなに簡単な実験でもそうそうは簡単にできない。ましてや、自分の業績にならない追試を行う研究者・技術者のモチベーションを保つのは大変。
このサイトは大丈夫?
似非科学信じちゃう人は論文の妥当性なんか気にしないからね。水素水はマジでビビった。
百五十余年の歴史を誇るイギリスの総合科学雑誌「Nature」や同じく老舗のアメリカ科学振興協会誌「Science」、そしてライフサイエンス学術雑誌「Cell」などは科学者垂涎の憧れの科学雑誌だから、研究者なら誰もが論文掲載(プロジェクトの一員としての名前表示)を夢見るんだろうね。
こんな世界的権威のある学術雑誌がある一方で、お金(掲載料)を積めば論文もどきでも載せてくれる便利な(?)商売熱心な非科学的商業雑誌も結構たくさん在るんだねぇ。
個人の経済的・社会的利益と研究の公正さに対する社会的責任が衝突相反する企業資金や報酬を得た研究では、研究結果が資金提供者に有利となる可能性があるので、研究の利益相反(COI: Conflict of Interest)の開示義務が生じるけれど、掲載料のみで査読査定がおざなりの場合はどうなるんだろか。
AIは決して万能ではないが、少なくとも正当な科学論文掲載の手順を踏んでいないもの、また、金は稼ぐが世の中に何の貢献も果たさない似非科学雑誌を抽出・選別するのには有用有益みたいだ。
新型コロナウイルス騒動以降こういうの激増した。
特にワクチンや免疫関係。
もはや新興宗教だよ。