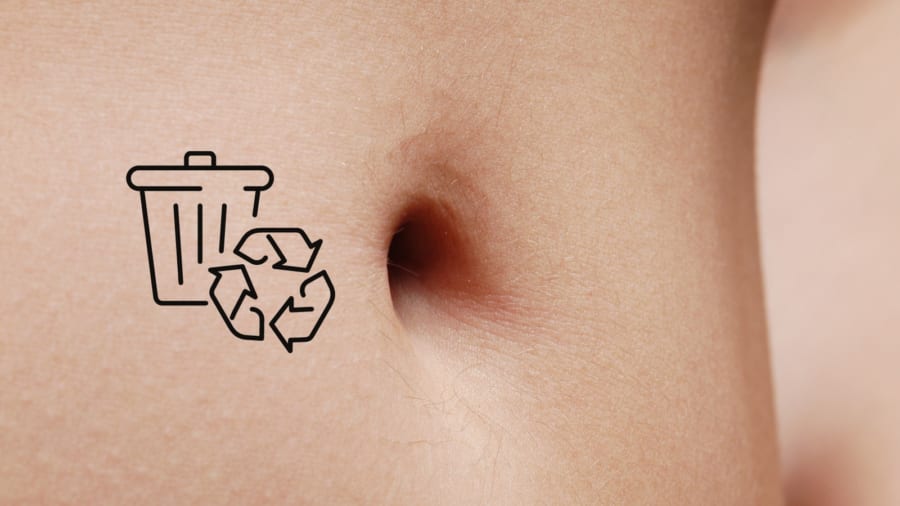8000年分の骨から探る「動物の大きさ」の変化
動物の体の大きさ(体サイズ)は、その動物がどんな環境で生きてきたのか、人間とどんな関わりを持ってきたのかを知るうえで、とても重要な手がかりです。
しかし、これまで「家畜」と「野生動物」の体サイズの変化を、同じ場所・同じ時間軸で同時に比較した研究はほとんどありませんでした。
今回の研究チームは、フランス南部の311か所の遺跡から見つかった22万5000点以上の骨や歯を集めました。
ウシやブタ、ヒツジ、ヤギ、ニワトリといった家畜はもちろん、シカやキツネ、ノウサギなどの野生動物も含め、骨や歯の長さや太さを測って体の大きさを推定しています。
さらに、当時の気候や植物、人口、土地の使われ方といった「環境の変化」もあわせて調べ、「何が動物の体の大きさを変えてきたのか?」を探りました。
その結果、8000年前の新石器時代から約1000年前の中世まで、野生動物も家畜も「体の大きさがほぼ同じパターンで変わってきた」ことが分かりました。
寒さや乾燥といった「環境の変化」によって、動物全体が同じように影響を受けていたのです。
この時期、人間はすでに家畜を育てていましたが、まだ「自然の環境」の力のほうが強く、家畜も野生動物も同じような変化をたどっていました。
しかし、8000年間のうち、最後の1000年間で状況は大きく変化しました。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)