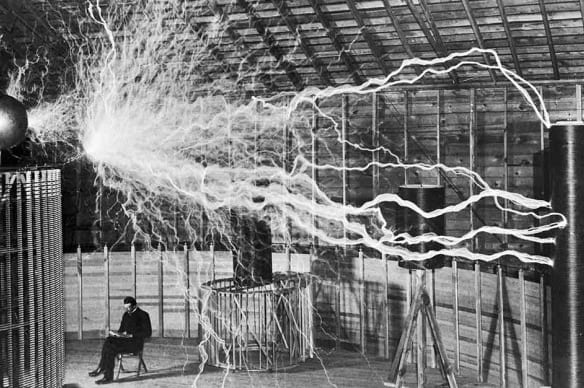与えすぎのサイン①:「不満や憤り」
まず理解すべきは、「与えすぎ(overgiving)」とは単に親切にすることではなく、「相手のために自分を犠牲にし続ける行動」 を意味するという点です。
たとえば、相手のために自分の時間や体力をたくさん使ったり、気持ちの面でも相手を思いやり続けたり、何度も許したりチャンスを与えたりします。
そうしたことが重なると、自分が疲れきってしまうのです。
この「与えすぎ」のサインの1つが、関係における「不満や憤り」です。
たとえば、「休日のたびに自分の希望を抑えて相手に合わせたり、相手が落ち込んでいるときには何時間も慰め続けるのに、自分が弱ったときにはほとんど気にかけてもらえない」と感じるでしょうか。
そんな経験が続くと、「私ばかり頑張っている」という感情が募り、やがて愛情が苦い思いに変わってしまいます。
この現象は、研究でも裏付けられています。
2014年に795組の既婚カップルを対象に行われたブリガムヤング大学(BYU)の研究では、配偶者の努力をどう認識しているかが、夫婦の満足度や離婚リスクに直結することが示されました。
努力が双方に感じられないと、不満が積み重なり関係は揺らぎやすくなるのです。
さらに2022年の西南大学(Southwest University)実験研究では、72人の参加者が「冷水に手を入れる課題」に挑戦し、恋人のためであれば友人のためよりも長く痛みに耐えることが確認されました。
これは「愛する人のためなら犠牲を厭わない」という人間の特性を示しています。
だからこそ、犠牲が一方的な状況も生じやすく、これが続くことで心理的な負担が膨らみやすいことも示唆しています。
つまり、愛情に基づく犠牲は自然な行動ですが、見返りがまったくない状態で続けば、不公平感が強まり、関係そのものを不安定にしてしまうのです。
では、自分の「与え方」を見直すためには、どうすれば良いでしょうか。
たとえば、「私は本当に心から与えたいから行動しているのか、それとも相手にもっと好きになってほしいからやっているのか?」 「この行動自体で自分が満たされるのか、それとも何かお返しを期待しているのか?」 と、立ち止まって自分に問いかけてみましょう。
もし「愛されたいから頑張ってしまう」という気持ちが強い場合は、いったん立ち止まることも大切です。
自分が本当に望む与え方や、無理のない範囲を見つめ直すことで、より健康的な関係に近づくことができます。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)