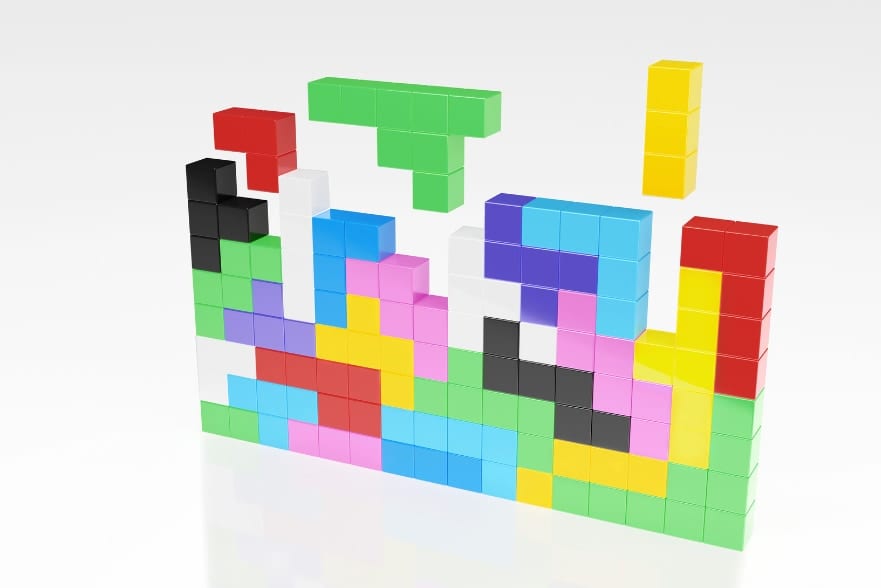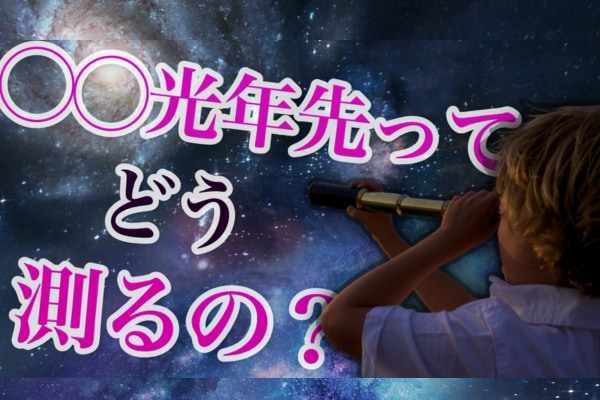ハーブの味で分かる「舌を使ったインフルエンザ検査」
毎年のように流行するインフルエンザ。
PCR検査は高精度ですが、専門機器や人員が必要で結果にも時間や費用がかかります。
一方、薬局で手に入る迅速検査(ラテラルフロー式)は手軽な反面、症状が出る前の段階では見逃しが起きやすいという弱点があります。
つまり従来の方法では、「まだ元気に動ける人が、実は感染しているかもしれない」状況を拾い上げるのが難しかったのです。
こうした中で生まれた研究チームの発想はとてもシンプルなものでした。
「複雑な測定装置の代わりに、人間の舌を使おう」というものです。
具体的には、インフルエンザウイルスが持つノイラミニダーゼという酵素に注目しました(インフルエンザウイルス「H1N1」の“N”)。
この酵素は、ウイルスが人の細胞から離れて広がるときに働き、感染者の唾液中にも存在します。
そしてウイルスはノイラミニダーゼを用いて、攻撃対象の細胞の特定の結合を切断し、感染します。
研究チームはこのメカニズムを応用しました。
開発されたセンサーは、ノイラミニダーゼが切ると“味”が出る分子として設計されています。
味の正体はチモールという成分で、ハーブのタイムに含まれる香味分子です。
チモールは普段はセンサー分子に結合されたままで味がしません。
ところが、口の中にウイルスのノイラミニダーゼがあると、これがセンサー分子の結合を切断。チモールが放出され、舌が「タイムのような味」を感じるのです。
この仕掛けで、味が出た=感染の可能性に気づけます。
さらに重要なのは選択性です。
研究チームは、センサーの糖部分(N-アセチルノイラミン酸)を化学的に工夫し、細菌由来のノイラミニダーゼでは切れにくく、インフルエンザ由来のノイラミニダーゼで切れやすいように設計しました。
つまり、「ウイルスの酵素が働いたときだけ味が生まれる」ように調整されているのです。
そしてこの効果は実験でも確かめられました。































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)