赤ちゃんの脳は世界を「4Hzのスローモーション」で見ていた

赤ちゃんの脳の情報処理は速いのでしょうか、それとも遅いのでしょうか。
このシンプルな疑問に答えるため、研究チームは「見るだけで脳のテンポを測る」特別な方法を考案しました。
実験では、生後8か月前後の赤ちゃんが保護者の膝に座り、画面に現れるカラフルなキャラクターを眺めました。
映像は時には規則正しく(2〜30Hz)点滅し、時にはリズムのない「ブロードバンド刺激」と呼ばれる、決まった周期がない光の変化も混ぜられました。
頭には小さなセンサーをつけ、64チャンネルの脳波計(EEG)で脳のリズムを記録しました。
赤ちゃんはただ画面を見るだけでよく、負担は最小限でした。
すると、驚くべきパターンが現れました。
どの点滅条件でも、赤ちゃんの脳波には約4Hz(1秒に4回の波、いわゆるシータ波帯)のリズムが安定して現れたのです。
この4Hzの成分は、画面に静止画像を見せた場合にも確認されましたが、刺激を完全に省いたときには有意な増加は見られませんでした。
一方で、大人に多い8〜14Hz(アルファ波帯)の独立した応答は見られず、乳児の脳では4Hzこそが特別な拍であることが浮かび上がりました。
言い換えれば、赤ちゃんの脳は自分の4Hzリズムを保ちながら外界の刺激に同調していると考えられます。
さらに、ランダムな点滅(ブロードバンド刺激)のときにも面白い現象が起こりました。
赤ちゃんの脳は入力信号に対して約4Hzの「やまびこ(エコー)」のような反応を返していたのです。
このエコーは刺激提示後およそ1秒間、4Hzで約4サイクル分続き、映像のリズムが脳内で反響しているかのようでした。
そして入力信号から4Hz成分だけを取り除くと、そのエコー反応も消え、4Hzだけが特別に共鳴していたことが確かめられました。
これは、赤ちゃんの脳が4Hzの情報を何度も「響かせて」処理していることを示しています。
比較のために健常な成人7名でも同じ実験を行いましたが、結果は大きく異なりました。
成人の脳波では有意な4Hzのエコーは見られず、その代わりに約10Hz(アルファ波帯)の共鳴応答が確認されました。
つまり、乳児期の脳がシータ波(4Hz)で「刻む」のに対し、成人の脳はアルファ波(約10Hz)で「刻んで」いるのです。
この違いは脳内ネットワークの発達を反映しており、乳児の脳内リズムが成長にともなってシータ帯からアルファ帯へ移行していく過程を示唆しています。














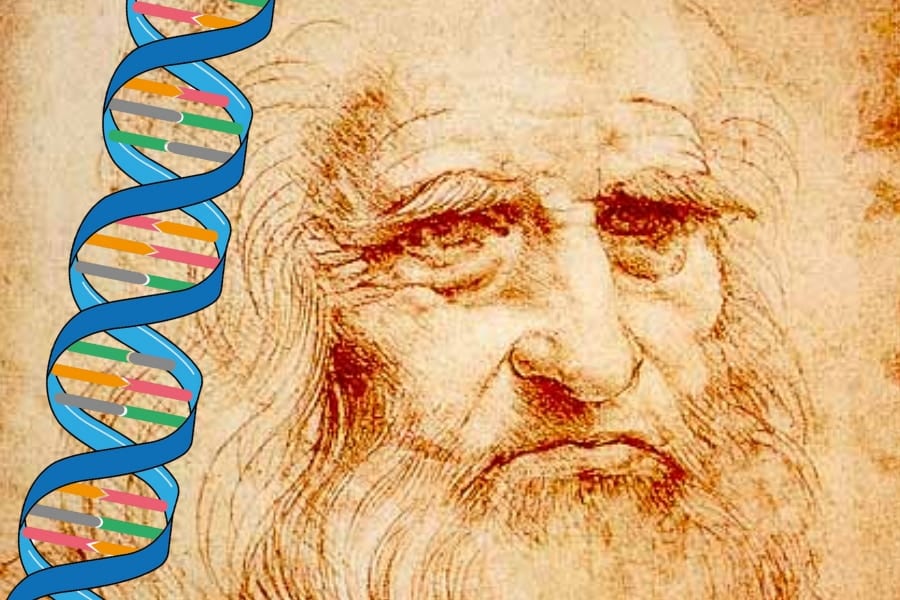














![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)



























