7歳を境に“知りたくない”が生まれる? 子どもの中に芽生える「見ない選択」
3つの実験の結果、7歳前後になると人は「知る勇気」よりも「知らない安心」を選ぶ場面が増えることがわかりました。
最初の実験では子どもたちに、身近で起こりそうなシナリオを示し、それに対しての情報が欲しいかどうかを訪ねました。
これは例えば「好きなキャンディが体に悪いかもしれない」「友だちが自分をどう思っているか」といった情報です。
その結果、7歳頃を境に子どもたちは“知らないまま”を選ぶ割合が高くなったのです。
また別の実験では、子どもたちの前にはステッカーの入った2つの箱が置き、どちらか1つを自分がもらい、もう片方はペアの友だちに渡されるというゲームを行いました。
ただし、この実験では友だちに渡された箱に何枚のステッカーが入っているかは見えません。
ここで子どもに「友だちの箱を開けて中身を見る」か「見ないか」を選んでもらいました。
この実験でも、年長の子どもほど「見ない」ことを選ぶ傾向がありました。
研究者は、この行動を「道徳的な逃げ道(moral wiggle room)」と呼ばれる心理に似ていると説明しています。
これは、知ってしまうと罪悪感を覚える可能性があるとき、あえて“知らないまま”でいることで心の平穏を保とうとする反応です。
例えばこの実験の場合、もし相手の方が多くステッカーをもらっていたら嫌な気持ちになるし、自分の方が多かったら後ろめたい気持ちになるかもしれません。
見ないことで、そんな気まずさを感じずに済むのです。
最後に、研究者は「幼い子どもでも情報回避を選ぶようになる状況は作れるか」を確かめるために、次のような実験を行いました。
子どもたちに「もしその箱の中身を見ると悲しい気持ちになるかもしれないから、見るかどうかを選ぶときは気をつけてね」というような警告をあらかじめ与えます。
その上で、子どもの前に示した箱の中身を「見るか・見ないか」、その選択を調査したのです。
その結果、幼い子どもでも「見ない」選択をする割合が通常よりも高くなりました。
この実験は、自分に不利な情報を避けたいという気持ちは、成長とともに自然に強くなるが、“知らないことで安心”を得るという行動は、年齢に関係なく感情を守る自然な反応として現れることを示しています。
一方で、子どもたちはすべての情報を避けているわけではありません。
「上手くできたか」「どうすればうまくなるか」といった、自分の努力や成長に関する情報については、年齢に関係なく多くの子どもが知りたがりました。
しかし、他人との比較や不公平を意識させる情報は避けられやすく、「知ると気分が悪くなりそう」と予想できるものほど、回避の傾向が強くなっていました。
この結果から、研究チームは、情報回避は単なる“現実逃避”ではなく、感情を守りながら学ぶための心の工夫だと説明しています。
7歳前後というのは、他人の視点を理解し、自分がどう見られるかを意識し始める時期です。
その発達が進むことで、子どもは「知るとつらい現実」から身を守る一方で、「知ることで前に進める情報」には向き合うという、心のバランス感覚を身につけていくのです。
嫌な現実から目をそらすのは、単なる弱さではなく、自分の心を守るための最初の知恵なのかもしれません。
















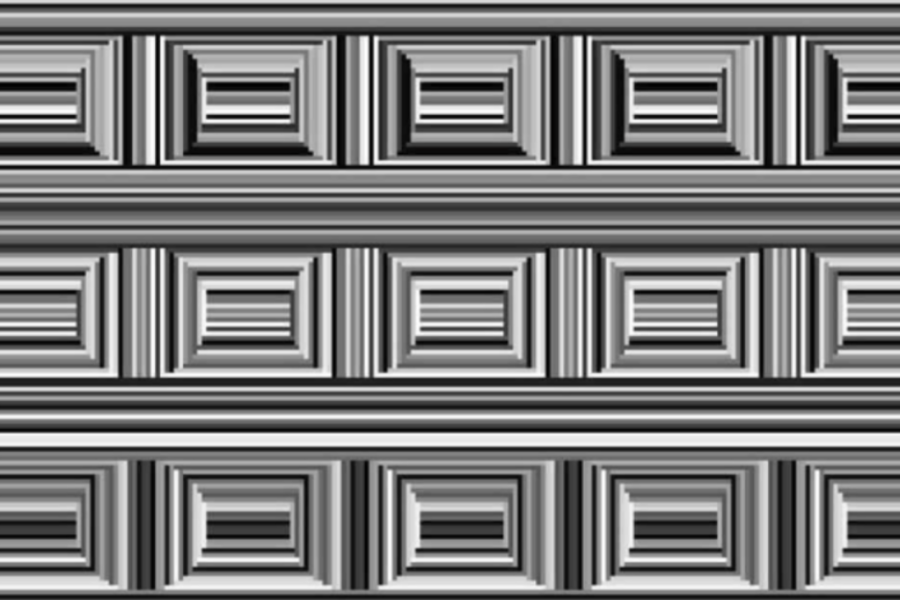










![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)



















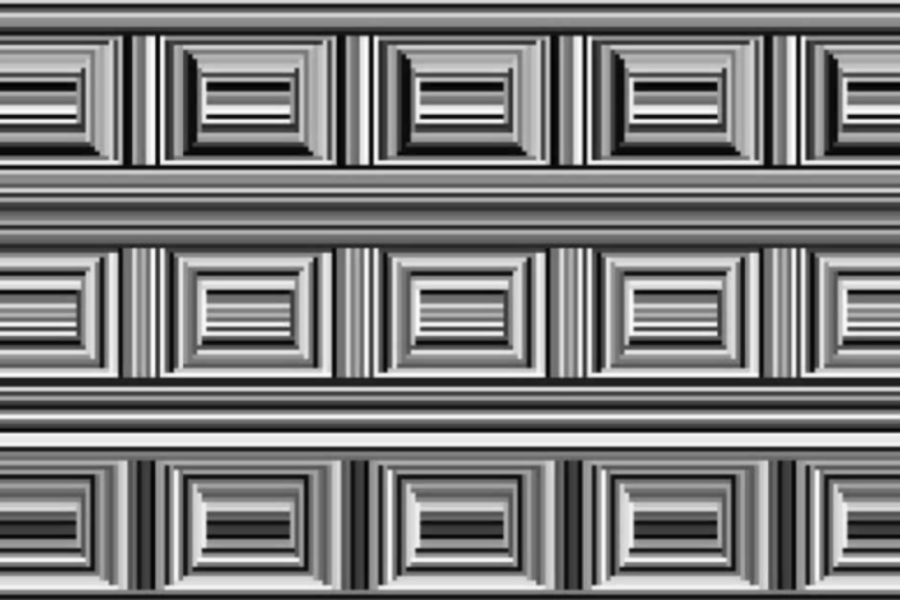








1番ダサいのはそれを共通認識とするとこなんだわ
ダサいはダサい