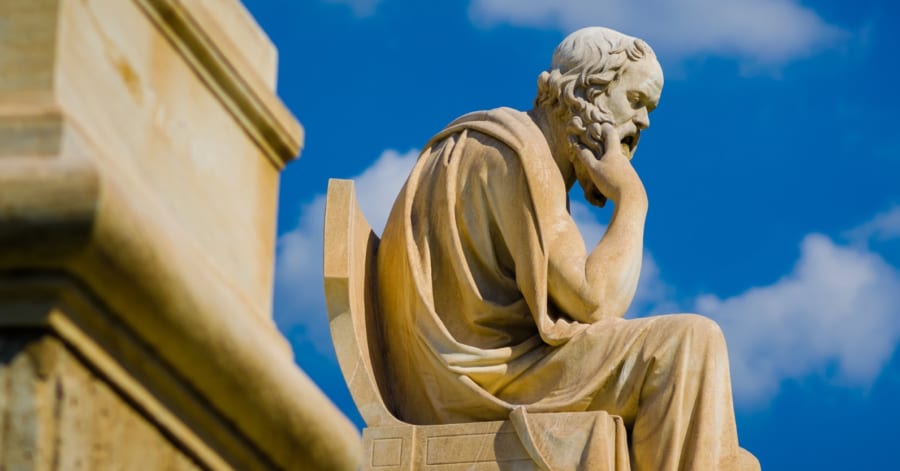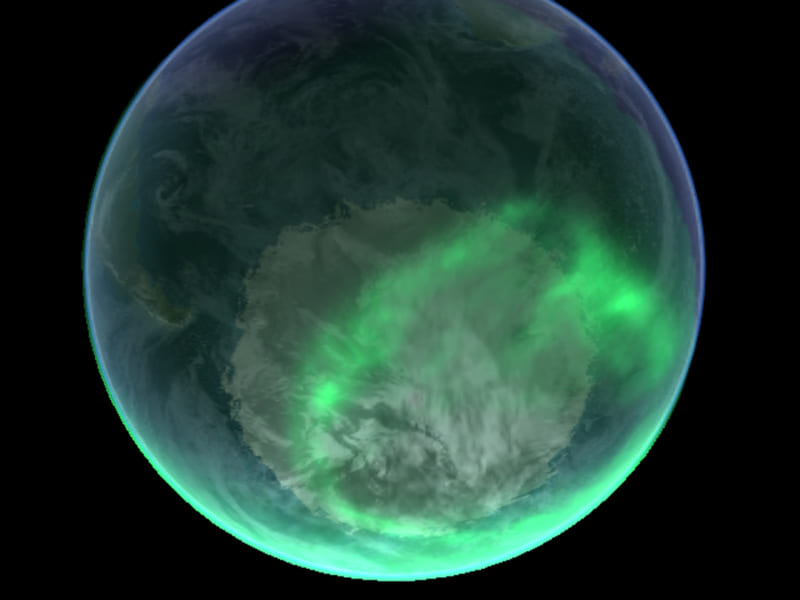集中できない特性が創造性につながる
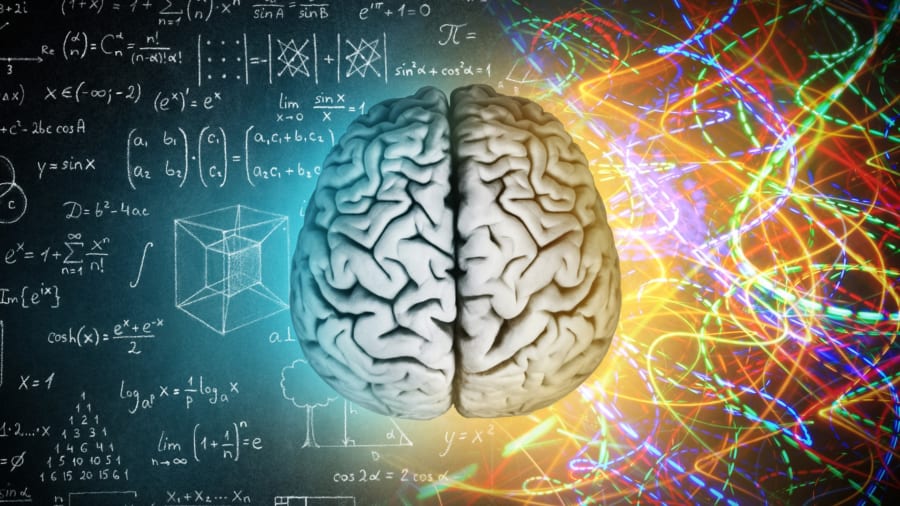
「また別のことを考えてる!ちゃんと集中しなきゃ……」――大事な場面でつい頭の中が脱線してしまい、自己嫌悪に陥る。
そんな経験は、誰でも一度くらいはあると思います。
人間の脳というのは実はそれほど集中力が続くようにはできておらず、時折、目の前のことと無関係なことを考え始めてしまうものです。
こうした現象は専門的に「マインドワンダリング」と呼ばれます。
直訳すれば「心の散歩」、つまり、心が自由にあちこちさまよってしまう状態のことです。
例えば授業や会議中に、気がついたら次の休日のことを考えてしまったり、夕飯のメニューを考え始めていたりするアレですね。
実は、この「マインドワンダリング」という状態は誰にでも起こることですが、ADHD(注意欠如・多動症)の人では、特に頻繁に起きやすい傾向があります。
ADHDというのは脳の特性の一つで、注意力を持続させることが難しかったり、衝動的に行動してしまったりする傾向が強い人のことを指します。
こう聞くと、どうしてもADHDの特性は「問題があるもの」「なんとか直さなければ」といったネガティブなイメージで語られることが多いですよね。
勉強や仕事をする上でも、どうしても集中力が続かず、つい他ごとを考えてしまい、効率が下がってしまう。
こうした理由からADHDはしばしば「厄介者」扱いされ、本人自身も苦しんでしまうケースが少なくないのです。
しかし最近では、ADHDの人の脳が持つ「注意があちこち飛びやすい」という性質を、必ずしも「悪いこと」だと捉えない見方も増えています。
実際、「マインドワンダリング」には、思いがけないアイデアや新しい発想を生み出す可能性がある、ということが、様々な研究で指摘されてきているのです。
例えば、多くの作家やアーティスト、起業家のインタビューなどを読んでいると、「ぼんやりする時間が大事だ」「むしろ集中しすぎると良いアイデアが出ない」といった発言をよく目にします。
授業中や仕事中にふと別のことを考えていたら、突然良いアイデアが浮かんだという経験を持つクリエイターも意外に多いのです。
人によってはお風呂に入っていたり、散歩中だったり、トイレの中だったりもします。
このように、「ボーッとすること」「気が散ること」が創造性を刺激するかもしれないという考え方は、最近特に注目されるようになってきました。
逆に何かに一心不乱に集中して打ち込んでいる状況と、全てをひっくり返すような新しいアイデアが脳裏に浮かぶ状況は、ある意味で両立し難いものと言えるでしょう。
少し言葉遊びのような言い方をすれば「集中しているときに集中しているもの以外が脳裏によぎることがあるなら、それはもはや一心不乱型の集中とは言えない」からです。
とはいえ、これまでの研究はまだ断片的で、「ADHDの人の脳は創造性が高い傾向があるらしい」ということは分かっても、その詳しい仕組みや理由までは明らかではありませんでした。
そこで今回、オランダ・ラドバウト大学医学部のハン・ファン氏(Han Fang)らの国際研究チームが、真正面からこのテーマに挑みました。
研究チームが問いかけたのは、「ADHDの人が持つ『寄り道思考』の傾向は、本当に創造性と関係しているのだろうか?」というシンプルかつ重要な問いだったのです。




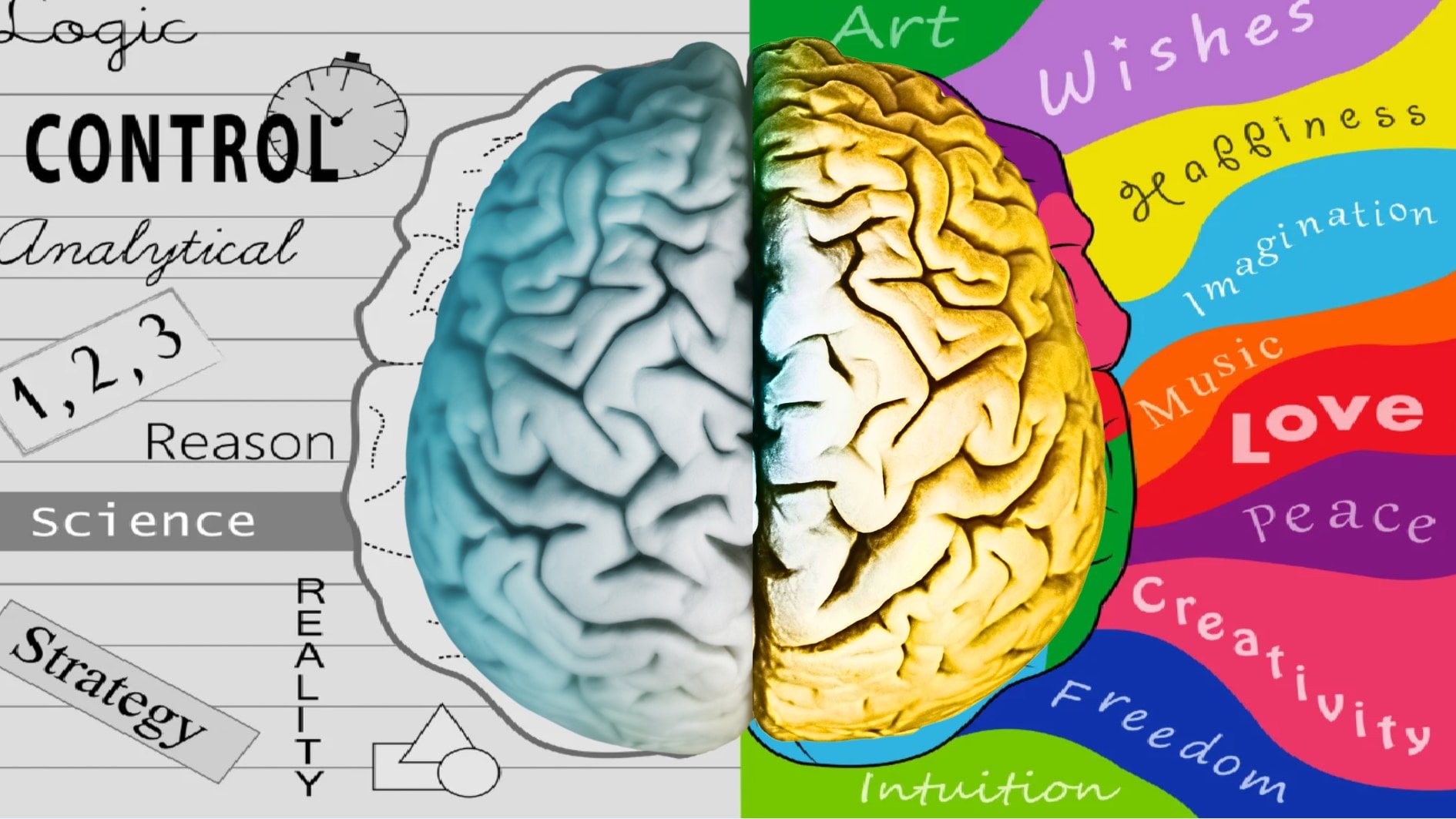





















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)