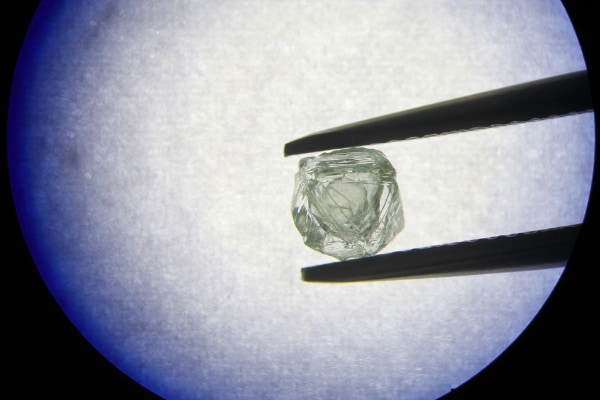創造性が高いADHDの人は、さまよう注意の中から「ひらめき」をみつける

研究チームが注目したのは「マインドワンダリング」と呼ばれる、心が目の前の課題から離れてあちこちさまよう現象でした。
たとえば授業中に先生の声が聞こえているのに、頭の中では晩ご飯のメニューを考えている――そんな状態です。
つまり、心が「いま、ここ」から抜け出して、自由に旅をしているようなものなのです。
このマインドワンダリングには、実は2つのタイプがあります。
ひとつは「自発的タイプ」。これは気づかないうちに勝手に考えが飛んでいく状態で、たとえば退屈な会議中に無意識で別のことを考えてしまうときなどがそうです。
もうひとつは「意図的タイプ」。こちらはあえて別のことを考えるタイプで、言ってみれば“考える脱線”を自分の意志でコントロールしている状態です。
研究チームはこの2つの違いに注目しました。
ADHDの人は、こうしたマインドワンダリングが人より多い傾向があります。
先にも触れたように、ADHDは注意を長く保つのが難しく、つい気がそれてしまう脳の特性をもっています。
そのため、マインドワンダリングを“悪いクセ”として否定的に見る人も少なくありません。
しかしチームの仮説は逆でした。
「もしかしたら、この“寄り道の多さ”こそが創造性の高さと関係しているのではないか?」というのです。
この問いを確かめるために、研究チームはヨーロッパとイギリスの二つのグループ、合わせて725人(プレスリリースでは約750人とされています)の成人を対象に調査を行いました。
参加者にはまず、ADHD特性の強さを測る質問票を実施しました。
そして、創造性を評価するために「創造的達成」や「発散的思考」を測る課題を行ってもらいました。
発散的思考とは、たとえば「ペーパークリップの使い道をできるだけ多く挙げてください」といった発想課題のことです。
さらに参加者には「どれくらい心がさまよいやすいか」を尋ねるマインドワンダリング尺度も答えてもらいました。
その結果、ADHDの特性が強い人ほどマインドワンダリングが多いという、予想どおりの関係が見られました。
これは「ADHDの人は気が散りやすい」という日常の実感を科学的に裏づける結果です。
ところがここからが面白いところです。
マインドワンダリングが多い人ほど、創造性のテストでも高得点を示しました。
つまり、注意が逸れやすいという弱点が、ひらめきを生む“土壌”にもなっていたわけです。
さらに分析を進めると、創造性が高い人ほど、マインドワンダリングの中でも「意図的タイプ」が多い傾向があることが示唆されました。
言い換えれば彼らは「コントロールされた意図的な注意散漫」を利用して、新しい発想を探していたのです。
重要なのは、“勝手にボーッとする”ことではなく、“意識してボーッとする”こと。
この微妙な違いが、ADHDの創造性を生み出す鍵なのかもしれません。
実際、一部の研究ではADHDの本質はあらゆるものへの高度な集中と解釈する場合もあります。
小コラム:言い方が違うだけで本質は同じ?
「あらゆるものへ高度に集中することで、ひらめきに繋がる」というのと「コントロールされた意図的な注意散漫で、ひらめきに達する」というのは言い方が違うだけで中身が同じようにも思えます。
同様に「コントロールされていない注意散漫では創造性につながらない」と「あらゆるものに集中し過ぎて逆に何も思いつかない」という2つの解釈も本質は似ている可能性もあります。
そう考えると、ADHDが持つ「さまよう思考」を自分の武器にするか、人生の足を引っ張る重りになるかは、ほんの僅かな使いようの違いにあるのかもしれません。
今回の研究は、ADHDと創造性をつなぐメカニズムを初めて直接検討した初期の報告の一つとされています。
ADHDの特性を「問題」ではなく「戦略」として捉え直す――そんな視点の転換をもたらす重要な一歩だったのです。




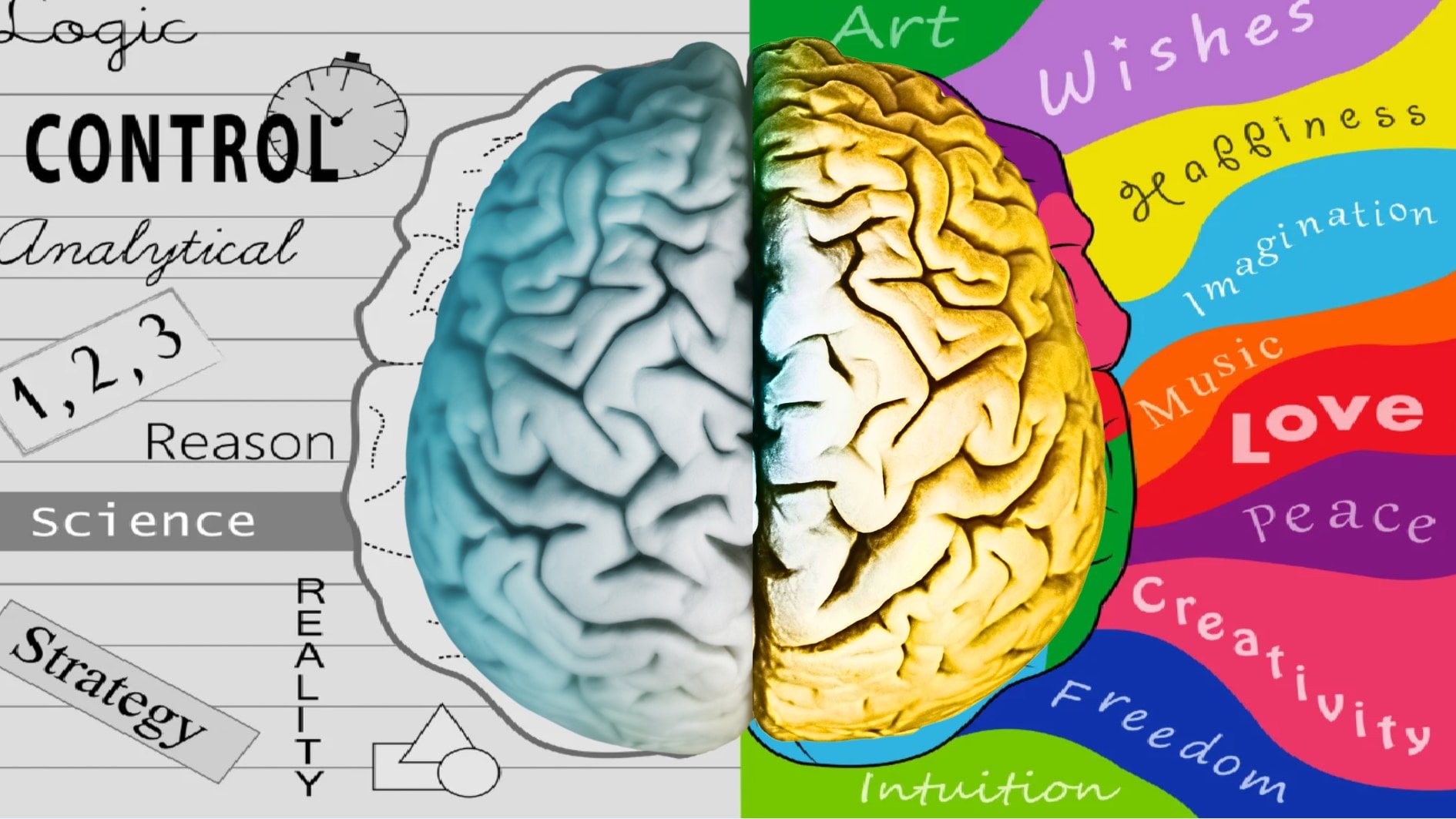





















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)