創造性にとって「集中が良く散漫が悪い」とは限らない

今回の研究は、「ADHDの人はクリエイティブである」という漠然としたイメージを、科学的に一歩前進させました。
つまり、ADHDの脳がなぜ創造的な傾向を持つのか、その秘密の一端が「意図的な寄り道思考」という心の使い方にある可能性を示したのです。
これは、言い換えれば「集中できないことは必ずしも弱点ではない」という、私たちの常識をひっくり返すような発見とも言えます。
この知見は、教育や支援の現場にも新しい視点をもたらすかもしれません。
今までの教育では、授業に集中できない生徒に「もっと集中しなさい」と叱ることが普通でしたが、この研究はむしろ逆の方向を提案しています。
「注意がそれやすい特性」を無理に矯正するのではなく、それを活かして新しいアイデアや創造的な発想につなげる方法を模索する方が、ずっと有効ではないかというのです。
実際に研究者らは、心理教育プログラムなどを通じて、ADHDの人が持つ多様な発想を伸ばす方法を提案しています。
これはADHDの人が持つ発想力を否定せず、むしろ積極的に引き出してあげようという取り組みです。
また、治療や心理支援の分野でも、今までのように「注意散漫を抑え込む」訓練ばかりでなく、「意識して思考を切り替える」トレーニングが有効かもしれないという新しい考え方が生まれつつあります。
ただし、ここで勘違いしてはいけないのは、「じゃあADHDはそのままで良いんだ!」と簡単に結論づけることです。
研究チームも念を押していますが、ADHDの特性が生活のさまざまな場面で困難を引き起こすことは変わりません。
例えば、注意が頻繁に逸れることで仕事や人間関係に支障が出たり、勉強が思うように進まないという現実的な問題が残っているのです。
あくまでも、「意図的に寄り道ができるような、適切な訓練や環境が整えば」という条件つきの話だと理解することが重要です。
また、この研究はあくまで観察研究(実験をせず、調査や観察によって関係性を調べる手法)であるため、まだ明らかになっていないこともたくさんあります。
特に、なぜマインドワンダリングが創造力を引き出すのか、脳内のどのような仕組みでそうなっているのかという詳しいメカニズムについては、今後の研究課題です。
それでも、この研究には非常に大きな意味があります。
これまでADHDは多くの場面で「注意力が欠けている」「集中力に問題がある」といったマイナスな視点で捉えられてきました。
しかし、今回の知見は「注意散漫である」という特性を「創造力を引き出す新しい戦略」として捉え直す可能性を提示しています。
これは「神経多様性(neurodiversity)」という考え方にも一致しています。
神経多様性とは、人間の脳には様々な特性があり、それらを「欠陥」ではなく「個性」として尊重しようという新しい考え方です。
集中力が弱いとされるADHD脳も、この視点で見れば「常識にとらわれないユニークなアイデアの工場」とさえ表現できるかもしれません。
実際、専門家の中には、ADHDの人が持つ柔軟な発想力は社会にとって貴重な資源になり得ると評価する声もあります。
言ってみれば、ADHDの脳は「整理整頓が苦手なぶん、誰も思いつかない発想を生み出せる可能性」を秘めているということです――もちろん、適切な支援や環境が整えばという前提つきで。
今回の研究が私たちに投げかけているのは、「『集中』が絶対に良いことで、『散漫』が絶対に悪いこと」という常識そのものに対する問い直しなのです。




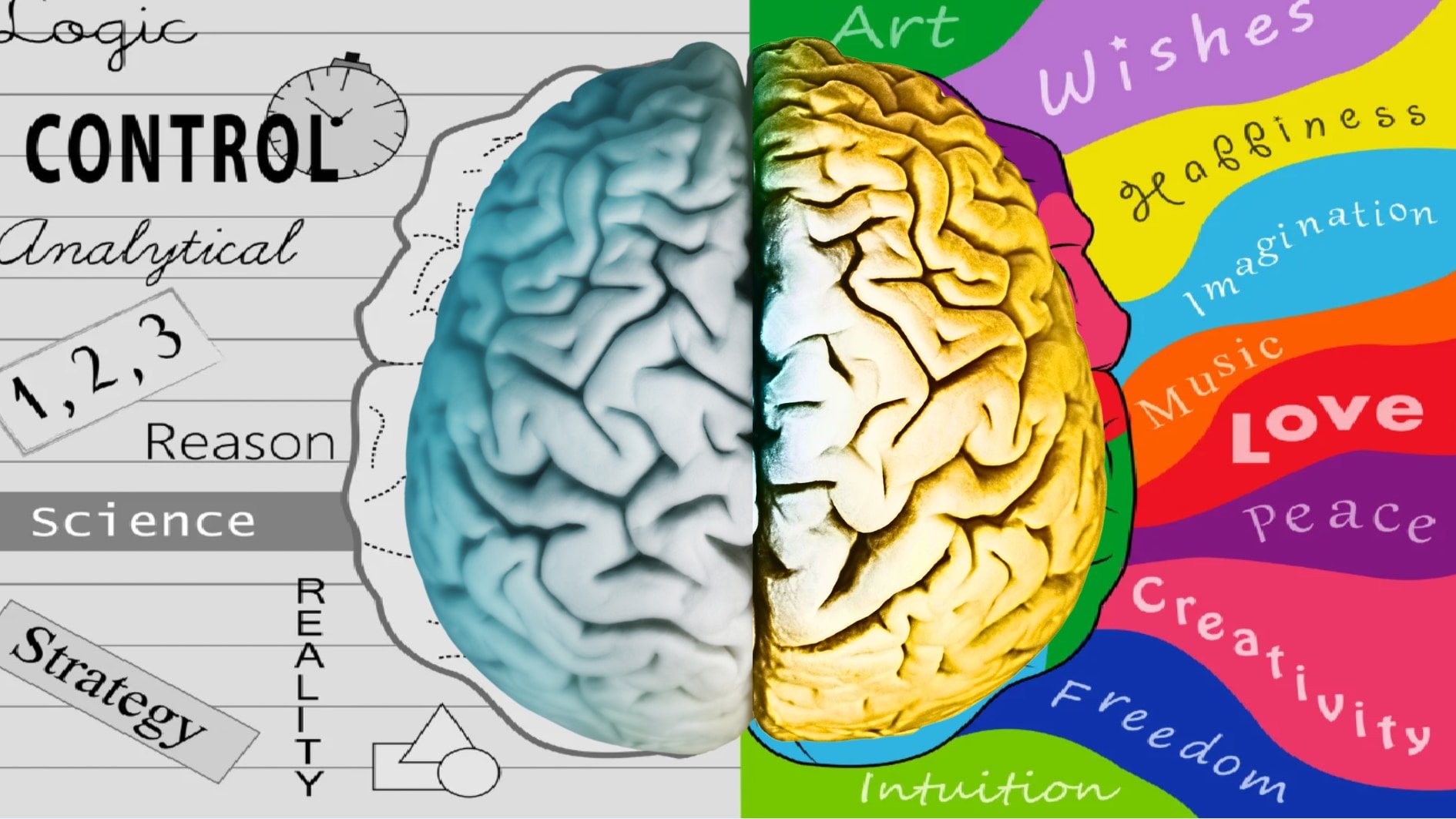





















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)




























でも創作者がADHDだらけかというと…そんなことはないっていう現実が待っているという。
向いているからと言ってその分野の頂点になれるほど世の中甘くないですからね。
向いてても才能がなければ話にならないわけでして。
それはそう
仕事にするなら人とのやりとり必須だからね
遅刻や約束破りをすると信用をなくす
信用なくすとお金に関わらせてもらえなくなる
宣伝や販売を誰も手伝ってくれなくなったら商売にならない
ADHDが有利であればこの世はすでにADHDで支配されてるはず。
ADHD傾向は多少誰しも存在するものである、むしろADHDは狩猟採集社会では役にたっていたかもしれない話もある。
ただし確実に言えるとしたら、現代社会のシステムはADHD傾向が極端に強い人にとってはミスマッチとなっているということではなかろうか(ミスマッチ仮説はASDにも似たようなことがいえるが
自分を客観視。それと抽象的で実態のない主体から求められてる優先順位をつけられること。
これが備わるなり育てば、組織の中や仕事も上手くいく可能性高まる。
だが、これらのことが大抵、できない。
できない原因や、苦手になるためのバックボーンが特性的にあるのか?結びついてるんだろうか?それとも、単なるその人の性能なりその人の中の優先順位の問題なのか?