魚類の進化と生態に新しい光
ウナギの仲間が陸上で獲物を捕る。
これは、実は魚類全体を見渡しても非常に珍しい行動です。
これまで陸上でも餌が捕れる魚は、トビハゼやイールキャット、リードフィッシュなどごくわずかしか知られていませんでした。
特にウナギのような細長い体型の魚で、この行動が実験的に確認されたのは世界で初めてです。
なぜウナギは陸上狩りを身につけたのでしょうか?
本来、ウナギは下流のほうに多く生息していますが、エサが乏しい上流にも進出します。
こうした多様な環境で生き抜くには、柔軟な摂餌戦略が不可欠です。
ウナギは水中だけでなく、陸にいる甲虫やトカゲなども獲物にすることで、生息域を広げることができたと考えられます。
この能力は、ウナギが大きな河川から小さな渓流まで、日本各地のさまざまな川に適応してきた秘密のひとつだったのです。
さらに今回の発見は、水から陸への進化という壮大なテーマにもヒントを与えます。
四足動物(両生類や爬虫類、哺乳類)の祖先は魚類から進化したと考えられていますが、「どんな魚が、どのように陸上の餌を利用し始めたのか」は進化学の大きな謎でした。
ウナギの両生的な狩りのしくみをさらに詳しく調べることで、今後は進化の道筋や生態多様性の理解がいっそう深まるかもしれません。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)





















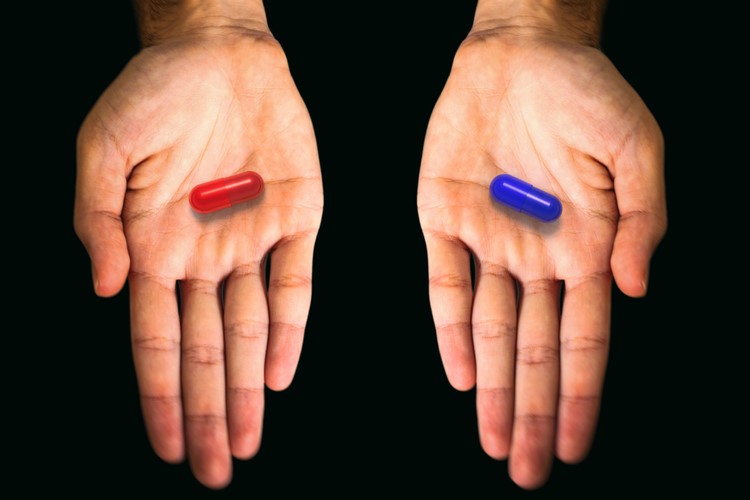






ヘビみたいな格好って、その適用のために都合がよかったんじゃないかな。
同じことをたとえばアジみたいな魚ができそうな気がしない。
これどう見てもゴアウルドだろうという古いネタを使ってみる。
あれももともと水棲動物で陸上に上がるために水辺に来た生き物に寄生するようになったという設定が…。
両生類もニョロニョロしてますし、まだ四肢が発達してない初期の陸上生物にとっても細長い体は陸上移動で有用だったでしょうね。
昭和30年頃の沖縄、雨の夜に大ウナギやスッポンを道で捕まえたことがありました。別の川や池に移動しているものと思っていました。もしかして、スッポンも陸上で狩りをしていたのかも?
これ、ダーウィンがきた
で結構前にやってましたね
あれから論文にまとめたのかな
NHKのダーウィンが来たでウナギの陸上での狩りの映像を見た
論文より実際の映像の方が何百倍もインパクトあるよ
うなぎが陸上で狩りをする際、五感をどのように使っているか興味があります。鼻は盲管でしょうから臭いは使わないとして、視角は、水中に適応した目は(空気の密度が低いから)地上では近眼でしょうし夜の狩りです。耳に相当する器官があっても皮膚の下に隠れていそうですから方向定位は難しそうです。顔などに張り巡っている側線器が振動などを拾っているのでしょうか?
また、奄美大島という多雨で冬でも虫が飛んでいそうな環境は、川の周りを探す価値がありそうですが、九州以北のような四季のしっかりある地域でもみられそうな行動なんオでしょうか。