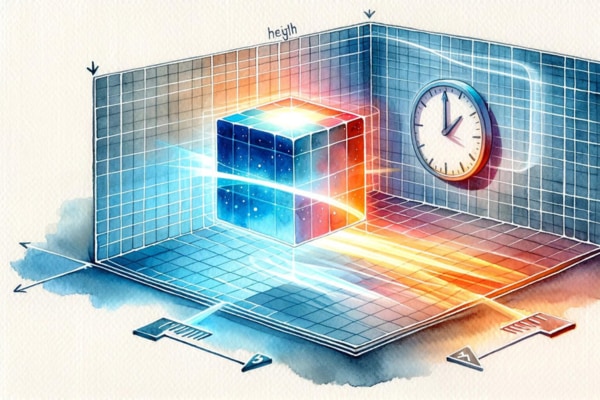新しいAIは人類にわかりやすい数式を吐き出すように調整されている
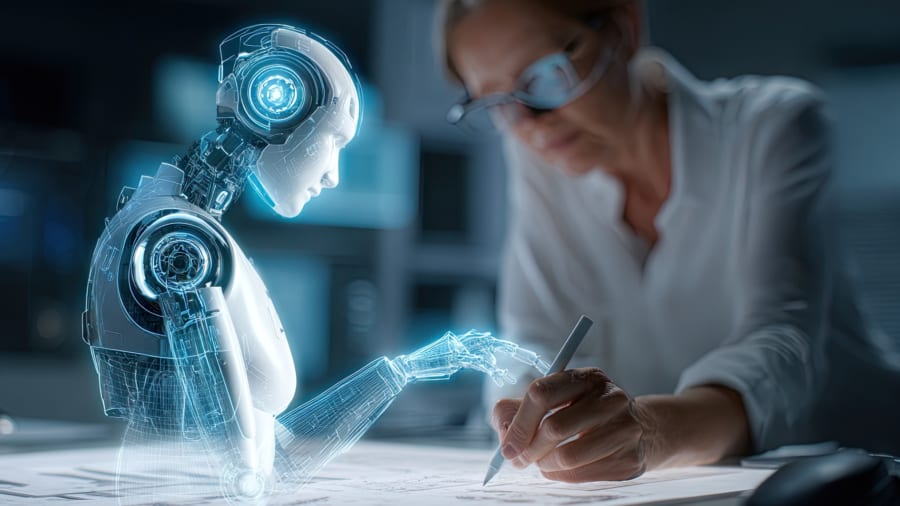
さて、今回の研究の最大のポイントは「AIがどのようにして物理法則を見つけ出すのか」という部分です。
AIが数式を見つけるというのは、なんだか魔法みたいな話に聞こえるかもしれませんが、その仕組みは魔法ではなく、ちゃんとした工夫とアイデアでできています。
研究チームが今回作り上げたAIシステムの名前は、「PhyE2E(フィジー・エンドツーエンド)」と言います。
これは直訳すると「物理を端から端までつなげる」という意味で、要するに観測データを入力すると、その背後にある物理の数式を一貫して見つけてくれる仕組みになっています。
では具体的にどのように数式を見つけ出すのか。
まず、AIがベースとして使っているのは「Transformer(トランスフォーマー)」と呼ばれるニューラルネットワークの一種です。
これはもともと翻訳や文章生成などで大成功したAIで、大量のデータから法則性やパターンを見つけ出すのが得意です。
研究者たちはこのAIを物理学のデータに応用し、観測した数値データを学習させて、そのデータを最も正しく説明できる数式を探すようにしました。
ところが、ここで一つ工夫が加わります。
それが「単位を正しく扱う」というポイントです。
物理の世界では、数式の右側と左側の単位が合っている必要があります。
たとえば距離を求める式なら結果はメートル(m)でなければいけませんし、時間なら秒(s)といった具合です。
AIにとってはただ数字が合えばいいわけですが、ここであえて「単位が合うかどうか」をチェックする条件を加えました。
こうすると、人間の物理学者にとって納得しやすい式だけが出てくることになります。
さらにもう一つ、AIが数式を探す際に「いきなり複雑な式を探す」のではなく、「まず大きな問題をいくつかの小さな問題に分割する」という戦略を取り入れました。
これはまるでパズルを解くように、大きな謎を小さなピースに分け、それぞれに当てはまる式を順番に探していくというやり方です。
実は物理学の研究でも、大きな問題を部分的に切り分けて解いていく手法はよく使われているため、この考え方はとても合理的です。
最後の仕上げとして、AIが見つけた数式にさらに「ブラッシュアップ」をかけます。
AIが最初に提案した数式は、多くの場合まだ完全に洗練されていません。
そこで使うのが「遺伝的アルゴリズム」と「モンテカルロ木探索」という、二つの数式を改良する手法です。
「遺伝的アルゴリズム」とは、式を生物の遺伝子のように扱い、良い数式同士を組み合わせたり、あまり良くない数式を取り除いたりする方法です。
一方の「モンテカルロ木探索」は、可能性がありそうな数式を少しずつ試して、次第に精度が高い式を見つけていく方法です。
これらを組み合わせることで、最終的にはシンプルで精度の高い式が得られます。
こうした工夫により、PhyE2Eはとても高い精度で物理法則を導くことに成功しました。
特に単純な現象については、低複雑度の問題で約98%という精度で数式を正しく当てることに成功しました。
全体的に見ても、従来の似たような手法よりベースラインと比べて最大で約40%高い精度で法則を見つけることができました。
さらに、このAIの強みは、少ないデータしかない状況でも比較的安定して正しい式を見つけられるという点です。
これは実際の物理研究ではとても重要なポイントで、データが不十分な場面でも、AIが頼もしいアシスタントになり得ることを示しています。
このように、AIが単に「ブラックボックス」として役立つだけでなく、人間が理解し納得できる数式を導き出せるようになったことは、科学研究において大きな進歩だと言えるでしょう。
では、この新しいAI「PhyE2E(フィジー・エンドツーエンド)」は、具体的にどのような物理問題に挑んだのでしょうか?
研究チームは、その実力を示すため、宇宙物理学の「解明が難しい」とされる代表的な5つの問題をテストとして選びました。
①「太陽の黒点の長期リズム」
②「地球の周りのプラズマ圧のシンプル法則」
③「太陽の自転スピードの法則」
④「太陽からのEUV光の強さを決める法則」
⑤「月が作る電場の法則」
ひとつ目は、太陽の表面に現れる黒点の「長期的なリズム」を解明するという問題です。
実は太陽の活動は、約11年周期で活発になったり落ち着いたりすることが知られていますが、その背景にはもっと長い周期も潜んでいると考えられてきました。
しかし、実際にどのような周期が隠れているのかは、これまでの研究でははっきりと特定できていませんでした。
そこで研究チームは、観測された黒点数のデータをAIに学習させ、「数式」を導き出させました。
すると、このAIが提示した数式は、よく知られる約11年周期だけでなく、約60年周期や約205年周期といった、これまで明確には知られていなかった長周期の存在まで示唆していたのです。
しかも驚くことに、この60年周期というのは、東アジアで昔から暦や干支などの周期で用いられてきた60年のサイクルと偶然一致しています。
また約205年という周期も、太陽系の惑星運動と関係している可能性があり、今後の研究で検証が進むと見られます。
つまり、AIが導き出した数式は、これまで人類がぼんやりとしか捉えられていなかった現象を、明確な形で示すことに成功したのです。
ただし、この新しい周期の存在は、今後さらに精密な観測や理論的な検証を経て確かめられる必要があります。
ふたつ目は、地球の周りに広がる宇宙空間(近地球空間)に存在するプラズマ(電気を帯びた粒子の集まり)の圧力が、「地球からどのくらい離れると、どれくらい弱くなるか」という法則を導く問題です。
従来は、衛星観測データを使って、「プラズマの圧力が地球から離れると指数的に弱まる」という経験則が知られていました。
ところがPhyE2Eは、同じデータを元にもっとシンプルでわかりやすい「近地球圏では距離の2乗におおむね反比例する」という新たな関係を導き出しました。
距離の2乗に反比例するというのは、重力や光の強さが遠ざかるほど弱まる法則と同じタイプの減少のしかたです。
このように、物理の基本的な考え方と同じ形でプラズマ圧力も減ることが示されました。
この新しい数式は、他の衛星データでも高い精度で再現され、今後の宇宙空間での安全対策や衛星運用にも役立つ可能性があります。
研究ではこの2つにさらに3つを咥えた合計5つの課題を通じて、このAIが出した数式の多くは、人間の直感に合う物理的な意味を持つことが確かめられました。
物理学における「理解」とは、「原因と結果の関係を人間が理論的に納得できる」ことを意味します。
物理学者が求めているのは単なるデータの再現性ではなく、その現象を支配する根本的なルールです。
人間本位な考えではありますが、ここが守られないと、物理学は自然の神秘を解明する場ではなく、単なる実用に便利な公式を発見するだけの場になってしまうでしょう。
そういう意味でAIが「自然の法則を人間が理解できる数式として提示できる」ことを実際に証明した本研究は非常に大きな意味があると言えます。




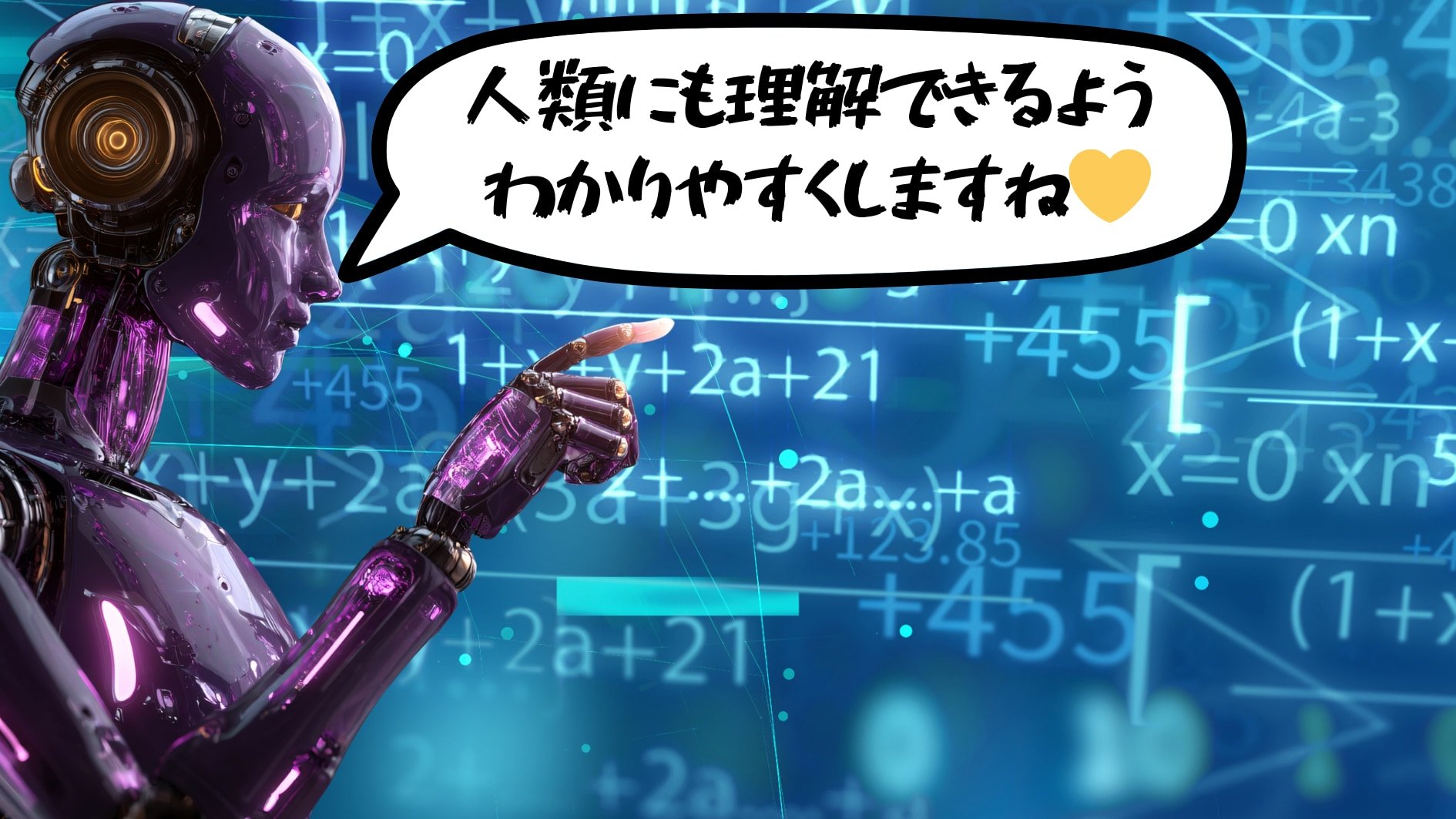



























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)