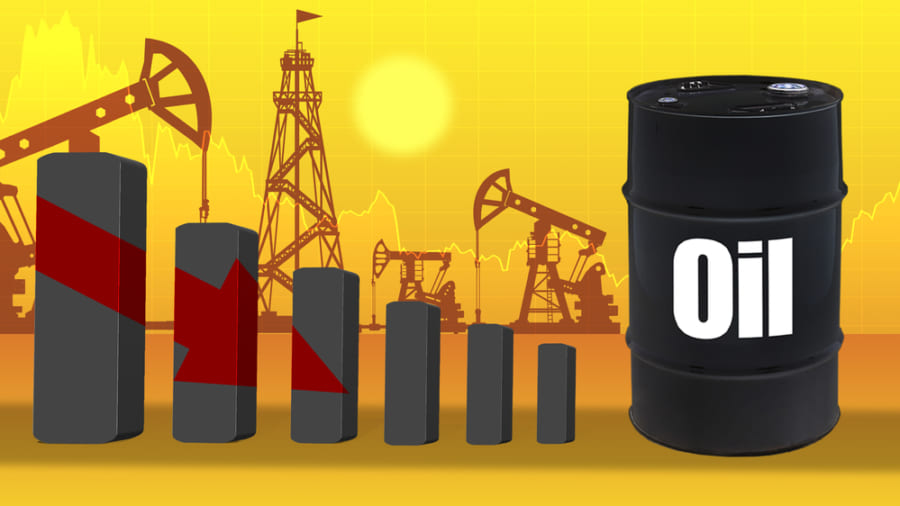AIが物理法則を発見する時代が既に来ているが人間はそれが理解できない

「物理法則を発見する」という言葉を聞くと、ケプラーやニュートンのような偉大な科学者が、天から舞い降りるような「ひらめき」を得る場面をイメージするかもしれません。
実際、歴史をひも解けば、物理の法則を数式として導くためには、長く苦しい試行錯誤がつきものでした。
たとえば17世紀の天文学者ケプラーは、火星の軌道を調べて「楕円」というシンプルな法則を見出すまで、実に40種類もの仮説を立てては失敗を繰り返しました。
19世紀の物理学者ファラデーも同様で、電気と磁気の関係を理解するまで、何度も実験を繰り返してやっと「電磁誘導の法則」にたどり着いたのです。
つまり、人類にとって自然の法則を見つけるというのは、途方もない忍耐と「ひらめき」が不可欠な営みだったのです。
ところが近年、そうした「ひらめき」や「直感」の領域に、人工知能(AI)が足を踏み入れようとしています。
それが今回の研究でも使われている「シンボリック・レグレッション(記号的回帰)」と呼ばれる手法です。
これは簡単に言えば、「実験や観測のデータをコンピューターに読み込ませると、背後に隠れている数式を見つけてくれる」という便利な仕組みです。
人間がいちいち仮説を立てる代わりに、AIが膨大なデータを分析して「この現象には、こんな数式がぴったり合いますよ」と教えてくれるわけです。
一見すると夢のようですが、ここにはひとつ大きな問題がありました。
それはAIが見つける数式が「人間にとって分かりやすい」とは限らないことです。
というのも、AIは「結果が正しければそれでいい」という姿勢で数式を作り出します。
ただし、近年はAI側にも「単位の整合性」や「式の簡潔さ」を評価する仕組みを取り入れ、人間にとって納得しやすい形を目指す研究も進んでいます。
この「ブラックボックス」問題は科学者にとっては重大な障害でした。
いくら予測が正しくても、その式が物理的に何を意味しているのか理解できなければ、本当の意味で「物理法則」として役立てるのは難しいからです。
しかし、人間が理解できなくても役立つ式が既に多数発見されているのも事実です。
たとえば海で突然現れる荒波(ローグウェーブ)を予測する式です。
現実の海で得られた観測データをAIと数理解析で調べると、「人間の直感ではすぐには理解できない数式」が現れました。
ところが、この数式をもとにした発生確率モデルによって、異常波の発生地点やタイミングをある程度予測できることが分かり、安全対策への応用が進められています。
(※この式の人間の理解度は5段階中4「ほぼ解明だが部分的には未解明」段階です)
また、惑星が遠くの星の前を横切るときに起きる「重力マイクロレンズ」という現象では、近年の研究で複数の退化解(同じ観測結果を説明できる別の数式)があることが分かり、AIを使った解析によってその構造を整理する試みも進んでいます。
このような解析では、観測データの違いを一つの仕組みで説明できる可能性が示され、観測の理解がさらに深まりました。
(※この式の人間の理解度は5段階中4「ほぼ解明だが部分的には未解明」段階です)
量子物理学の分野でも、機械学習とシンボリック回帰という手法を使って量子の性質を予測する式が多数導き出されています。
しかし、それらの式がなぜそうなるのかを人間が理解するには、まだまだ長い道のりが必要です。
(※この式の人間の理解度は5段階中2「未解明の部分が多い」段階です)
さらに数学の世界でも、ラマヌジャン・マシンと呼ばれるAIシステムが作り出した「謎めいた数式」が存在しています。
このAIは、さまざまな数字を組み合わせて、シンプルで美しいけれども一見すると非常に奇妙な数式を大量に見つけています。
興味深いことに、AIが導き出したこれらの新しい数式は、コンピューターで精密に検証すると「正しい」と言えるほど極めて高い精度を示します。
にもかかわらず、「なぜこの数式が正しいのか」「どんな数学的な原理が背後にあるのか」を人間が理論的に証明できないケースが非常に多く残っています。
(※この式の人間の理解度は5段階中2「未解明の部分が多い」段階です)
つまり、今のAIが導く物理法則は「理由はよく分からないがよく当たる」ことが多いのです。
ただ、この状況は決して満足できるものではありません。
やはり科学にとって重要なのは、その現象がなぜ起きるのかを説明できることです。
そこで清華大学らの研究チームは、シンボリック回帰の手法を大幅に改良して、「物理的な意味を人間が納得できる形で表した数式」をデータから直接導き出すという挑戦に踏み切ったのです。
人間の直感とAIの予測力が融合することで、「ブラックボックス」という大きな壁を打ち破る可能性が、いよいよ現実的になってきました。




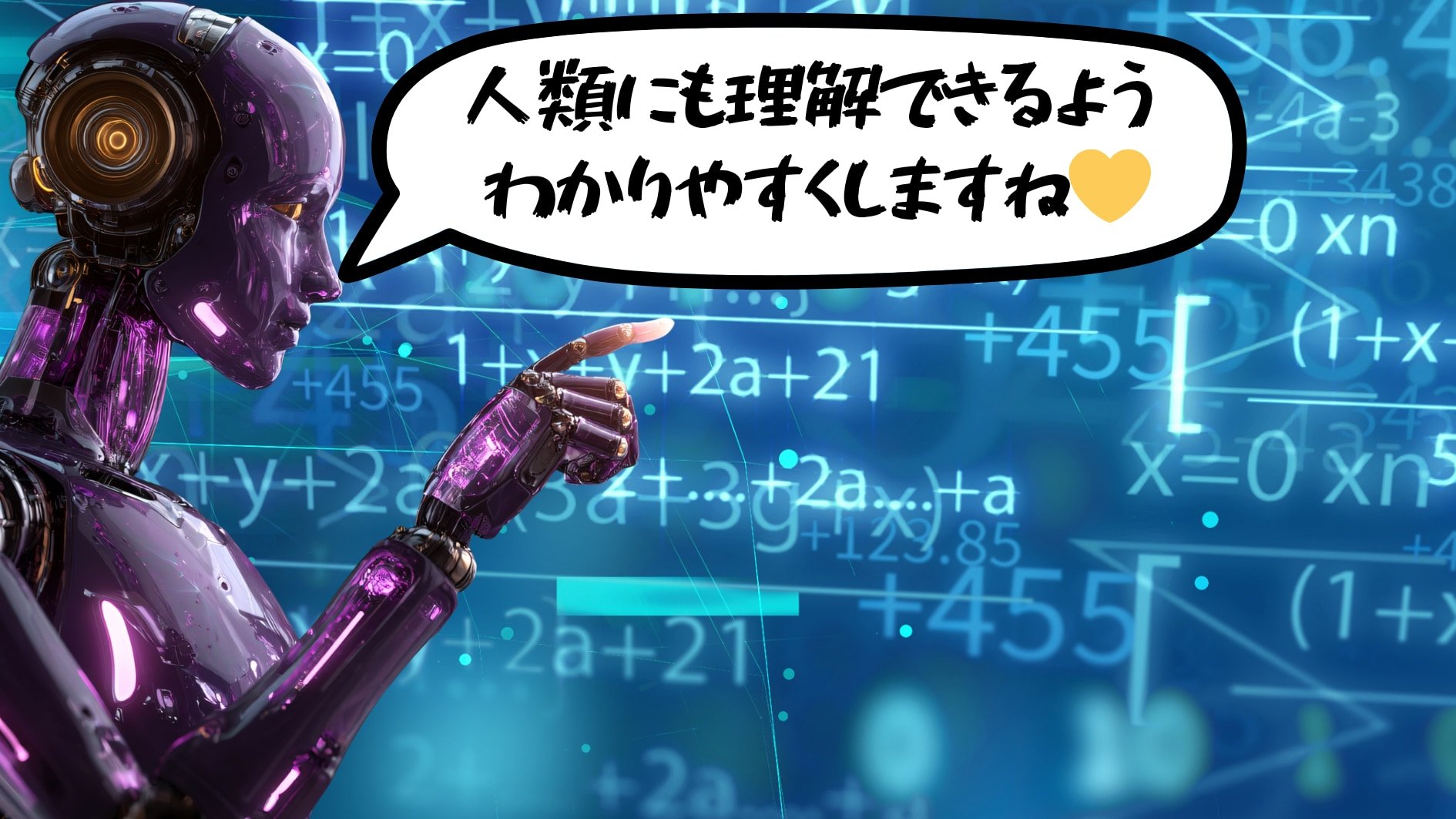


























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)