職場の誘いが「嬉しい人」と「負担な人」の分かれ目
同僚からの誘いは、一律に良い影響をもたらすわけではありません。
多くの人は「自分を気にかけてくれた」「仲間に入れてもらえた」と感じ、感謝が高まり、誘ってくれた同僚に向けた組織市民行動(organizational citizenship behavior:OCBI)が増える傾向が見られました。
一方で、「断りづらい」「自分の時間が減る」と感じる場合は、心理的資源が消耗し、感情的疲労が高まりやすくなりました。
その結果、その日や、翌日以降にかけて意欲の低下や離脱行動につながる傾向が確認されました。
つまり、誘われるという出来事そのものが、感謝を生む“資源の連鎖”にも、ストレスを生む“消耗の連鎖”にもなりうるのです。
明暗を分けたのは、対人自己効力感(interpersonal self-efficacy)、すなわち「人づきあいをうまくこなせる」という自信でした。
この自信が高い人は、誘いを「信頼のサイン」と捉えやすく、感謝や帰属意識が強まり、協力行動が自然に増えます。
一方で、この自信が低い人は、「うまく対応できるか不安」「場を盛り上げねばならない」と感じやすく、ストレスや疲労につながります。
つまりこの問題においては、その人の性格特性よりも、社交の場でうまくやれるという“自信”が鍵だったのです。
日本では、飲み会が親睦の場として定着してきましたが、近年は「気を使って疲れる」「断りづらい」と感じる人も増えています。
今回の結果は、こうした感覚の差が性格の違いだけではなく、心理的資源や自己効力感の差で説明できることを示します。
誘う側は、相手の状況や心の余裕を尊重し、「断っても関係が悪化しない」「自由に選べる」雰囲気づくりを意識することが大切です。
ただ、本研究はアメリカと台湾で実施されたため、文化的背景の影響をさらに検証する必要があります。
また、飲み会やバーベキューなど、活動の内容や頻度による違いも十分には解明されていません。
職場の誘いを“交流のチャンス”と感じるか、“負担”と感じるかは、あなたの社交への自信に左右されます。
同時に、誘う側の小さな配慮が、相手の心の資源を守り、チーム全体の余裕を生み出します。
「飲みニケーション」の成立には、互いの心に余裕を残せるかどうかにかかっているのです。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)




















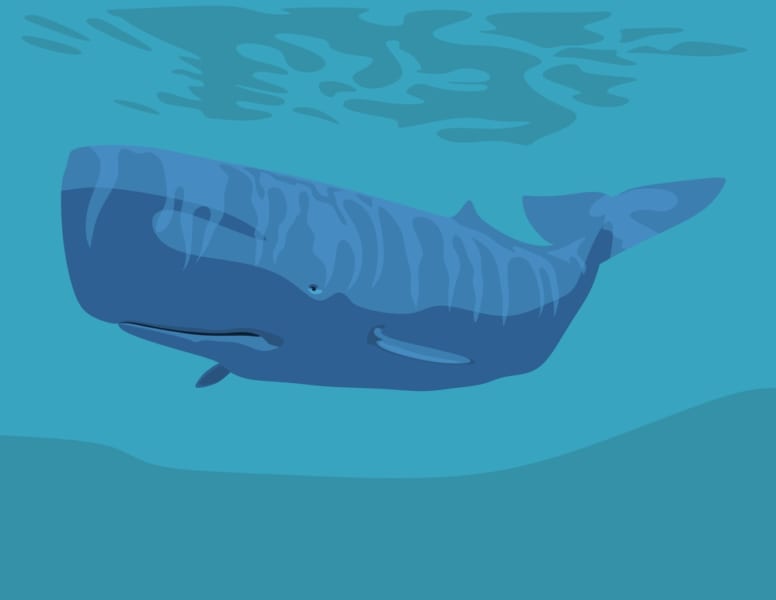







どうせくだらないことしか話さないやつに誘われたら時間の無駄だからいやなんだよ。
素晴らしい人から誘っていただいたら喜んで参加させていただきます。
お酒、飲めネんだわ…。
スマドリがあるじゃないか!
と言いたいところですが、私はあの雰囲気が好きじゃない。
ぜひ日本でも調査してほしい。
定型の人にとって対人コミュニケーションは「娯楽」のひとつなのだときいたことある
自分には毛ほどもない発想だわ
自分の場合、同じ人に誘われて気を遣うにしても、内容次第。飲み会や食事会はイヤ。スポーツなどその行為自体が楽しい場合や、その人に誘ってもらわなければ体験できないような事柄なら喜んで。そう考えると、誘ってくれた人とのコミュニケーションを楽しむ気は自分には無いことが分かった。
日本人には適応されない論理
まずアルコール耐性を考慮してよ 話はそれから