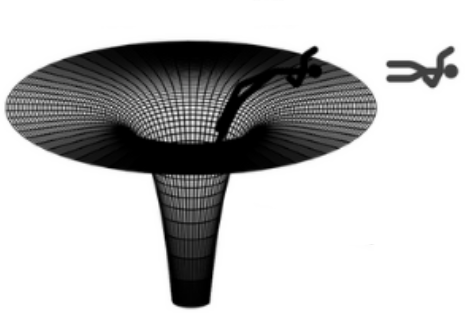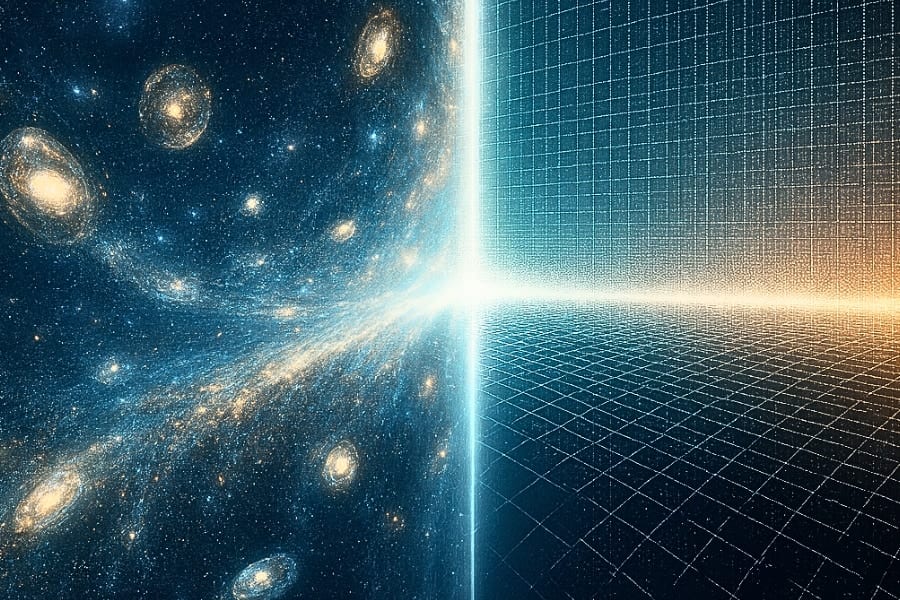Point
■生き物の「死んだふり」をコントロールする遺伝子群が、世界で初めて明らかに
■遺伝子解析によると、ドーパミンに関連する遺伝子が「死んだふりの時間」を変化させることが判明
敵に襲われたとき、時々「死んだふり」をする動物がいます。理由には諸説ありますが、死を装うことで一種の防御行動をとっているというのが一般的な仮説です。
このほど岡山大学、玉川大学、東京農業大学の共同研究により、「死んだふり」をコントロールする生物の遺伝子群が世界で初めて明らかになりました。
その鍵を握るのは、運動調節や意欲に関係する神経伝達物質である「ドーパミン」。研究チームは、生物の動きや生き延びるための行動を支配する主要な遺伝子がドーパミンであることを、今回世界に先駆けて明らかにしたのです。
https://www.nature.com/articles/s41598-019-50440-5
ドーパミンが「死んだふり」の時間を変化させる
死んだふりは、捕食ターゲットになりやすい生き物にとって、必要不可欠な防衛スキルです。
この行動は珍しいものではなく、哺乳類や魚類、鳥類、昆虫とほぼすべての生物に見られます。
今回の実験では、穀物類を中心とした世界的な害虫である「コクヌストモドキ」が用いられました。

研究チームは約20年にわたり、刺激を与えると死んだふりをする「タイプ1」と刺激を与えても死んだふりをしない「タイプ2」のコクヌストモドキを育成していました。
この2つのタイプに対してDNA解析を行ったところ、発現の異なる518もの遺伝子がタイプ間に存在することが判明したのです。
特に、これら遺伝子群のうち、チロシン代謝経路に属するドーパミン関連の遺伝子において、タイプ間に大きな発現の差があらわれることが分かりました。

さらに、タイプ間では脳内で発生するドーパミンの量が異なっており、このドーパミンを体内に注入することで、死んだふりの時間が短くなるといいます。
「死んだふり」行動が遺伝子レベルで解明されたのは、世界でも初めてのこと。今後、研究チームは「この発見が人の行動についても同じ影響を与えるのか」について調査を進める予定です。










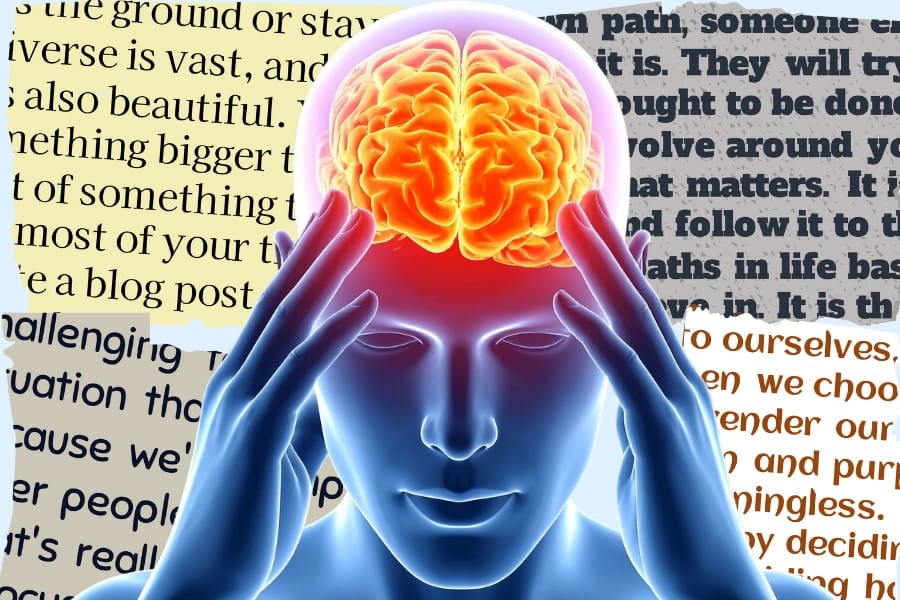





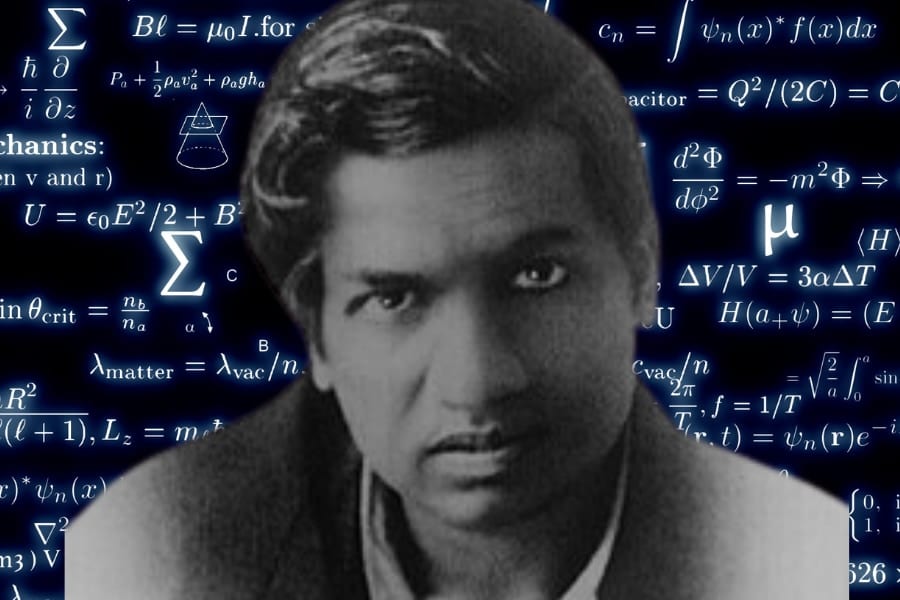
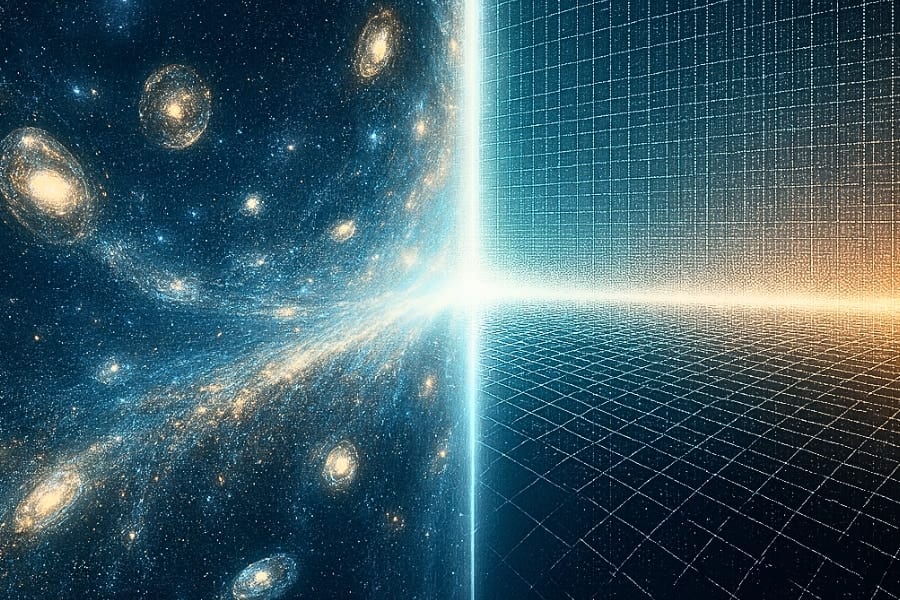









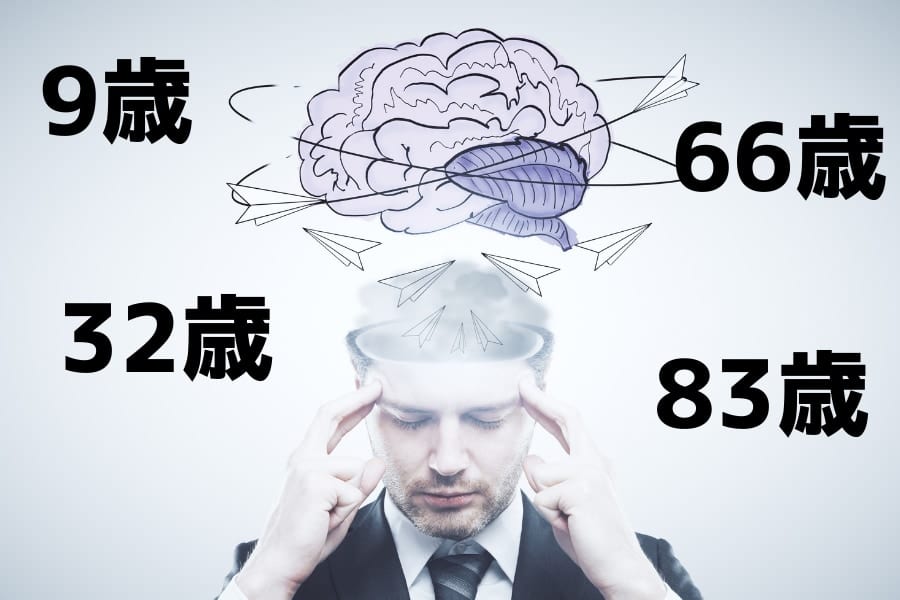


![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)