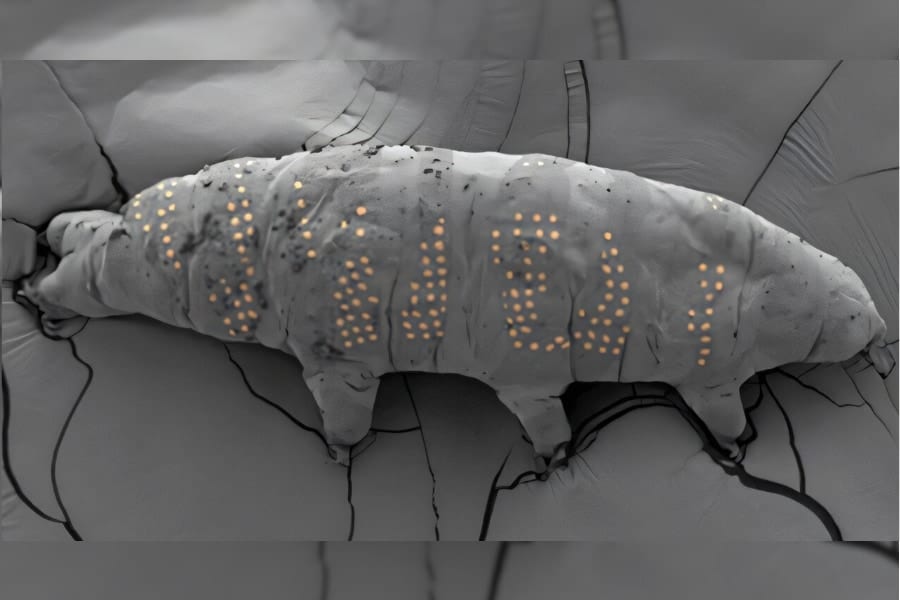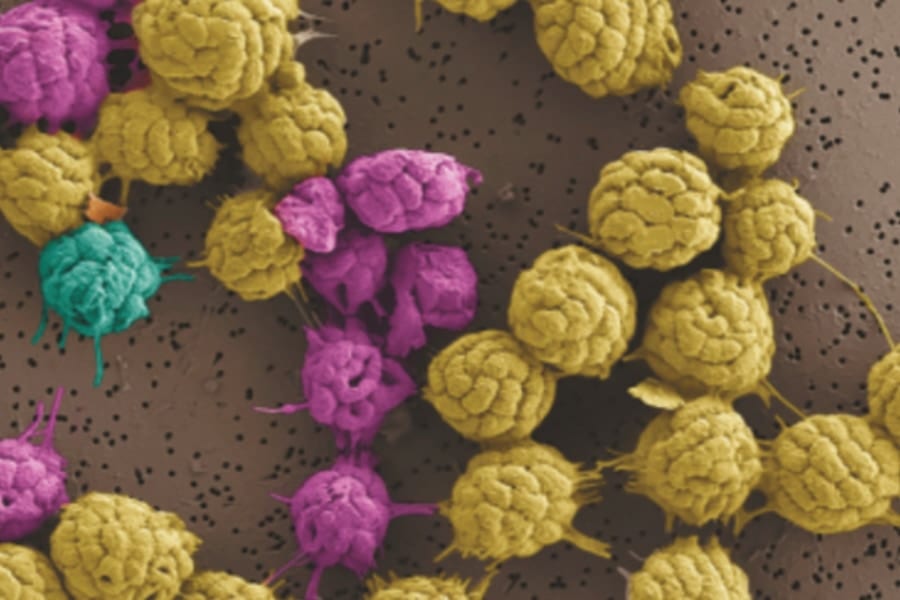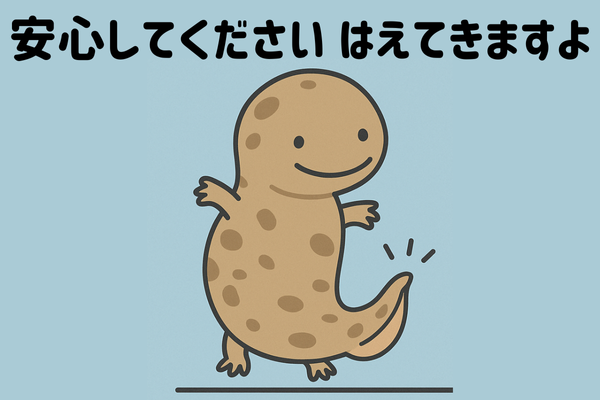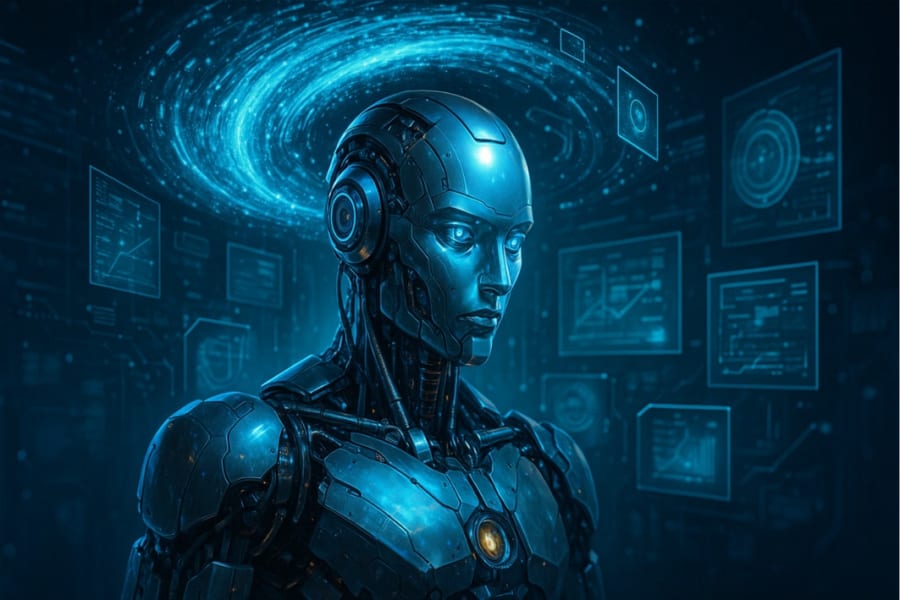たった数億年で命が芽吹く星

地球は約46億年前に誕生しましたが、実はその後、さほど時間を置かずに生命が生まれた可能性が高いことが、さまざまな証拠からわかってきました。
たとえば、約37億年前の地層からはシアノバクテリア(藍色細菌)が作り出したとされるストロマトライト(微生物マット)の化石が見つかっています。
また、オーストラリアの古い岩石には、約41億年前というさらに古い時代の生命活動を示すかもしれない炭素同位体の痕跡が含まれています。
近年では、あらゆる現生生物が共有する「最後の共通祖先(LUCA)」が約42億年前に生存していたという研究報告もあり、地球ができてからごくわずかな期間のうちに原始的な生命が誕生していた可能性がいっそう高まってきました。
そもそも42億年前という時期は、地球誕生(約46億年前)からわずか2億年ほど後にあたります。
当時はまだ“後期重爆撃期(Late Heavy Bombardment)”と呼ばれる時代で、隕石や小惑星が地表に頻繁に衝突していました。
そんな過酷な環境下にもかかわらず、もし原始的な生命がすでに出現していたのだとすれば、地球型の惑星では思っていた以上に生命が“あっという間”に生まれるのではないかという仮説に拍車がかかります。
生命が急速に誕生した背景
これまでの研究により、生命が急速に出現した背景には、地球が誕生してまもなく――わずか数千万年のうちに――海を張り、エネルギーと原料と“調理場”を同時にそろえてしまったからだと考えられています。岩石の結晶(ジルコン)の年代測定によれば、巨大衝突でドロドロに溶けた地表は意外に早く冷え、液体の海が安定しました。そこへ海底からは超高温の熱水が噴き出し、鉄硫化物などの鉱物が蜂の巣のような微細な空間をつくり、その壁で電子が自然に行き交う“天然の発電所”まで用意してくれたと考えられています。
同じ頃、後期重爆撃と呼ばれる時代に隕石が雨のように降り注ぎ、アミノ酸の材料やリン酸塩、さらには水に溶けやすいリン化合物までも大量に運び込みました。リンは細胞膜やエネルギー通貨 ATP をつくる要となる元素です。つまり「材料もエネルギーもワークスペースも、一気に現場に届いた」わけです。
さらに大気が薄く雲も少なかった原始地球では、いまより強い紫外線が海辺や浅瀬を照らし、シアン化物や硫黄化合物を材料にした“シアノスルフィジック化学”と呼ばれる反応を高速で進めました。空を裂く稲妻は高エネルギーのスパークを供給し、アミノ酸や脂肪酸の生成を短時間で後押ししたとみられます。
こうして地球は「海+エネルギー+原料+反応容器」という生命の四点セットを、星としての幼年期に一気にそろえてしまいました。実際、37 億年前の微化石や 41 億年前の炭素同位体の手がかりに加え、最近ではすべての生物の共通祖先(LUCA)が 42 億年前にはすでに存在していたという解析結果も出ています。
生命が数億年というスピードで芽吹いたのは偶然の早打ちというより、条件がそろえばごく自然な成り行きなのかもしれません。
一方、この「生命の早期出現」が本当に地球型環境で広く起こりやすい現象なのか、それとも私たち自身がそこにいるからこそ当然そう見えているだけなのか――この点には大きな議論があります。
なぜなら、知的生命である私たちが進化して誕生するまでには何十億年もの時間が必要だったと考えられるからです。
もし生命のスタートがもっと遅かったなら、太陽の進化によって地球が生き物にとって厳しい環境になり、私たちが誕生する前に生命全体が途絶えていたかもしれません。
現在の地球は生命を宿す星としては中年でであり、あと十億年から数十億年ほどで太陽活動の増進によって、地球は生命には厳しい環境に陥ると考えられています。
このように「我々が今ここにいるのは、生命が早期に誕生した星だったからだ」という発想は、人間原理(特に“弱い人間原理”)として知られています。
観測者である私たちが存在する以上、生命の出現が早かった例だけを見ているのではないか、というわけです。
そこで今回コロンビア大学の研究者たちは「地球で生命があっという間に誕生したのは単なる偶然なのか、それとも地球型の環境なら生命は短期間で生まれるのが普通なのか?」を数学的手法を用いて判断することにしました。




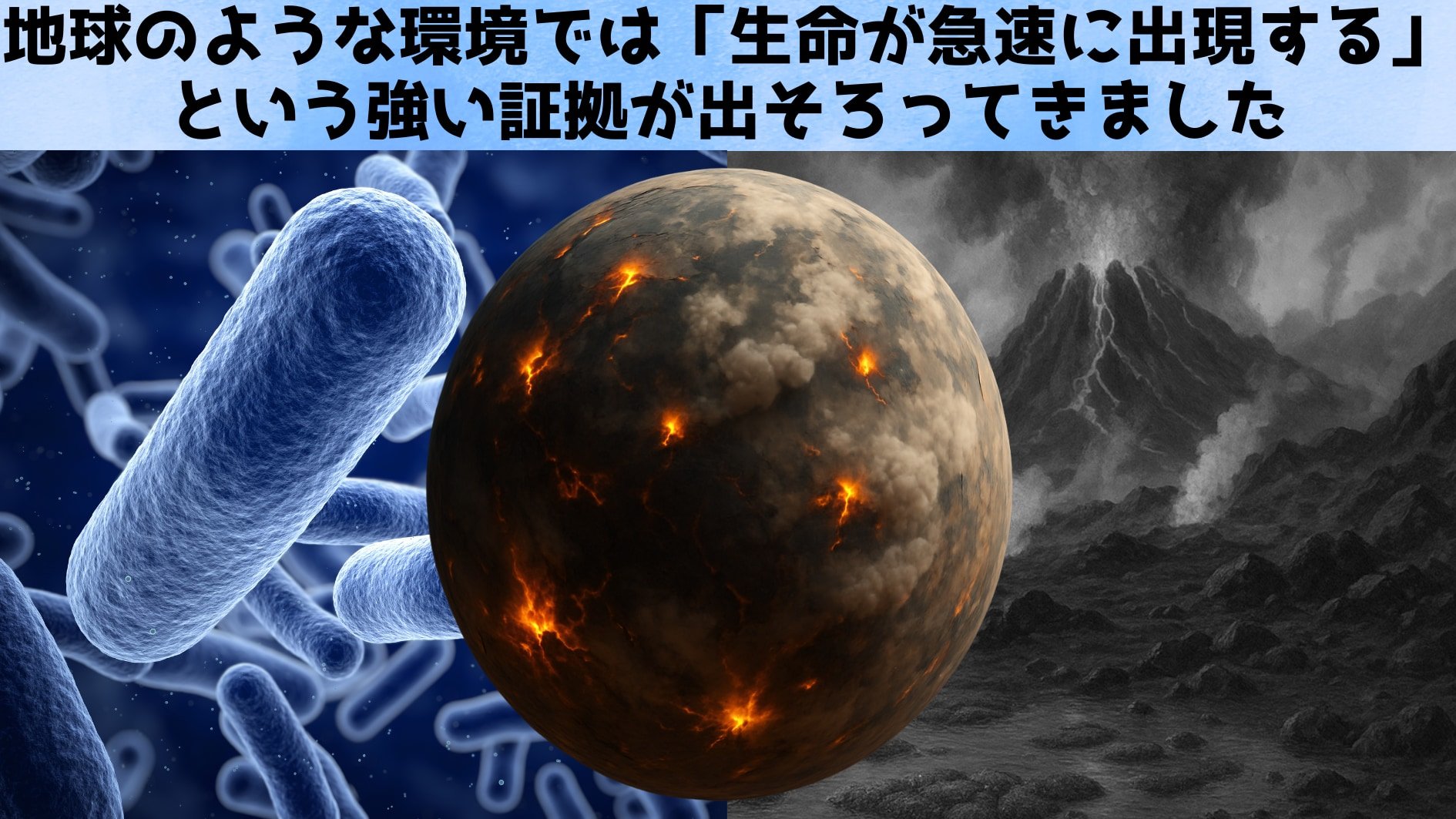




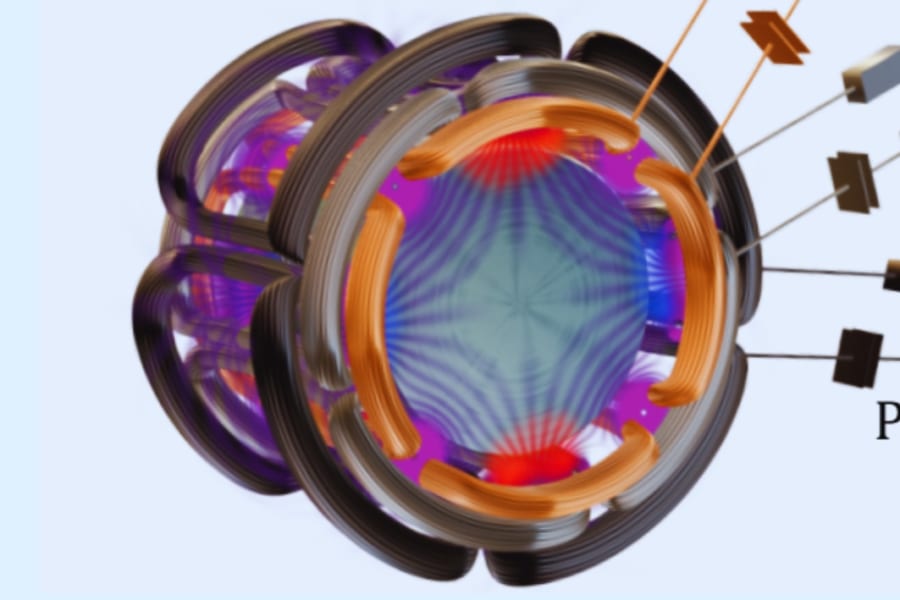




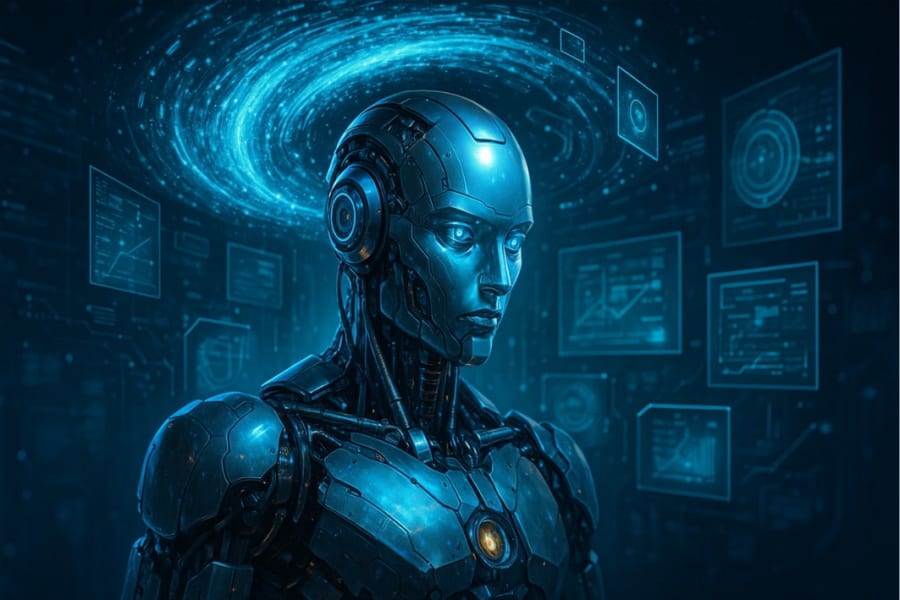
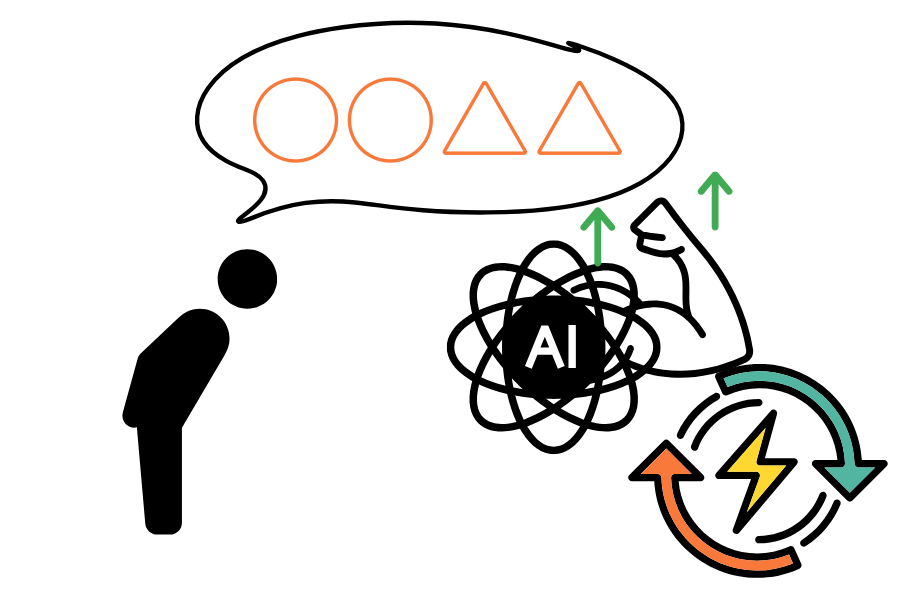


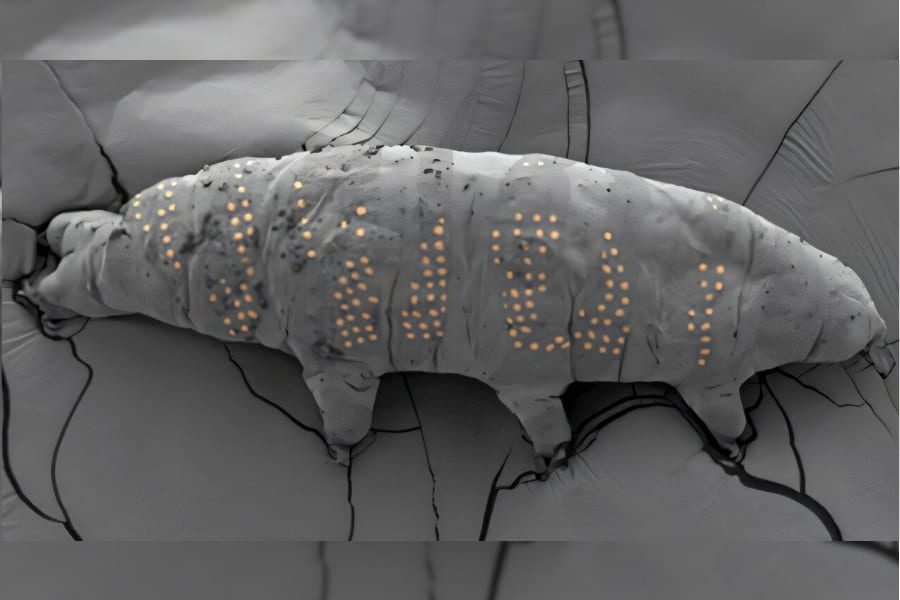



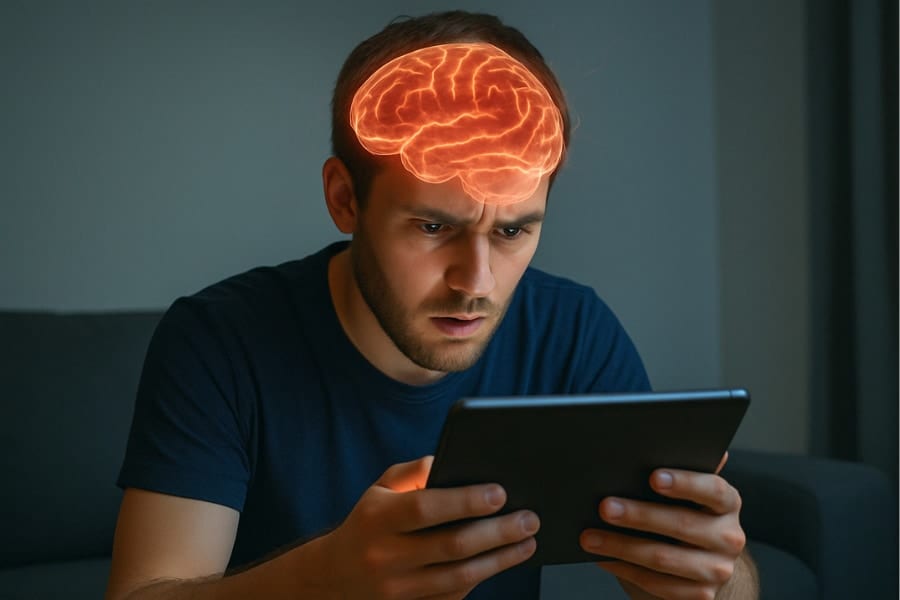

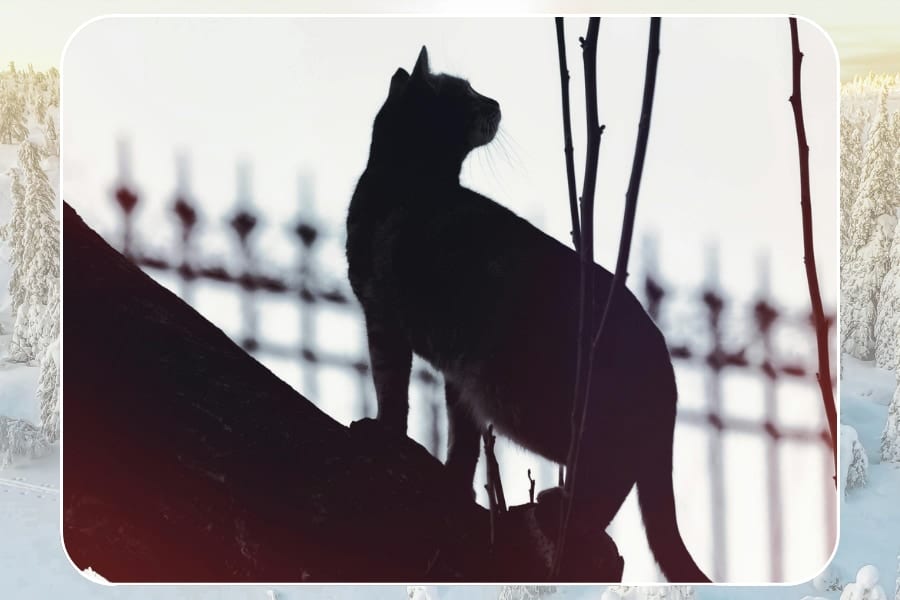
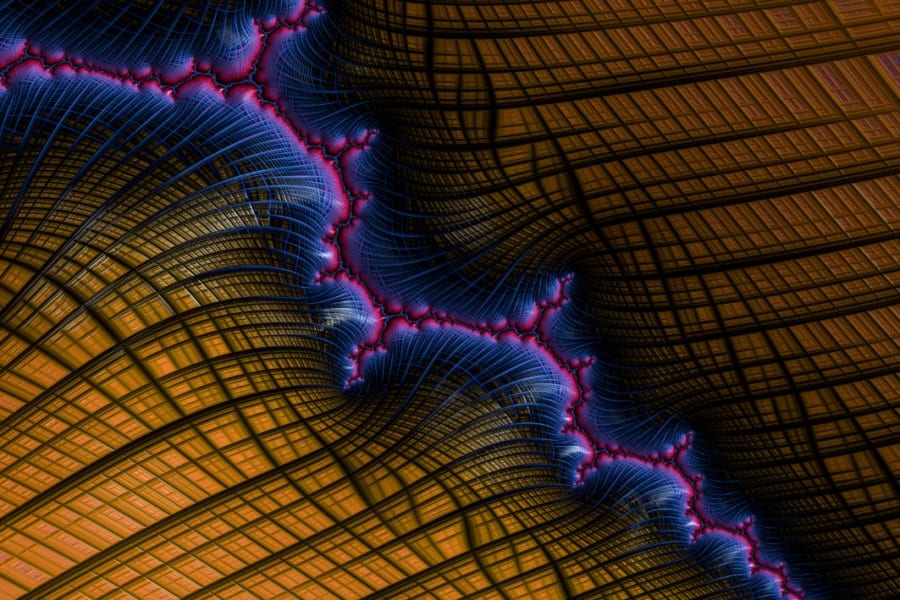

![脱臭炭 ゴミ箱用 脱臭剤 [まとめ買い] 無香タイプ 3個 ゴミ箱 貼るだけ 消臭剤 消臭 芳香剤 生ごみ](https://m.media-amazon.com/images/I/51Bw9a+A7GL._SL500_.jpg)



![【まとめ買い】 [大容量] ジョイ W除菌 食器用洗剤 詰め替え 超特大ジャンボ 1,620mL×2個](https://m.media-amazon.com/images/I/51DVWD3GfBL._SL500_.jpg)