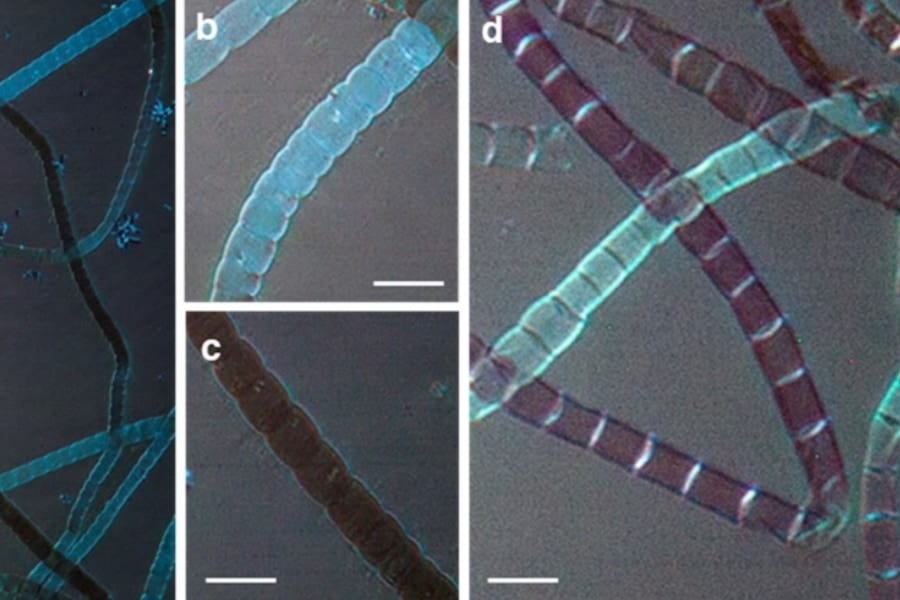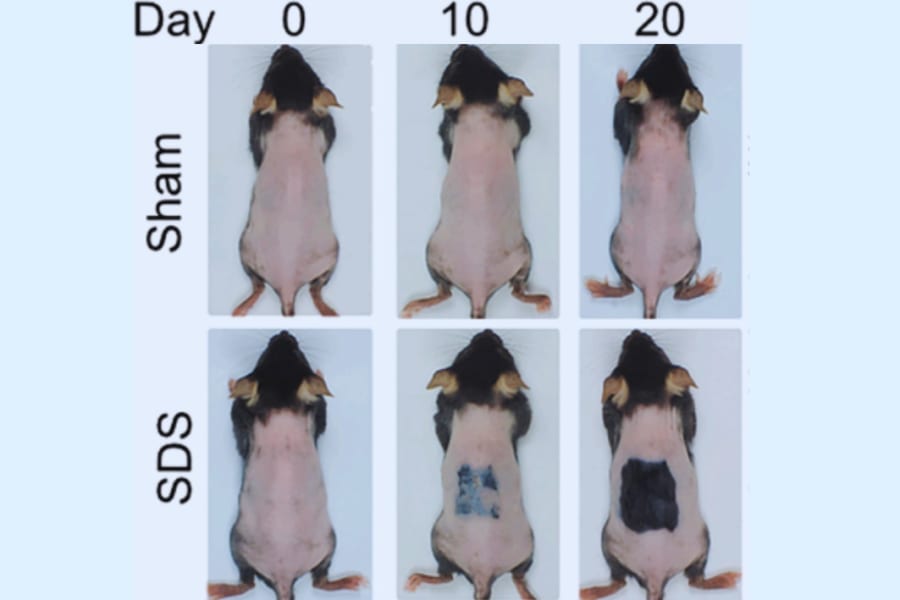卵子と精子の間にある食う食われるの関係

哺乳類における受精とは、オスの生殖細胞である精子とメスの生殖細胞である卵子が出会い、互いの細胞膜を融合させて一つの受精卵を作り出す現象です。
言葉で聞くと「精子が卵子の中に入り込むだけ」とイメージしがちですが、実際には多種多様な分子が時系列に連携し合う、きわめて精巧なプロセスが進行しています。
その中でも特に重要とされてきたのが、精子に存在するタンパク質「IZUMO1(イズモワン)」と、卵子側にある受容体「JUNO(ジュノ)」です。
実はこの2つの分子はそれぞれ、“縁結びの神様”として知られる出雲大社から名付けられたIZUMO1と、“結婚と出産を司る女神”の名を持つJUNOという、まさに“縁結びの象徴”ともいえる由緒正しき名前を与えられています。
2005年に井上直和教授らがIZUMO1を発見した当初から、「精子と卵子の融合には鍵と鍵穴の関係となる分子がある」という見方がされており、IZUMO1とJUNOががっちり組み合うことで受精が引き起こされると考えられていました。
ところが、さらに細かく調べてみると、受精にはIZUMO1とJUNO以外にも必須の膜タンパク質が何種類も存在することが分かりました。
たとえば卵子側には「CD9」、精子側には「SPACA6」「TMEM95」「FIMP」「TMEM81」「DCST1」「DCST2」といった面々が並び、いずれも配偶子(精子と卵子)どうしの融合に欠かせない要素です。
しかし、名前が分かったところで、それぞれがいつ、どのタイミングで、どのように働いているのかが長らく謎でした。受精はわずかな時間で完了してしまい、しかも卵子は不透明な大きな細胞ですから、中で何が起こっているのかをリアルタイムで見るのは至難の業だったのです。
いわば“ブラックボックス”の中で、どうやって精子と卵子が協力し合い、細胞膜を融合させているのか――多くの研究者がその謎に挑戦してきたものの、細部まで解明するのは極めて難しいテーマでした。
そこで今回研究者たちは多数の遺伝子改変マウス(ノックアウトマウス)を用いて精子・卵子の融合過程を詳細に解析し、受精直前の卵子で何が起きているのかを調べました






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)