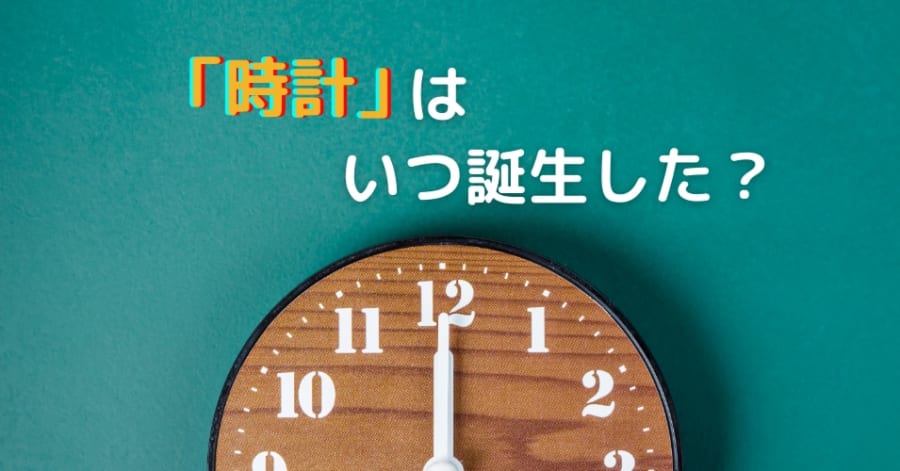言語は気候の影響を受けない?100年間続いた常識への挑戦

暖かい国に旅行に行くと、現地の言葉が伸びやかに響いて聞こえることはありませんか?
逆に寒い国では、言葉がぎゅっと詰まって聞こえることもあるかもしれません。
言語がこうした地域ごとの気候と関係しているのではないか、という直感的な疑問は昔から人々の興味を引いてきました。
でも、言語の研究では長い間、環境が言葉の音そのものに影響を与えることはないと考えられていました。
20世紀初頭、言語学者エドワード・サピアは「言語の音の仕組みは環境からほとんど影響を受けない」と述べました。
その後、チョムスキーの生成文法が広まったことで、「言語の基本的な構造は人間に生まれつき備わったものであり、環境による影響はごく限られている」という考え方が定着しました。
つまり、長い間、言語は独立した閉じられたシステムだと信じられてきたのです。
ところが近年、この考え方に疑問を投げかける研究が次々と現れ始めています。
例えば高地では空気が薄く、肺の圧力を使った独特な破裂音(エジェクティブ音)がよく使われることが報告されています。
また、降水量や湿度の低さが母音の比率に影響を与える可能性が指摘されており、乾燥地域ほど母音が減ってソノリティが低くなる傾向が別の研究で報告されています。
こうした例からも、人間の言語の音が環境に影響される可能性が徐々に認識されるようになってきました。
その中でも、最近特に注目されたのが、「気温」と「言語の響きやすさ(ソノリティ)」の関係です。
これまでにも、小規模な研究で「暖かい地域の言語ほど響きやすくなる傾向がある」と指摘されていましたが、調査された言語数が100程度と少なく、十分な根拠にはなっていませんでした。
そこで今回、ドイツ・キール大学の言語学者ソーレン・ヴィヒマン博士らの国際チームは、より大規模で包括的な調査によってこの仮説を検証しようと考えたのです。
もし気温が言語の響きに本当に関係しているなら、それは世界中の多くの言語で一貫して現れるはずです。
果たして、この仮説は正しいのでしょうか?




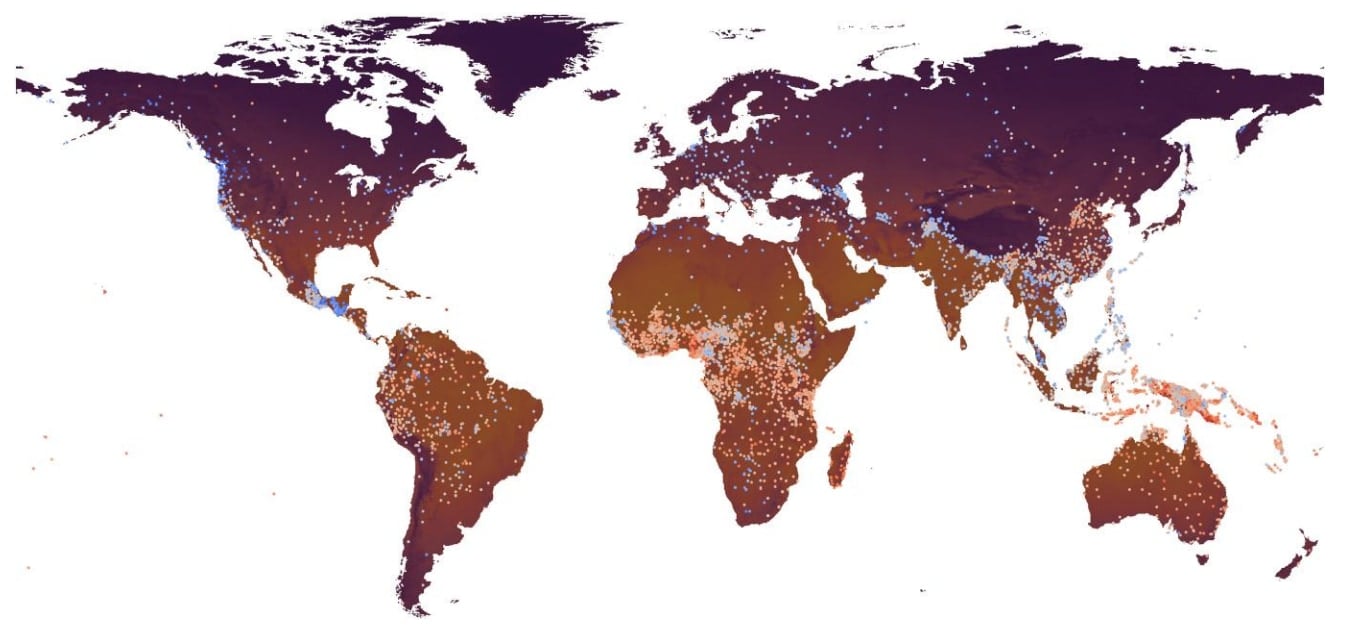























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)