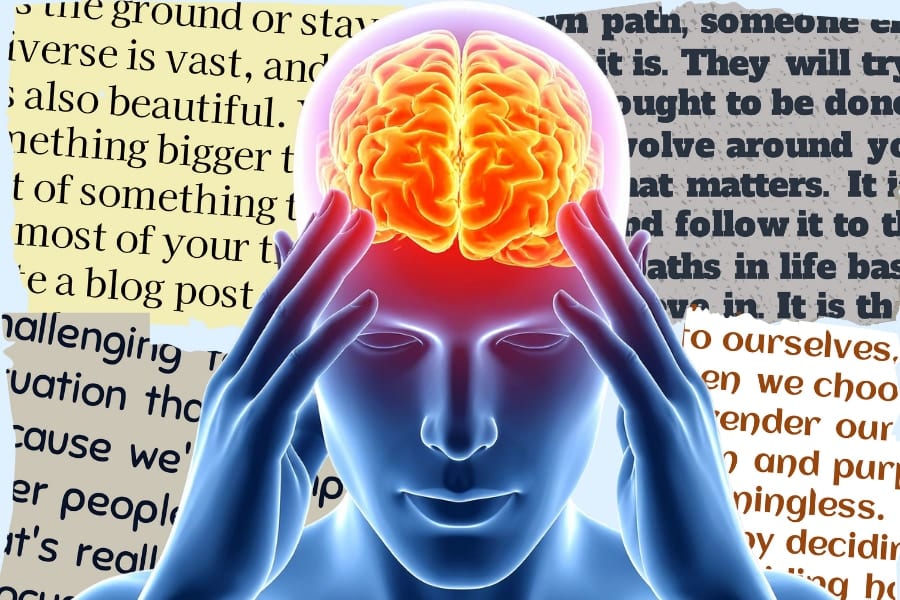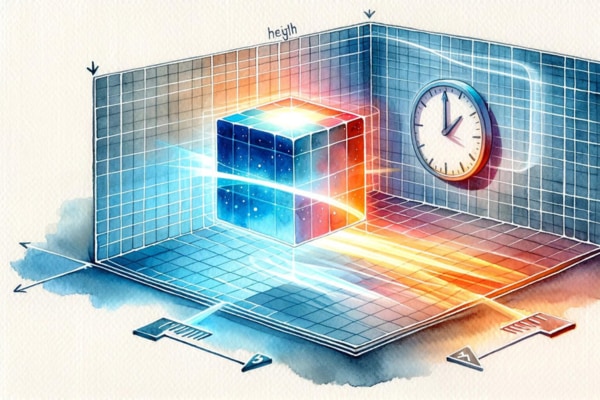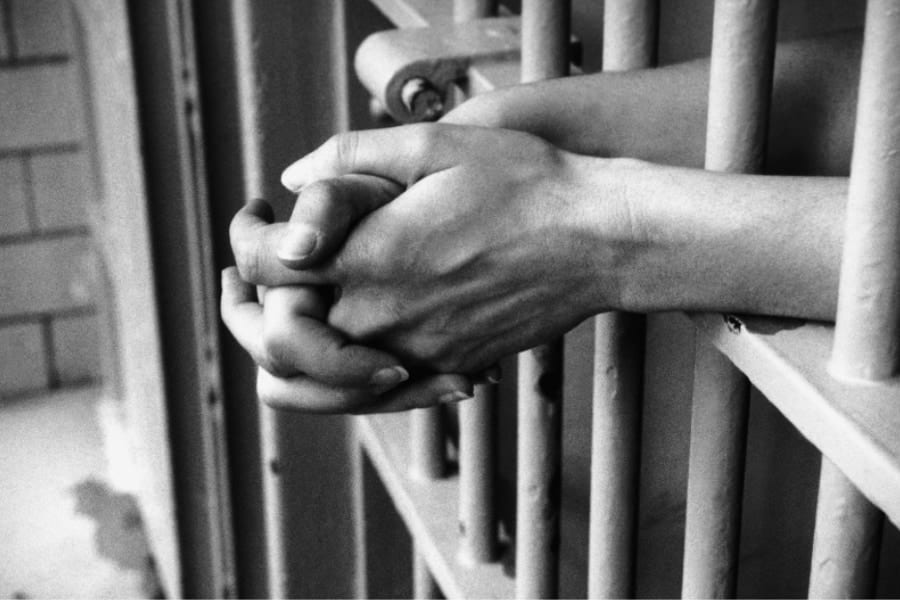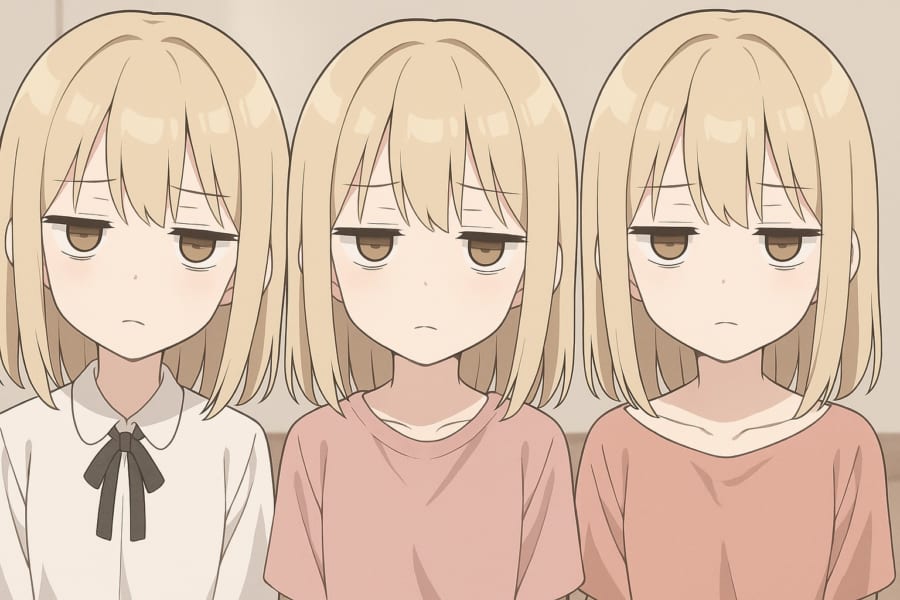「よく寝てもダメ」な理由は脳のクセにあった

「8時間寝れば万事OK」って、本当でしょうか?
世の中には、「ちゃんと8時間寝ないと身体に良くない」とか、「睡眠時間は7~8時間が理想だ」といった、いわゆる睡眠の「常識」があふれています。
もちろん、寝不足が良くないことくらいは誰でも経験で知っているでしょう。
実際、睡眠時間が短い日には「ああ、眠い…」とついぼやきがちです。
ところが、よく見てみると私たちの周りには、短い睡眠時間でもケロッとして元気な人もいます。
かと思えば、しっかりと長時間寝ているはずなのに「ぜんぜん疲れが取れない」と訴える人もいます。
ここでふと疑問に感じませんか?
「眠りって、時間だけで決まるほど単純なものじゃないのかも…?」と。
睡眠というのは予想以上に複雑なものです。
睡眠の専門家によれば、眠りには「長さ(量)」だけではなく、「質」や「深さ」、さらには「毎日の規則性」や「どの時間帯に寝ているのか」など、多くの側面があります。
これを料理に例えるなら、ただ「適量食べれば健康になる」というほど単純ではないように、「睡眠もただ推奨時間だけ寝れば良いというわけではない」のです。
つまり、「睡眠時間」と「睡眠の質や満足感」というのは必ずしもイコール(比例関係)ではないわkです。
ところが、これまでの睡眠研究は少し事情が違いました。
多くの研究では「睡眠時間と健康の関係」や「睡眠の質と心の状態の関係」といったように、特定の1つの要素に絞って、その影響を調べるという方法が主流でした。
もちろん、こうした単発的な研究でも貴重な成果が得られています。
例えば、「睡眠不足になると集中力や記憶力が低下する」とか、「睡眠の質が悪いとメンタルが不調になる可能性がある」などです。
ただ、このような研究だけを積み重ねても、睡眠という現象の「全体像」をうまく捉えることは難しいのです。
というのも、睡眠というのは本質的にさまざまな要素が絡み合って起きる「複雑な現象」だからです。
複数の要素が複雑に絡んでいるときに、要素を1つずつバラバラに調べても、本当に起きていることを理解するのは難しくなります。
これはちょうど、「料理を味わう時に、食材を別々に食べるだけではその料理の全体的な美味しさは伝わりにくい」のと同じです。
そこで今回の研究チームは発想を変えました。
彼らは睡眠に関わるさまざまな要因を、バラバラにではなく「一度にまとめて」分析する方法を使って、「人の眠り方の違い」を分かりやすく見える化しようとしたのです。
では、このように複数の要素を同時に見ることで、一体どんなことが明らかになったのでしょうか?
人間の睡眠が本当に5つものタイプに分かれるとしたら、その「眠りの個性」の正体とは一体どんなものなのでしょうか?









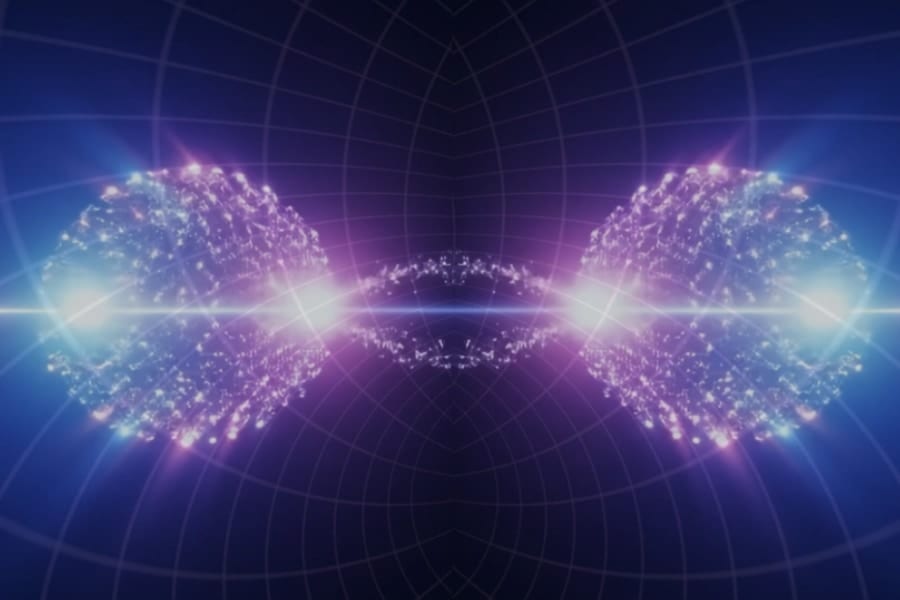

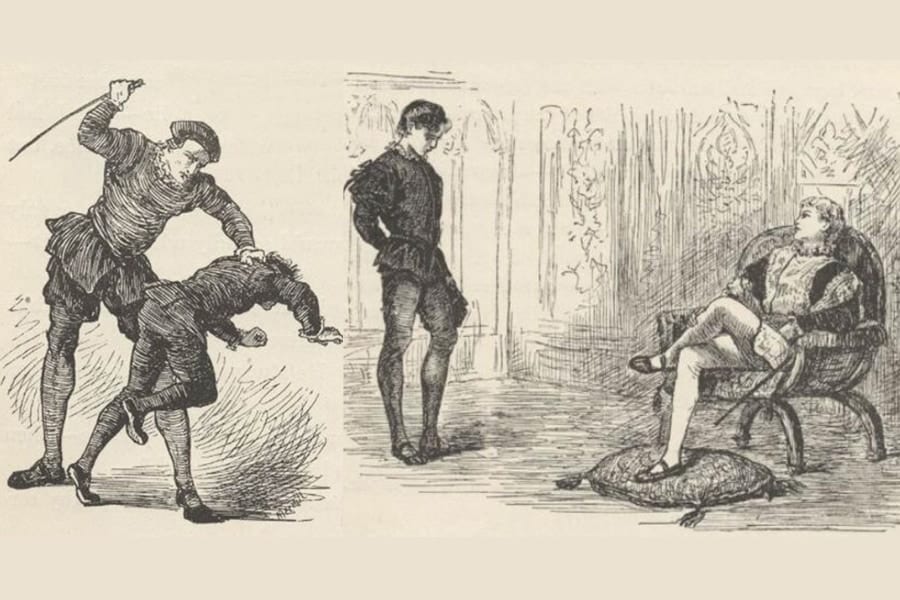
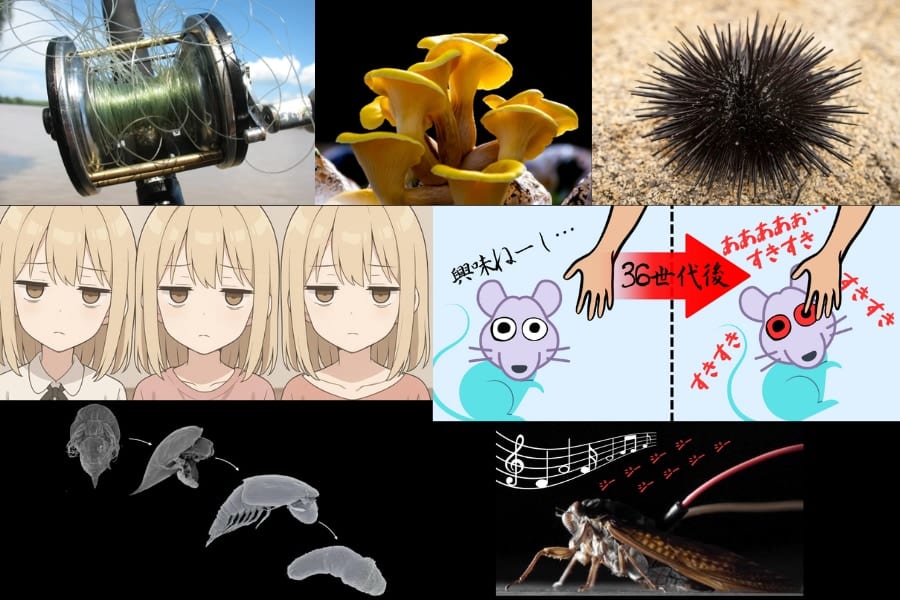




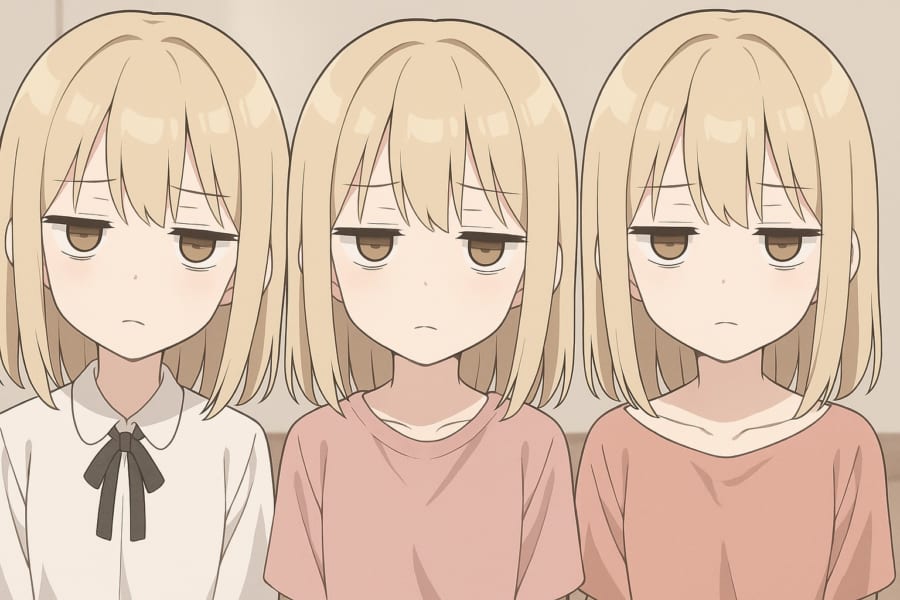














![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)