あなた専用の睡眠アドバイスが必要な理由
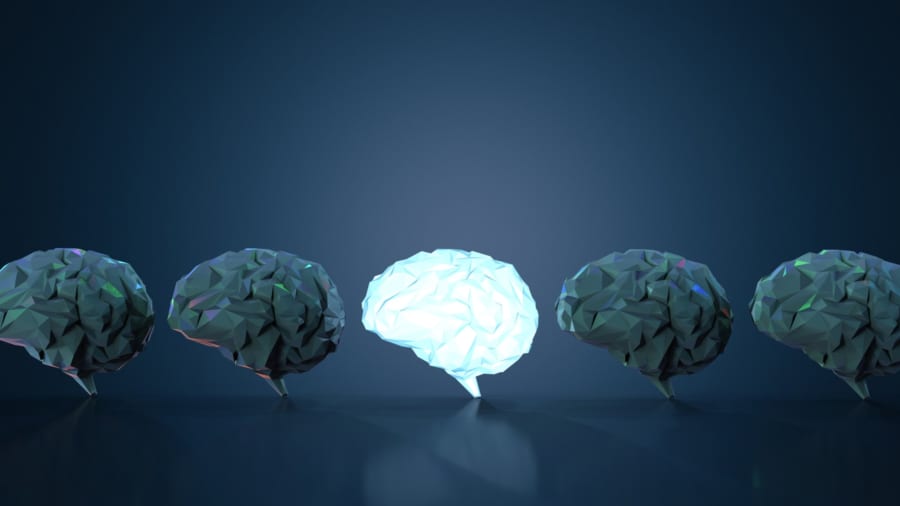
今回の研究は、睡眠をただ「良い」「悪い」で単純に二分する考え方を見直す、大きなきっかけになりました。
睡眠というと、私たちはつい「睡眠時間さえ確保できれば健康に良い」「眠りが悪ければ健康に悪影響がある」と考えがちです。
ですが、この研究は、「睡眠は単純な『時間の長さ』では測れない、多様な特徴を持っている」ことを改めて気付かせてくれたのです。
実際、今回の研究では700人以上もの若者を対象に、非常に多くのデータを同時に分析して、人間の睡眠が5つのタイプに分かれる可能性を示しました。
研究チームによると、「睡眠は単なる時間の問題だけでなく、さまざまな要素が絡み合って成り立っていることが分かりました。私たちは5つの『睡眠プロファイル』を特定しましたが、それぞれのタイプが、心や体の健康、日常生活、認知機能などと独自の結びつきを持っていることが確認されました」と述べています。
さらに、脳の活動を調べるMRIという装置でそれらの睡眠タイプを比較したところ、タイプごとに脳のネットワークにも特徴的な違いが見つかりました。
つまり、「睡眠タイプの違いは、心や身体だけでなく、脳の働き方にも関係している可能性があります」というわけです。
これは、睡眠というテーマにおいて、非常に興味深い視点の変化をもたらします。
睡眠の専門家たちがよく指摘するように、睡眠に関する指導や治療というのは、これまでどうしても一律になりがちでした。
例えば「夜11時までには寝ましょう」「毎日8時間寝ましょう」といった画一的なアドバイスが主流だったわけです。
ところが、この研究が示したように、私たちの睡眠が実際には5つものタイプに分かれるとしたら、同じアドバイスが全員に効くとは限りません。
あるタイプには効果があっても、別のタイプにはむしろ逆効果になる可能性だってあります。
研究者たちは、「睡眠のタイプごとに、より個人に合った指導や改善の方法を探ることが今後の課題です」としています。
例えば、睡眠の質が悪い人には睡眠環境を整えたり、心理的なケアを取り入れるなどの工夫を。
逆にメンタルの問題があっても睡眠が守られているレジリエンスタイプには、別のアプローチを考える必要があるかもしれません。
言ってみれば、「自分専用の睡眠改善法を見つけられるようになる可能性がある」というわけです。
とはいえ、この研究にも注意すべき限界や課題はあります。
まず、この研究はあくまで観察研究というタイプの研究です。
つまり、「睡眠が悪くなると健康やメンタルが悪化する」などという直接的な原因と結果の関係(因果関係)を証明することまではできていません。
こうした限界があるとしても、今回の研究は大きな意義を持つ発見です。
研究チームは今回の研究で使用したデータや解析コードをすべて公開しており、他の科学者たちが追試験を簡単にできるよう環境を整えています。
これによって、世界中の研究者が新たな視点で睡眠を再検討し、さらに理解を深められるようになるでしょう。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




















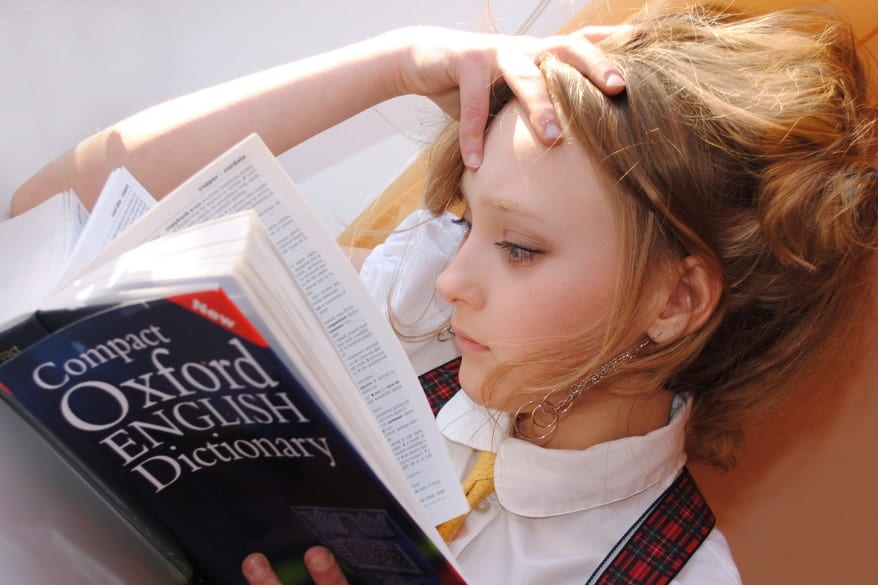

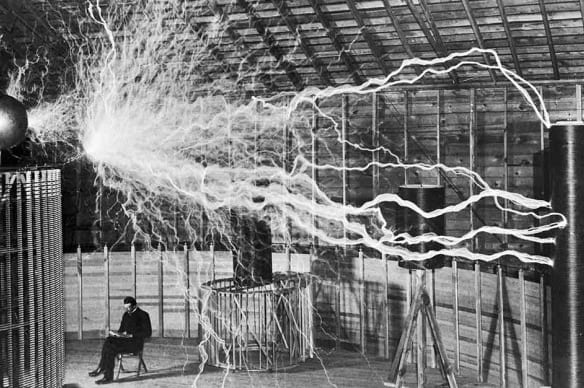






なんだこれ
だれしも5分類にわけられるっていうけど、それだとストレスもなく、睡眠も十分にとれ、健康的という人間が存在しないことになるじゃない?
良い睡眠について画一的な(8時間寝るのが良い的な)ことは言えない、可能性がある、ってだけの話やね
5タイプとかはあまり意味ないし、本当に画一的なことが言えないかも分からない、まだまだこれからの研究
>「睡眠が悪くなると健康やメンタルが悪化する」などという直接的な原因と結果の関係(因果関係)を証明することまではできていません。
って言ってるとおり別に何も証明されてないし
あくまで「画一的なことは言えないんじゃないか」ってアイディアが否定はされませんでしたってだけ(肯定もされてない)
なんだこれって感想は比較的正しい
研究(の初期段階)ってこんなもんよ
「やってみた」レベル
有望そうなら「やってみた」→「真面目に調べてみた」→「きっちり確認・検証してみた」ってどんどん研究が進んでく
有望そうでないなら・・・ポイー(他の研究に移る)
相関の強度だから”5つに分けられる”ではなくて、”5つの要素で説明される”あるいは”5つのパラメータがある”と書いた方が分かり良いと思う。ソース元だと1番目の要素が睡眠に大きく影響するらしい。体性感覚と顕著性ネットワークが主に動いてるみたいなので、体の不調感に気が向きやすいかどうかが睡眠に影響を与えやすい、みたいな。
なぜかはわからないけど5タイプで特徴づけられる結果になったということかな?
脳のメカニズムが未解明であることを解明できないこととして受け入れるような立場で
観察研究ということでしょうか
データの数値化と分類のクラスタリング手法、定性的評価と定量化の妥当性
このあたりをまず整えて、因果でない相関などから
睡眠そのものを改善する方法とともに、データ収集のための試験の在り方の標準化でしょうかね
メカニズム、因果の解明との並行だろうと思います
がしかし、かゆいところには手が届いてない感じ
たしかに、5タイプが5である妥当性なども、見解として出せるかどうかでしょうかね