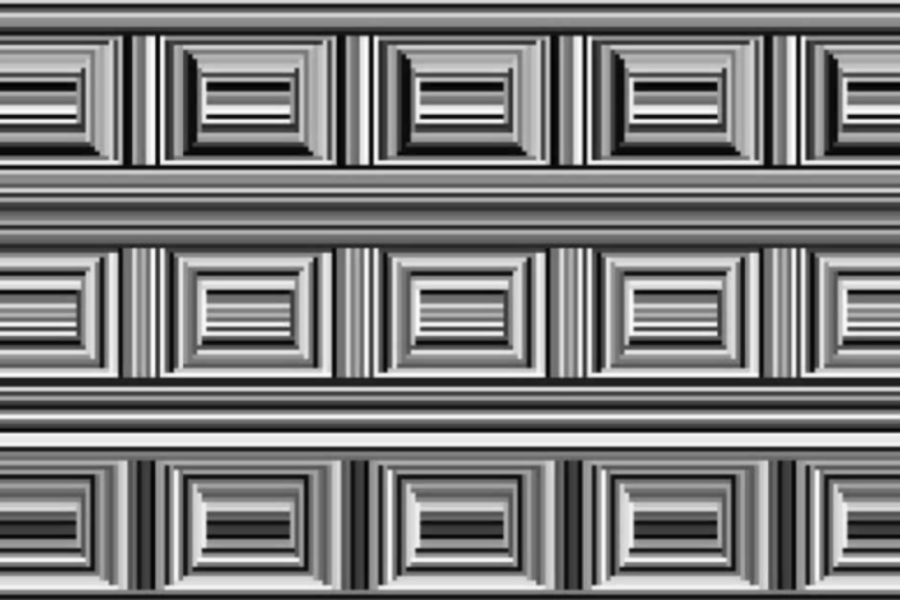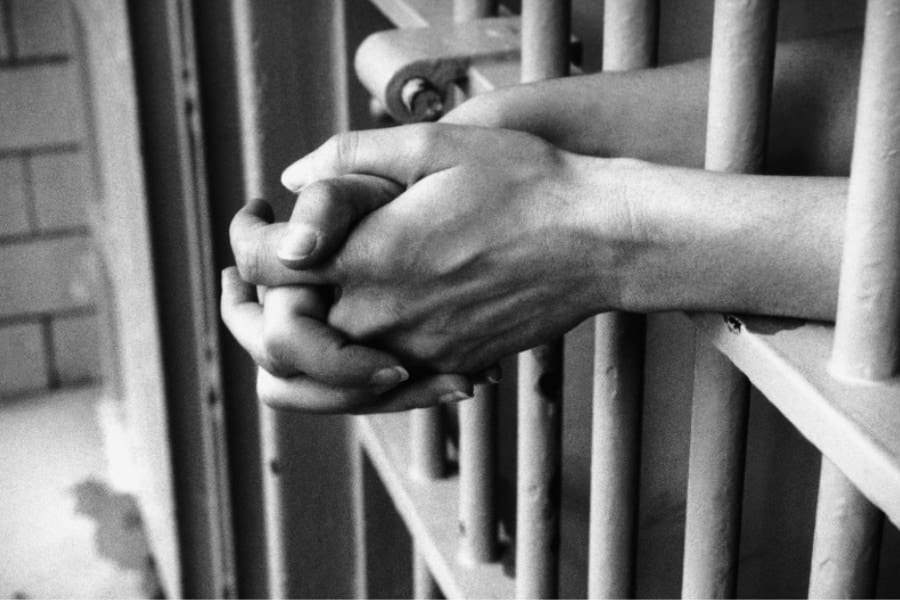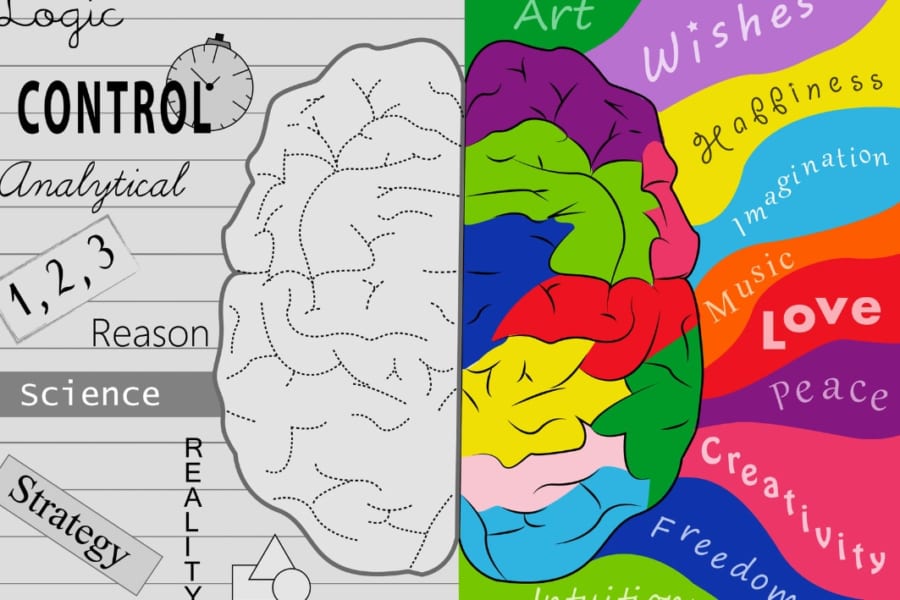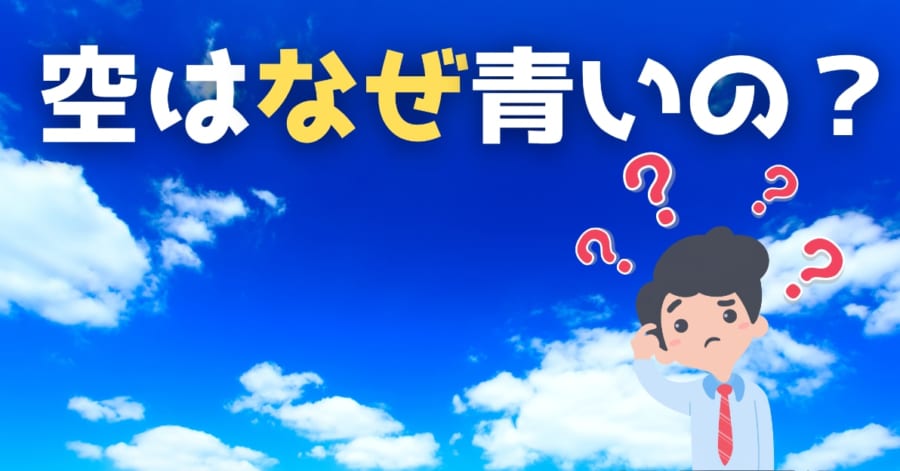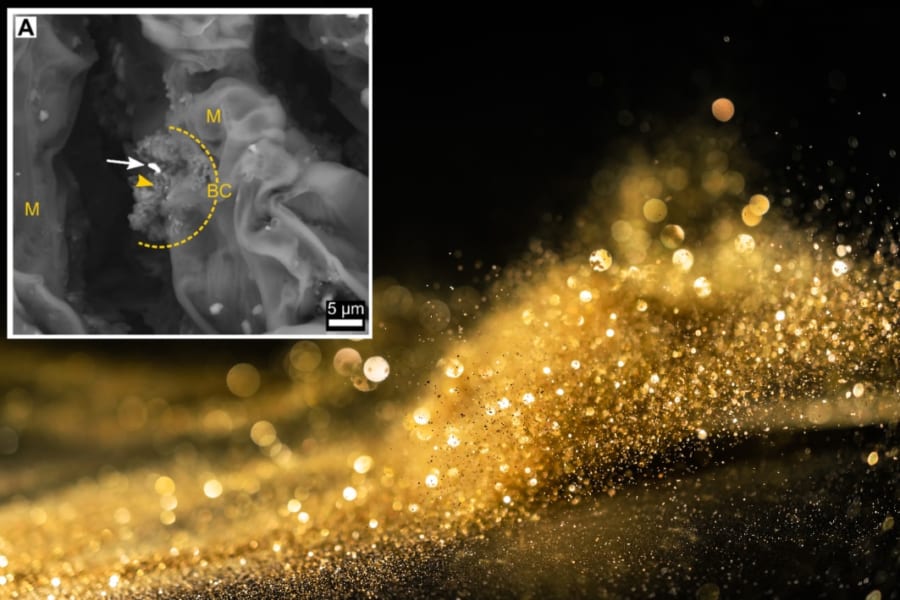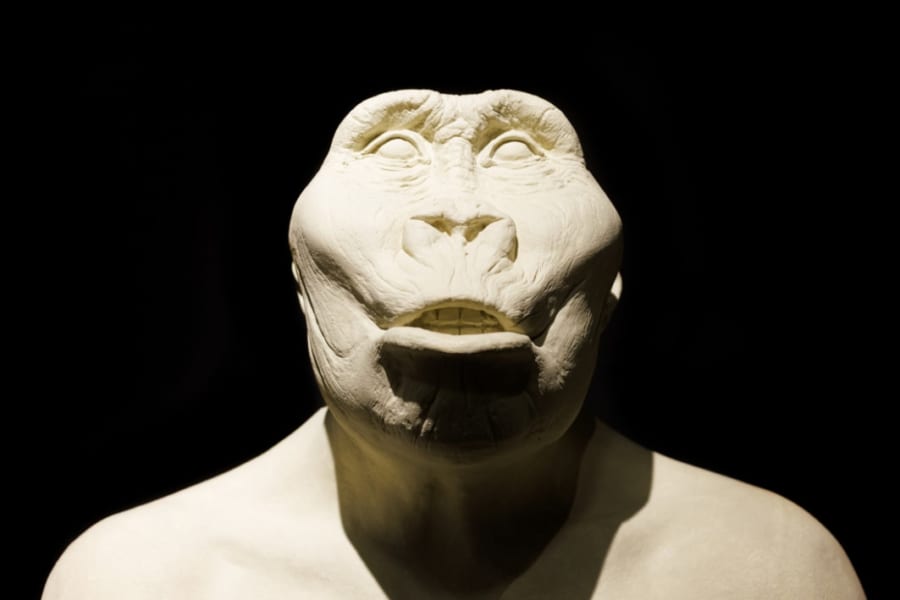「知ることを避ける心」は、いつから育つのか?
知ることで気分が沈むかもしれない情報を避けたくなる心理は、多くの大人に共通しています。
株価が下がると投資アプリを開かなくなったり、呼び出しが掛かりそうなときスマートフォンを見ないようにしたりするのも、その一例です。
こうした現象は「オストリッチ効果(Ostrich effect)」と呼ばれ、現実を避けて安心を得ようとする心の動きを指します。
ちなみにこの呼び名は「ダチョウは危険を感じると頭を砂に埋める」という伝説から来ています。もちろん実際のダチョウはそんな行動を取りませんが、古代ローマの博物学者プリニウスが、著書『博物誌』の中でそのように記していたことから有名な話になりました。
しかし、この「現実から目をそらす」心理については大人を対象にした調査ばかりであり、いつ頃から人の中に芽生えるのかははっきりしていませんでした。
そこでシカゴ大学の研究チームは、子どもを対象にした調査を行ってみることにしました。
実験ではアメリカの5〜10歳の子ども約320人を対象に実験を行っています。
実験はお話やゲームのような形式で進み、子どもたちは場面ごとに「知る」か「知らないでおく」かを自分で選びます。
たとえば「好きなキャンディが体に悪いかもしれないけれど、その情報を知りたい?」と尋ねたり、「自分より友だちのほうがごほうびを多くもらったかもしれないけれど、結果を見る?」と質問したりします。
研究チームは、情報を避ける理由として複数の動機を調べました。
具体的には、嫌な気持ちを避けたい、人に好かれたい・有能に見られたい気持ちを守りたい、自分の信じていることを壊されたくない、自分の好みを守りたい、自分の得を優先したい、といった動機です。
このように「気持ち」「評価」「信念」「好み」「得」の面から、子どもが情報を避ける選択をするかどうかを確かめました。
その結果、年齢が上がるほど情報を避けやすくなることがわかりました。
5〜6歳の子どもは、たとえ結果が悪そうでも「知りたい」と答えることが多いのに対して、7〜10歳では、「見ない」選択が増えたのです。
では、子どもたちはどんなときに「知りたい」よりも「知らないほうが安心」と感じるようになるのでしょうか。









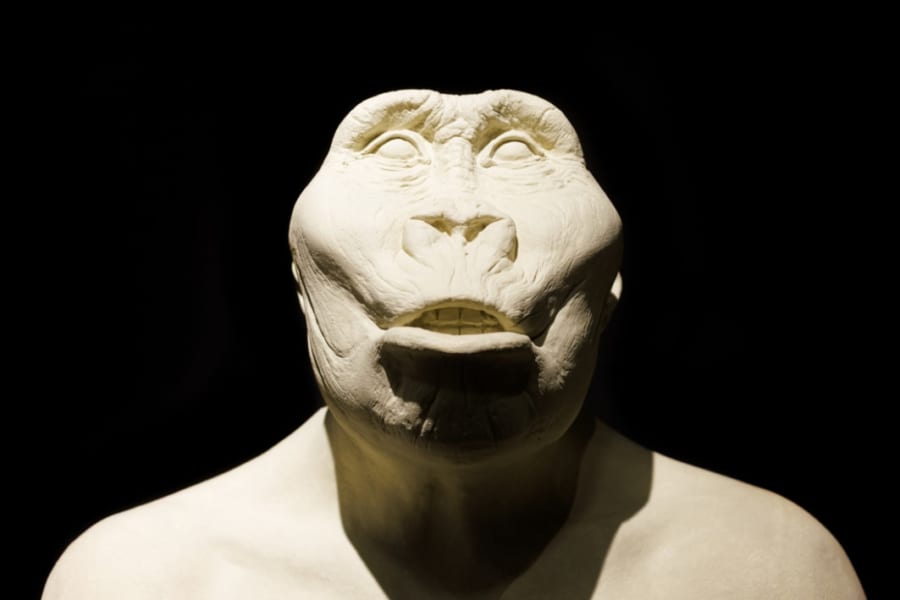







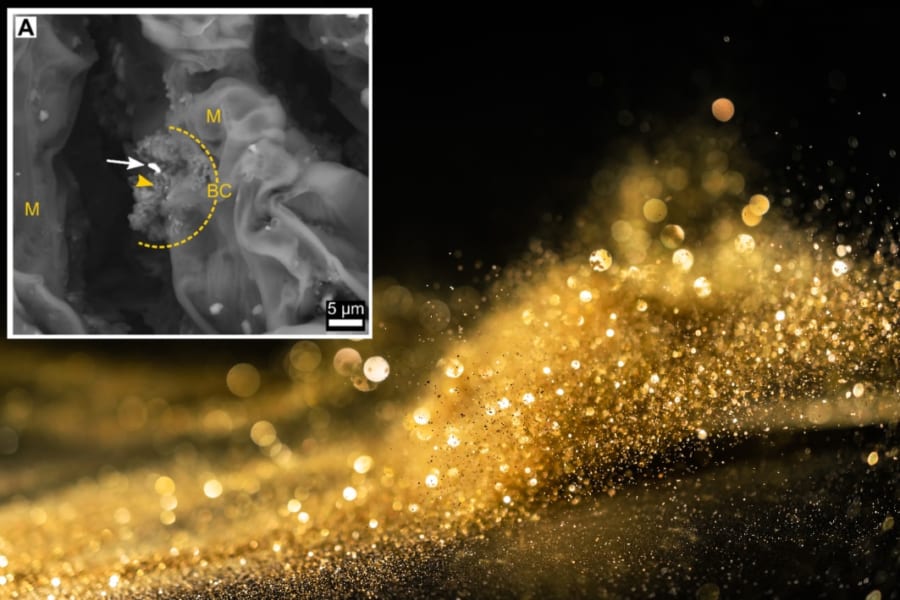


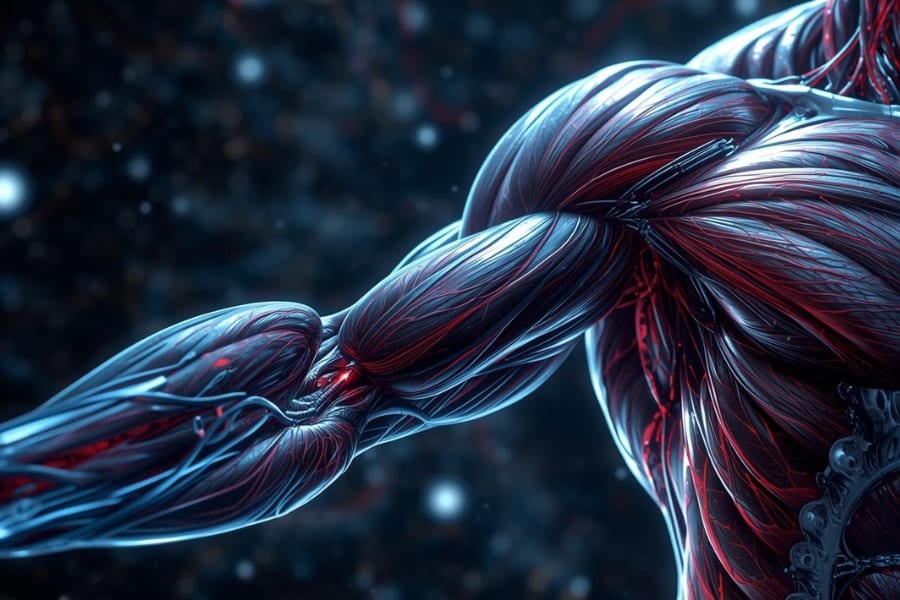




![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

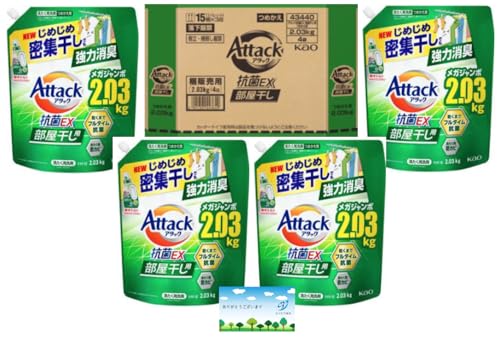
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
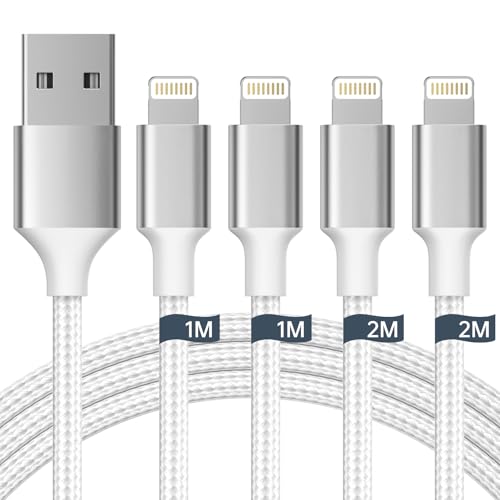
![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)