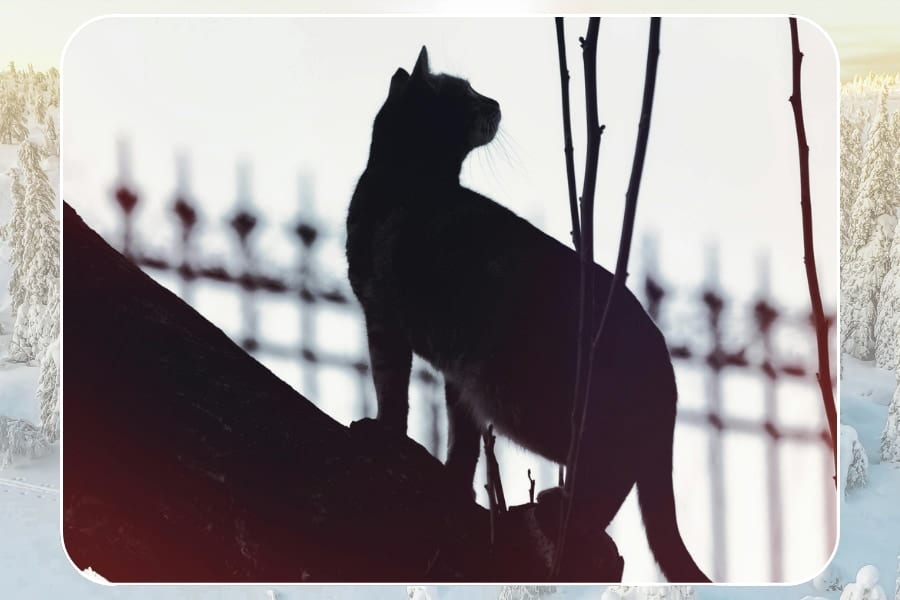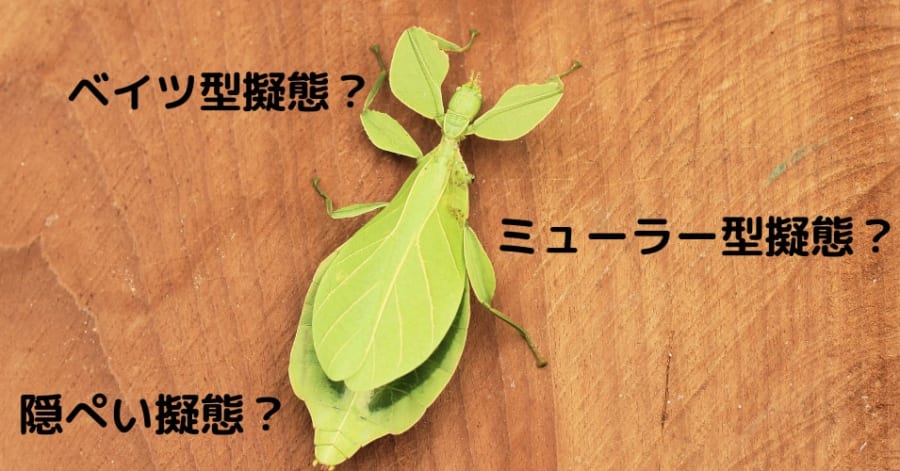死体発見のナンバーワンは?
死肉を食べ漁るスカベンジャーは、一見すると不気味に見えますが、病原菌の発生源となる死体を迅速に除去することで、生態系を守る重要な役割があります。
中でも、死肉食に特化したハゲワシは、死体の発見と消費能力に非常に長けた動物です。
また、彼らが死体めがけて上空を飛ぶことで、それを見た地上のスカベンジャーたちが死体の在り処を見つけやすくなっています。
一方で、日本の生態系にはハゲワシがいない上、機会があれば死体も食べる程度のスカベンジャーしかおらず、死肉食に特化した種がいません。
そのため、死体がどのような動物によって発見・消費され、どの程度の時間で消失するのか、よくわかっていませんでした。
そこで研究チームは、6月〜11月にかけて、日本の森林生態系にシカの死体44頭を設置し、自動撮影カメラを用いて、死体の発見〜消失までを観察。
その結果、設置した死体の88.6%が哺乳類によって最初に発見されていたことがわかりました。

また、哺乳類の中では、シカ死体の実に40.9%をタヌキが最初に発見しており、その発見時間の平均は3.3日でした。
この他にも、哺乳類ではツキノワグマやイノシシ、キツネ、テン、ハクビシンが、鳥類ではクマタカ、トビ、カラスが死肉を食べにやってきています。














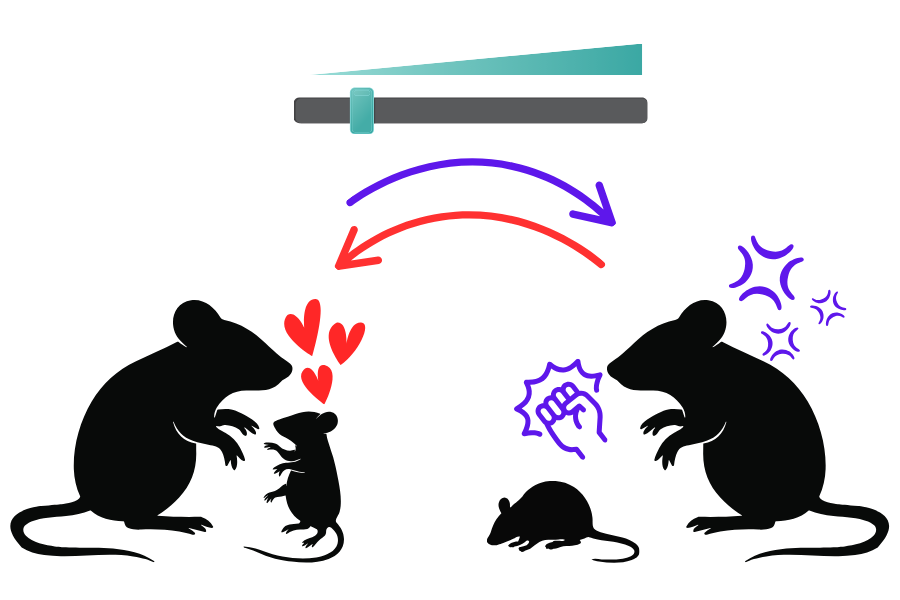


















![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)