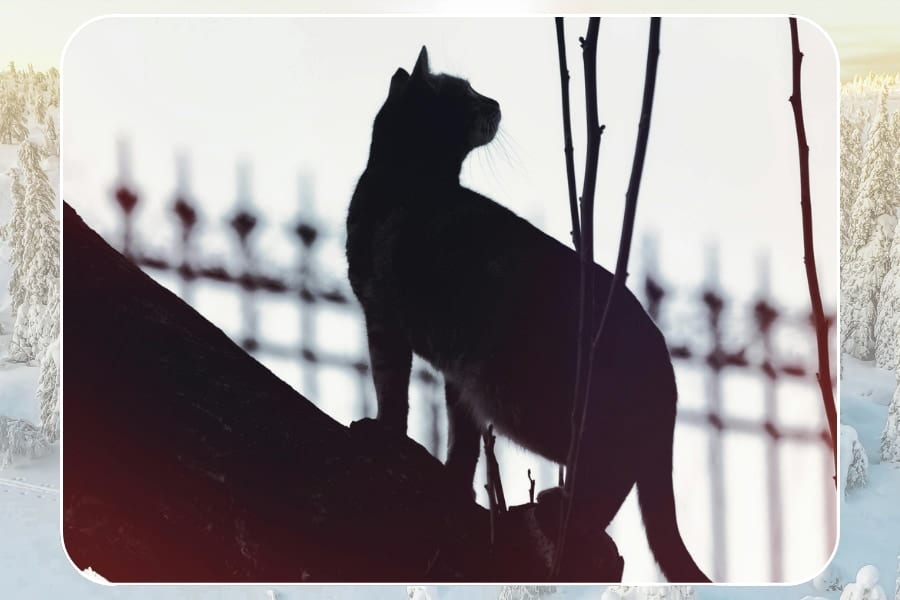夜になっても「明るい街」とそれがもたらす「体内時計のゆがみ」
現代社会では、夜になっても街灯や建物の照明が煌々と輝いており、本来であれば暗くなるはずの夜空が、まるで昼間のように明るく照らされてしまうことがあります。
これは「光害」と呼ばれる現象で、近年、都市部だけでなく郊外や自然保護区にまで影響を及ぼしている深刻な環境問題です。
地球上の多くの生物は、太陽の昇り沈みに基づいた「概日リズム(サーカディアンリズム)」を頼りに活動しています。
光と闇の切り替わりが、起床や休息、食事や繁殖などのタイミングを決定づけており、これは人間を含むほぼすべての生命体に共通するメカニズムです。
しかし人工の光が夜を侵食すると、この自然なリズムが狂ってしまいます。
例えば、日没後も周囲が明るいままだと、鳥たちの体内時計は「もう朝だ」と錯覚してしまい、通常よりも早く活動を始めたり、夜遅くまで活動を続けてしまう可能性があるのです。
今回の研究では、こうした光害が鳥類の行動にどのような影響を与えているのかを明らかにするために、科学者たちは世界中の鳥たちのさえずりパターンに注目しました。
解析に使われたのは「BirdWeather」という科学プロジェクトのデータです。
このプロジェクトでは、世界中のバードウォッチャーが自宅の庭などに生態音を録音できる装置を設置し、その音声データが中央のデータベースに送信されます。
研究チームはこの膨大なデータのうち、583種の鳥において、さえずり開始(朝)に関する260万件以上、さえずり終了(夕方)に関する180万件以上のデータを分析対象とし、各地点の光害レベルと照合しました。
その上で、鳥の行動にどれだけ影響があるのか、さらにその傾向が種によってどう違うのかを詳細に調査しました。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)