ロボットの「自己消滅」はどんなシーンで使える?
従来のハードロボットに比べ、柔軟な素材を使うソフトロボットは、生物のように柔らかい動きを再現できることで大いに注目されています。
その柔軟性や弾性により、狭い空間にするりと入り込んだり、壊れやすい物を優しくつかんだりと、高度で複雑な動きが可能です。
近年、ソフトロボットの機能は急速に進化しており、生物のあらゆる動きを模倣できるまでになりました。
しかし、その中で再現できていなかったのが「死(=消滅)」です。
生物のからだは有機物からなるため、寿命を終えると自然に分解が始まりますが、ソフトロボットは分解されにくい物質を使っているため、自己消滅の再現はどうしても困難でした。
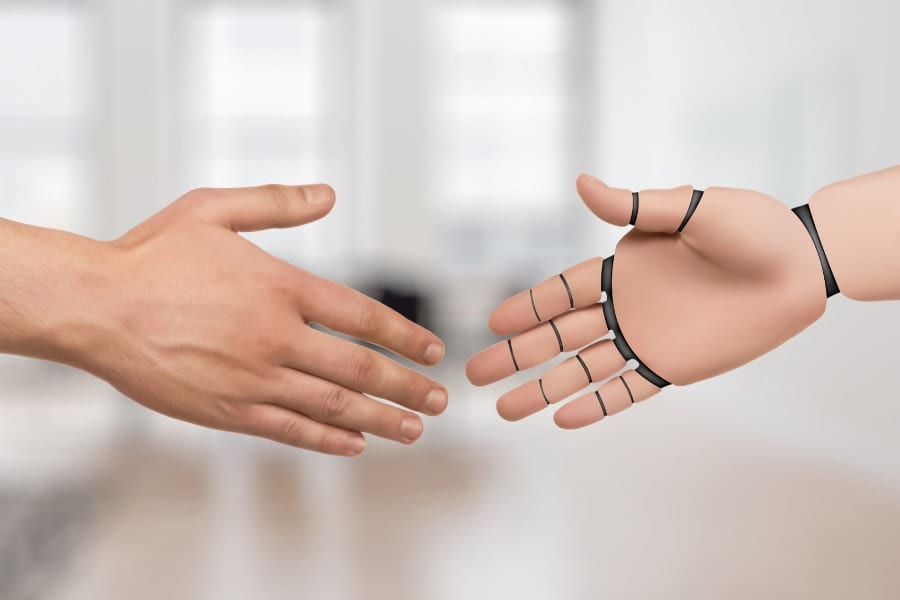
その一方でロボット工学者たちは、寿命や任務を終えたロボットが自己消滅するというアイデアに強く惹かれています。
例えば、軍事作戦の偵察・監視ミッションにおいて、重要なデータが敵の手に落ちるのを防ぐために、回復不能な形で自己消滅できる機能は大いに役立つはずです。
トム・クルーズ主演の映画『ミッション:インポッシブル』シリーズでは毎回、極秘ミッションを伝えるテープレコーダーが再生された5秒後に自動的に消滅するシーンが必ず出てきますね。
イメージとしては、あれと同じような機能をソフトロボットに持たせるようなものでしょう。
また深海や放射能の汚染エリアなど、ロボットの退避や回収が困難な場所で利用された際も、任務を終えたロボットが廃棄後に分解され自然のサイクルへ還るという死のプロセスをロボットに与えたいという希望が、開発者たちにはあるようです。
しかし、この機能の実現には乗り越えるべき課題が多く、研究チームもその方法の確立に約2年を費やしました。
では、チームは一体どのようにしてソフトロボットを自己消滅させたのでしょうか?






























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

























