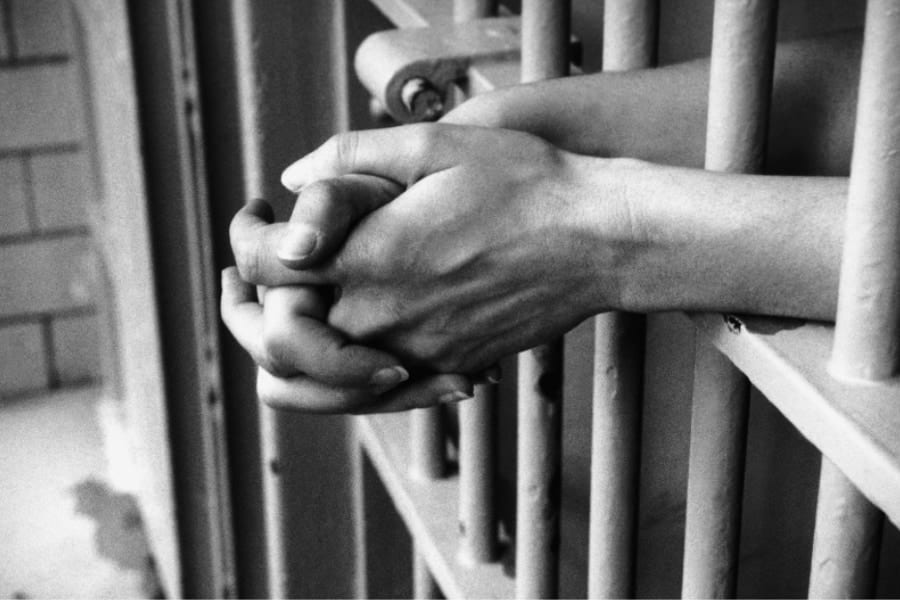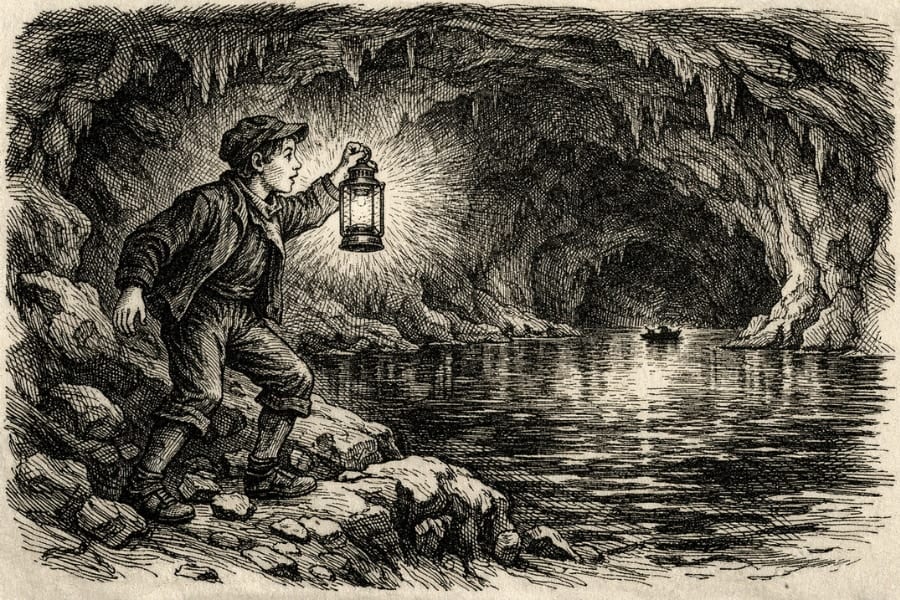侵略的外来種「ブルーギル」

ブルーギル(学名:Lepomis macrochirus)は、北アメリカ大陸原産の淡水魚であり、世界的に最も分布拡大している侵略的外来種の一種です。
日本でも在来種に深刻な影響を与えており、特定外来生物として輸入、放出、飼養などが規制されています。
必要に応じて、国や自治体が駆除を行うこともあるようです。
またブルーギルと言えば、初心者でも簡単に釣ることのできる魚として有名であり、ルアー釣りやエサ釣りを楽しんだことのある人もいるはずです。
ただし、侵略的外来種であることから、釣り上げた際はリリース(再放流)しないことが推奨されています。

実際、琵琶湖などではリリースが禁止されており、付近には「外来魚回収ボックス・いけす」が設置されているのだとか。
侵略的外来種の駆除という観点で、釣りも「個人が行える外来種駆除である」という考え方もあるようです。
とはいえ、こうした規制や取り組みがあるにもかかわらず、ブルーギルの存在は、依然として、日本の在来種にとって脅威となっています。
では、日本だけでなく世界中の淡水生態系を劣化させているブルーギルが、そこまで強い定着力を持っているのはどうしてでしょうか?
ピーターソン氏ら研究チームは、2022年の夏に、長野県北部の野尻湖でブルーギルの繁殖生態を調査しました。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)