マメはトウモロコシの悲鳴を聞いている
研究チームは、実験室で収集したトウモロコシの揮発性物質をマメに与えると、マメが自分の防御を増強することを発見しました。
この反応は、実験室だけでなく、実際の畑でも同様でした。
具体的には、トウモロコシの揮発性物質を感知したマメが、自分の「花外蜜腺」の働きを増大させると分かりました。

花外蜜腺とは、花以外にある甘い蜜を出す腺のことで、この蜜でアリなどを誘引し、他の昆虫による食害を防ぐ役割を持っています。
マメの場合は、葉の下に小さな花外蜜腺を持っており、これで自分を守る兵士(アリやスズメバチ)を引き寄せることができます。
そして、トウモロコシの揮発性物質を感知したマメは、通常よりも蜜の量と糖分濃度を増すことで、一層多くの兵士を引き寄せます。
しかも引き寄せられたアリやスズメバチは、マメだけでなくトウモロコシを襲う害虫を食べることで、両方を守ります。
ちなみに、マメの花外蜜腺は、トウモロコシの悲鳴で引き寄せられる「寄生バチ」にも良い影響を及ぼすことも分かっています。
栄養豊富な蜜を食べた寄生バチは、通常の2倍近く長生きし、より多くの害虫たちを駆除していたのです。
今回の実験では、トウモロコシの悲鳴を聞いたマメが、いつも以上に多くの兵士を雇い、自分とトウモロコシを守らせると分かりました。
これが伝統農法「ミルパ」のメリットの1つであることを考えると、この農法の奥深さは計り知れません。
研究チームは、全ての植物の組み合わせが、同じようなメリットを産むわけでもないことも指摘しており、植物と昆虫にはまだまだ複雑な関係が隠されているようです。
そして彼らは、こうした謎の解明が「化学農薬の使用削減に役立つかもしれない」と述べています。














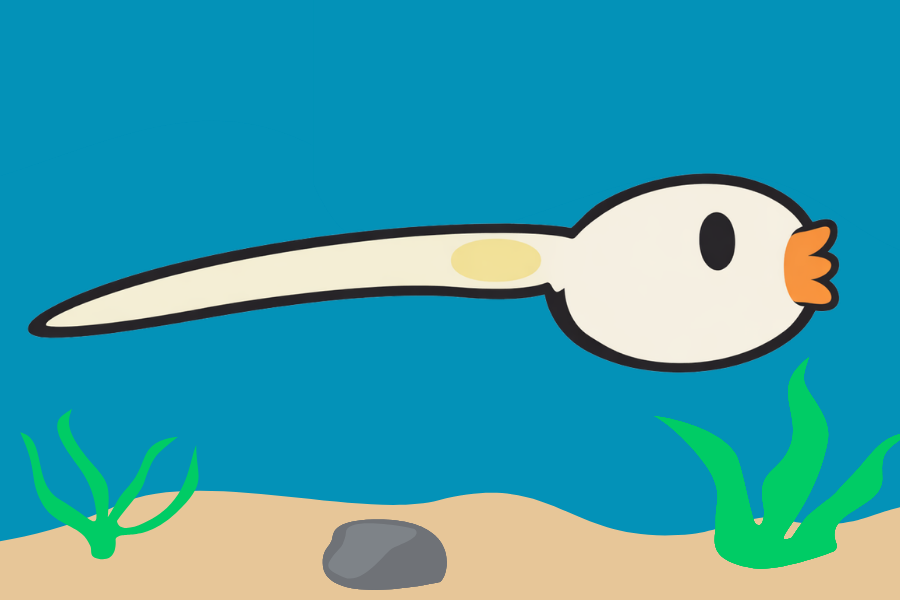

















![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)


















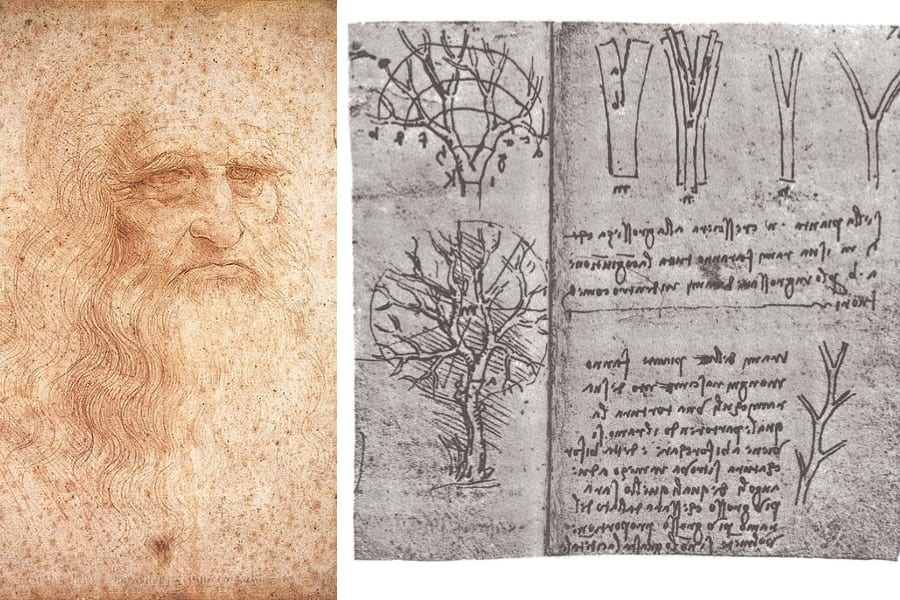










カボチャさんは豆さんとトウモロコシさんの会話には参加しないの?
意外と仲良しなのか…。
ひょっとして他のたいていの生き物から嫌われてるのって人間だけ…。
なんかキャベツみたいな話だな
トウモロコシ、カボチャ、マメって言われた時「マメ」だけ総称っぽい響きなんだけど何マメでも同じなんだろうか?
ミルパ農法してる地域のマメだけがそう進化したのかな?
CO2を集めるまでのコストに比べて、ギ酸を生成するプロセスが高コスト低収率すぎる夢物語のように見えます。エネルギー勾配に逆らって反応させるために炭酸ガスを超高圧にすれば設備費がかかりますし、金属触媒は高価です。ましてや光触媒は、維持が安定維持が大変で収率が悪すぎます。
地球温暖化にこだわらなければ、千葉県のヨウ素生産用の井戸から、副産物の二酸化炭素とメタン・水素を分離して、ガス燃焼で得た熱を利用してプラントを回す方が合理的に見えます。
上の投稿、あげる板を誤りました。
反省して、別のコメントを載せます。
記事で紹介された伝統技術は、近代的に機械化された大規模農場では無理としても、ビニールハウスや(手でもいで収穫する)高付加価値野菜の畑で利用できないかしら。
今どきの有機野菜を食べる意識高い系の方々は、「農薬は嫌だけど虫食いもいや」なので目の細かいネットで覆った圃場での収穫物を食べています。ミルパ的農法を利用したら、送粉昆虫を妨げず、1つの圃場で長い期間収穫でき、水管理が楽で、すべて収穫後にすき込めば肥料になるのはよさげ・・・と書いていて思いなおしました。
自分が虫害にあってなくとも、混作している作物の虫害によるアレロパシーで実が固くなったり渋くなることもありそうなので、舌の肥えた意識高い系には向かない農法かも