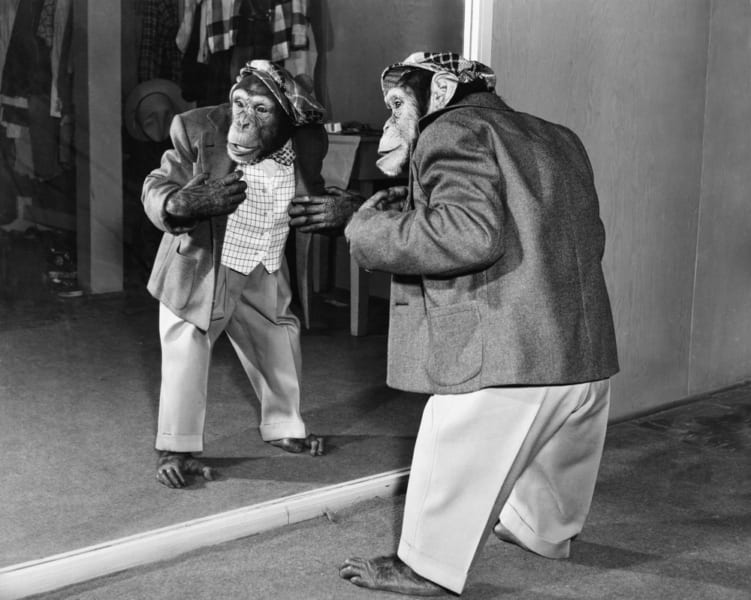米を蒸し、煮ていた古代日本人

縄文時代の終わり頃、日本列島には稲作が伝わり、その後の2500年にわたり、日本人は様々な調理法で米を楽しんできました。
稲作が広まるにつれ、米の調理法も多様化していったのです。
その中でも古代日本で主流だったのが、「飯(いい)」と「粥(かゆ)」の2つの調理法です。
「飯(いい)」は蒸した米を指します。
その中でも蒸した米の飯は強飯(こわいい)といい、食感はかなり硬かったです。
なお強飯は古墳時代からありました。
一方「粥(かゆ)」は煮た米のことを指しています。
現在お粥と言われている料理は弥生時代からあり、当時は「姫粥(ひめかゆ)」という名前でした。
また米は他にも様々な方法で調理されていきました。
奈良時代に入ると、強飯を乾燥させた乾飯(ほしいい)が作られ、携帯しやすい行動食として広まりました。
この乾飯はそのまま食べることもありましたが、基本的には水やお湯で戻して食べるのが一般的でした。
平安時代には、飯に水をかけた「水飯(すいはん)」が誕生し、これは現在のお茶漬けの原型とされています。
なお飯に水をかけるのは夏の間だけであり、冬は水飯の代わりに飯にお湯をかけた「湯漬け(ゆづけ)」が食べられていました。
また同時期に強飯を握った「屯食(とんじき)」も生まれ、それは現在のおにぎりの原型でもあります。
さらに米に野菜などを混ぜた「かて飯」や野菜を入れた粥の「味噌水(みそうず)」などもこの時代からあり、現在の混ぜご飯や雑炊に近いものはかなり古い時代からあったことが伺えます。
このように日本では米の調理に「蒸す」や「煮る」などの方法を取っており、これらを実現するために甑(こしき)といった道具が使われていました。

特に甑は、穴のあいた蒸し器として使われ竈(かまど)の上で蒸し炊きを行うのが一般的であったのです。
この甑が古墳時代頃から普及し、炊飯具の一つとして古代日本の生活に深く根付いていました
万葉集においても甑が歌に詠まれており、「貧窮問答歌」では、甑に蜘蛛の巣が張るほど飯を炊いていない、という一節がありました。
この「炊く(かしく)」は、米を蒸すという意味も含んでおり、当時の食文化が窺えます。
こうして、道具や技術の進化に伴い、米の食べ方も徐々に変わり、私たちが今日口にする「めし」に至るまで、長い歴史の過程を経てきたのです。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)