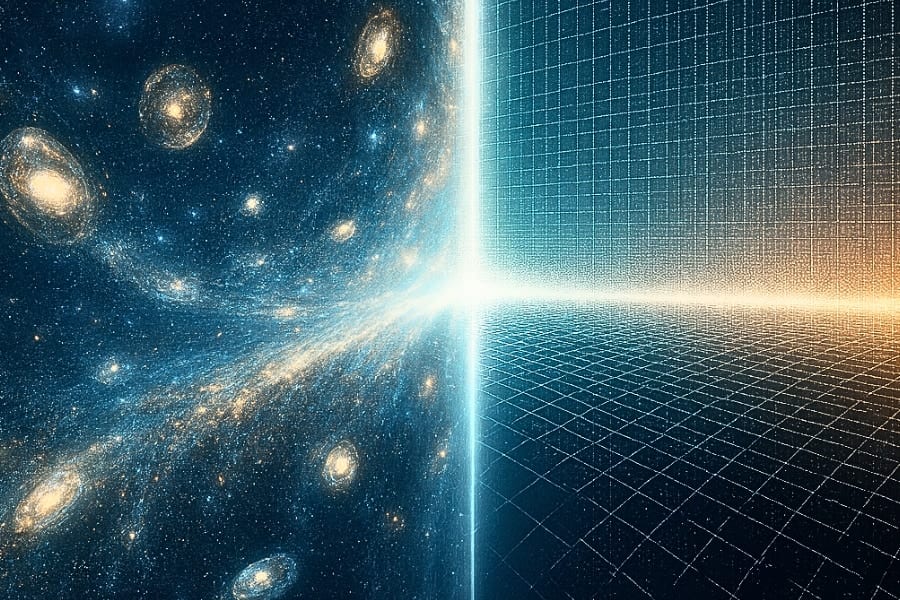調理器具の発展を待たなければならなかった、現代のメシ

このように古代の日本人は様々な方法で米を調理していましたが、現在のような方法での調理はいつ頃から行われていたのでしょうか?
たとえば「姫飯(ひめいい)」といったものは、今のごはんに近いものであり、その調理法には「炊き干し法」や「湯取り法」が用いられていたといいます。
炊き干し法では、米に水を加えて煮、その水がすべて吸収されるまで火にかけるというものです。
湯取り法では、一度米を煮立てて水を捨て、さらに蒸し煮にするものです。
この技術は弥生時代の甕(かめ)や壺から見つかった吹きこぼれ痕などの遺跡の証拠からも示されており、弥生時代から現代と同じような米を調理する手法が行われていたと主張する人もいます。
これには反対意見もあり、「炊き出し法や湯取り法で米を炊いていた跡ではなく、粥を作ろうとして失敗した跡なのではないか」と指摘されています。弥生時代の人々が失敗作の粥として結果的に現在の私たちと同じような調理方法で作られた米を食べたことはあっても、意図して現代の私たちと同じような調理方法で作られた米を食べたことはないというのです。
しかしいずれにせよ弥生時代の土器は表面が弱く、一度焦げると二度と使えなくなるということもあったので、意図的に行った者がいたとしてもこの調理方法が主流になることはなかったようです。
やがて平安時代になると、貴族の間では姫飯も日常的に食べられるようになったものの、それ以外の人々が日常的に現代のような調理方法で米を食べるようになるのは、陶器で作られた丈夫な調理器具が普及する中世を待たなければなりませんでした。
さて、日本には炊飯の心得を歌にした伝承があります。
「はじめチョロチョロ、中パッパ、ブツブツいう頃火をひいて…」という、誰もが一度は耳にしたことがあるこの歌は、実は科学的な炊飯のコツそのものなのです。
はじめの「チョロチョロ」とは、沸騰までの弱火を指し、米粒が外から内へ均等に水を吸うために必要な工程。
そして「中パッパ」で沸騰後の強火は、米に水を十分に行き渡らせるためのものです。
その後、「火をひいて」は、弱火でじっくりと米を蒸し上げるための指示で、最後に火を止めたあとも、蓋を開けないで蒸らすことが大切です。
「赤子泣いてもフタ取るな」とは、蒸らし中に蓋を開けると熱が逃げ、米がうまく仕上がらないからだといいます。
このような炊飯法は、1955年に登場した自動炊飯器にも受け継がれており、今や世界中で珍しがられるほどの技術革新となります。日本の炊飯文化は、こうして昔から積み重ねられた知恵の結晶といえるでしょう。


















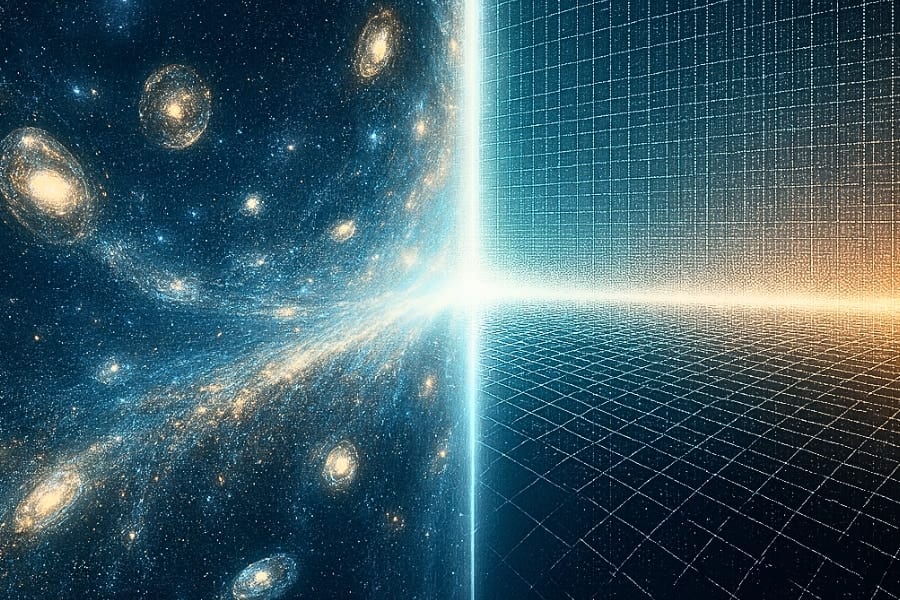


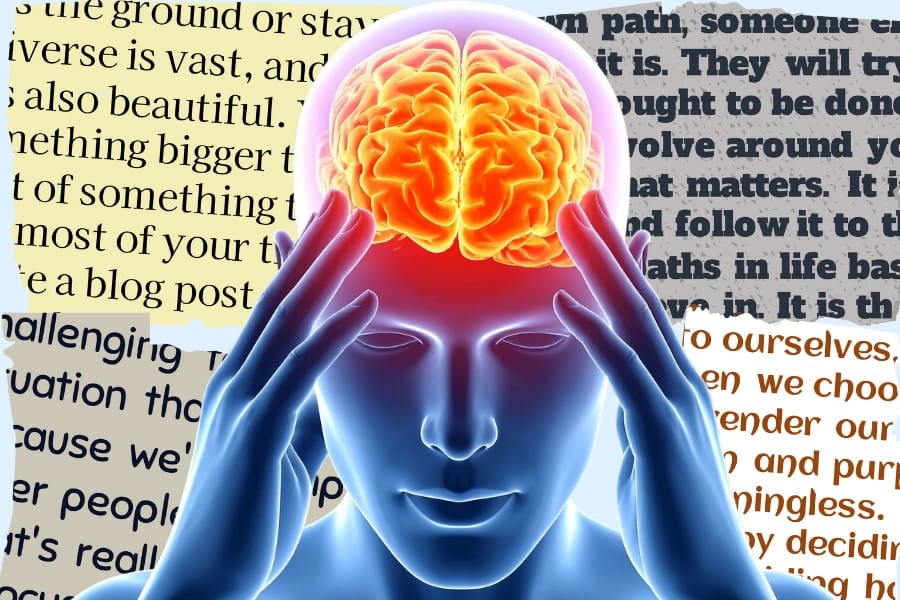






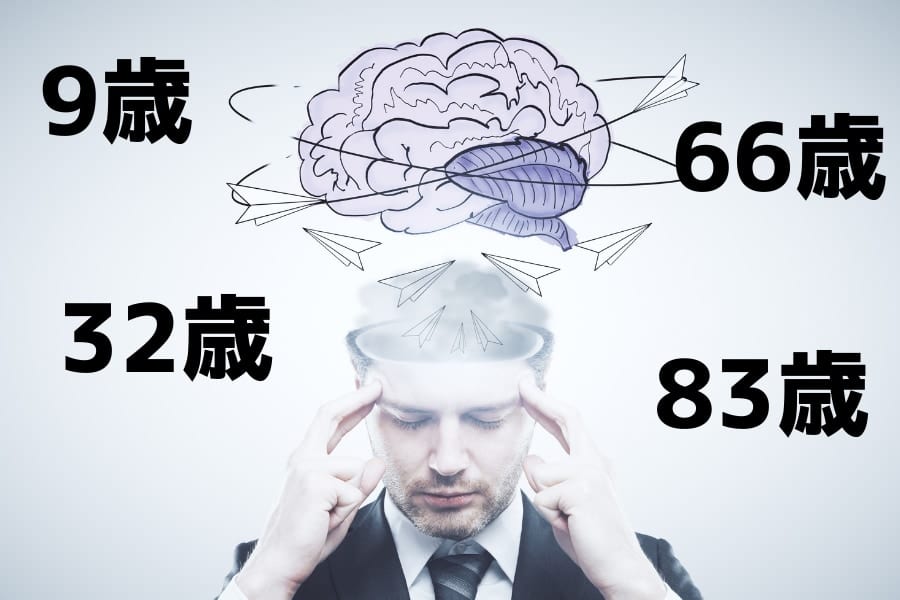


![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)