ウイルスの自然振動周波数は「指紋」になる
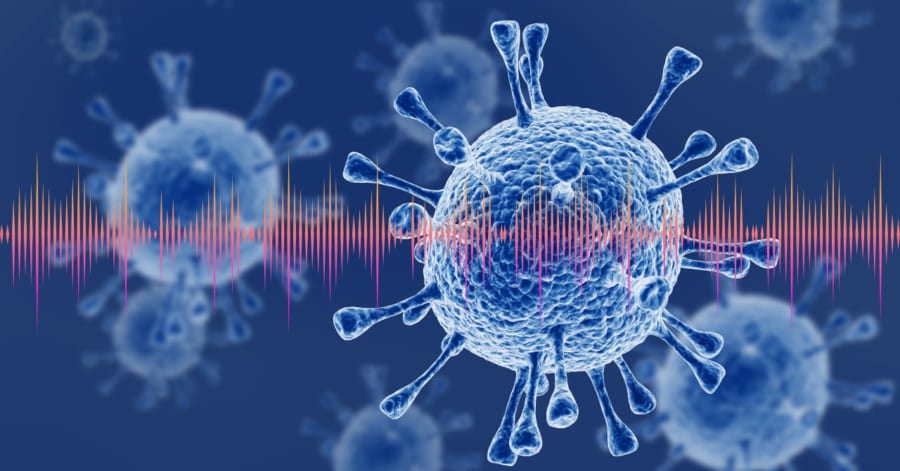
ウイルスはわずか数十ナノメートル(1ナノメートル=1ミリメートルの100万分の1)という極小の存在です。
そのため、ふつうの光学顕微鏡でははっきりと観察できず、電子顕微鏡など特殊な装置が必要でした。
また、ウイルスを識別したり、その活動状態を調べたりするには、遺伝子解析を行ったり、蛍光物質で染めるなどのラベル(標識)が必要なことが多く、実験の手間やサンプルの変化などの問題点もありました。
さらに、これまではウイルス全体の平均的な性質(例えば溶液に溶けた大量のウイルス粒子をまとめて調べる)を測ることが中心で、「1つのウイルス粒子がいま、どう動いているか?」という生々しい様子を捉えることは難しかったのです。
しかしウイルスは、決して静止した“ただの球”ではありません。
周りの環境との相互作用や、カプシド(殻)や内部の構造が変化するときに、“微弱な振動”を起こします。
この振動は私たちの耳には聞こえませんが、周波数(音の高さ)や持続時間(どのくらい揺れが続くか)が、ウイルスの形や硬さ、表面タンパク質との結合状態などを映し出す「指紋」のようなものになっています。
もし、この「ウイルスが出す音」を直接測定できれば、ラベルなしで1粒ごとの性質を見分けられたり、活動状態の変化をリアルタイムで追えたりするのです。
なぜこれが重要かというと、感染症の原因となるウイルスを素早く識別する手段や、新種のウイルスをいち早くキャッチして研究する方法に大きく貢献できるからです。
また、ウイルスが細胞に侵入して増殖する際のメカニズムも、振動の変化として観察できるようになる可能性があります。
これは基礎研究のレベルだけでなく、病院や検査の現場においても、感染症対策や早期診断につながる画期的なステップとなるでしょう。
そこで今回ミシガン州立大学の研究チームは、ウイルスが持つ“超高周波の音”を直接捉える実験装置を開発し、微小なウイルス粒子にレーザー光を当てて振動を解析しました。
具体的には、まず極めて短い時間だけ光を発する「超短パルスレーザー」を使います。
1回目のパルス(ポンプ光)をウイルスに照射すると、ウイルスの内部構造や殻、表面のタンパク質が軽く揺さぶられ、超高周波の“音”が生まれます。
続いて、ほぼ同時に2回目のパルス(プローブ光)を当てて、ウイルスがどう振動しているかを光の散乱パターンから測定します。
これを何度も繰り返し、わずかな時間差で観察することで、振動の変化を細かく追跡できる仕組みです。
研究チームはこれを「BioSonicsスペクトロスコピー」と名付けました。
この測定データを解析すると、ウイルスが出している音の“周波数”や“減衰のしやすさ(揺れの持続時間)”などがわかります。
結果として、それぞれのウイルスは周波数のパターンが少しずつ異なる“指紋”のような特徴を持っていることが判明しました。
たとえば、ある種類のウイルスでは20ギガヘルツ前後という超高周波で振動し、それが環境の変化やウイルス自身の状態変化(カプシドが弱ってくる、膜が変形するなど)に応じてわずかにズレたり、弱まったりする様子も捉えられました。
さらに、1つのウイルス粒子を時間をかけて連続的に観察することで、殻が壊れ始める“寸前”の変化まで見逃さずに追跡できるという点も大きな成果のひとつです。
つまり「どのウイルスかを見分ける」だけでなく、「今そのウイルスがどんな状態なのか」を非接触でモニターできる技術が生まれたといえます。
従来の方法では、ウイルス粒子を単独で観察しようとすると蛍光色素でラベルを付けるなど特別な手間が必要でしたが、BioSonicsスペクトロスコピーを使えば、ウイルスそのものが自然に発する“音”をキャッチするだけで済みます。
これにより、感染症の早期検出や、ウイルスが細胞を攻撃する仕組みをより細かく調べるうえで、将来にわたって大きな進歩が期待されています。




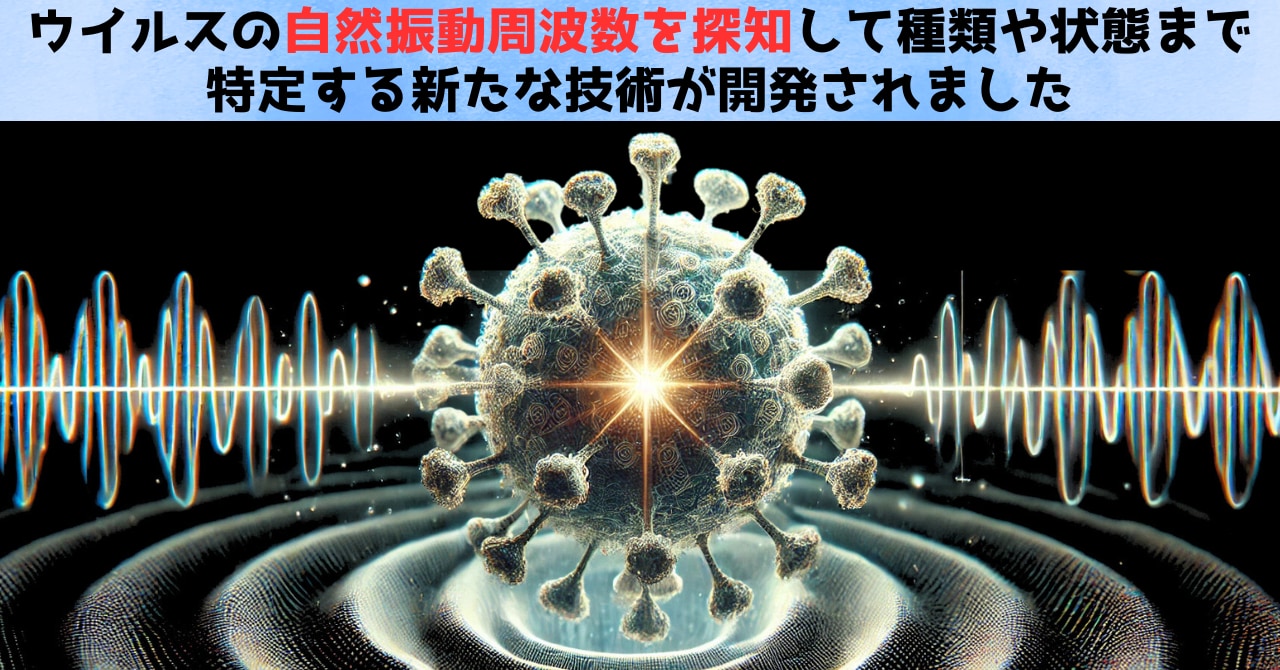











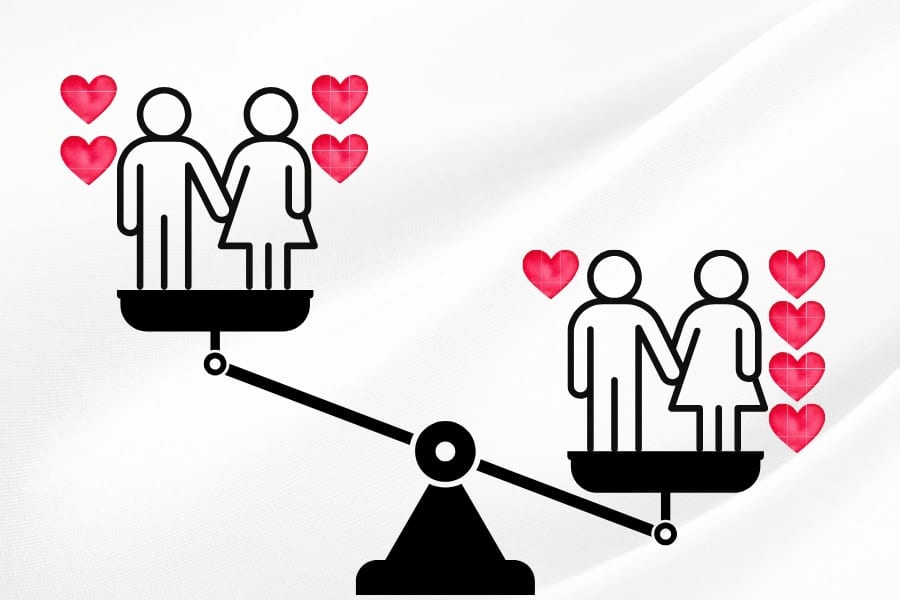












![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























