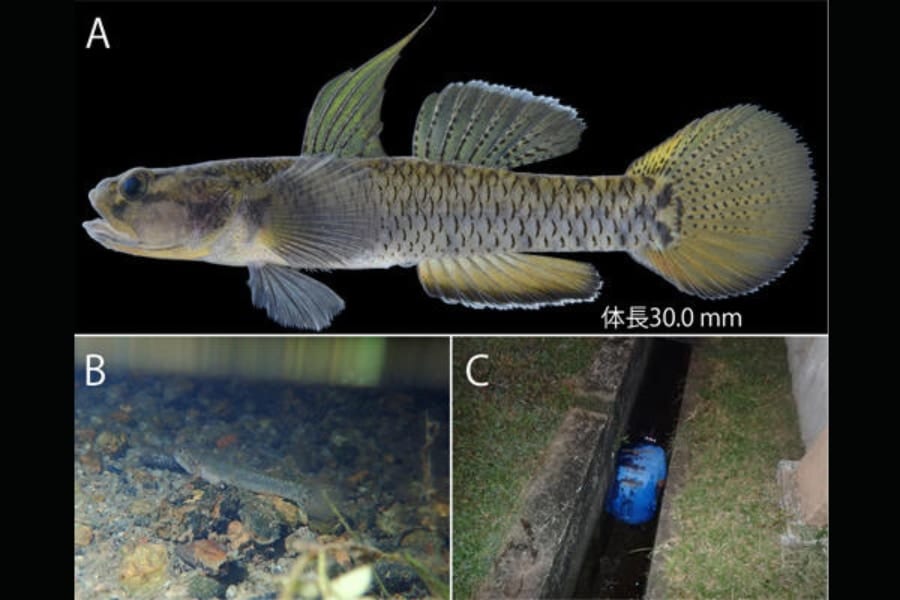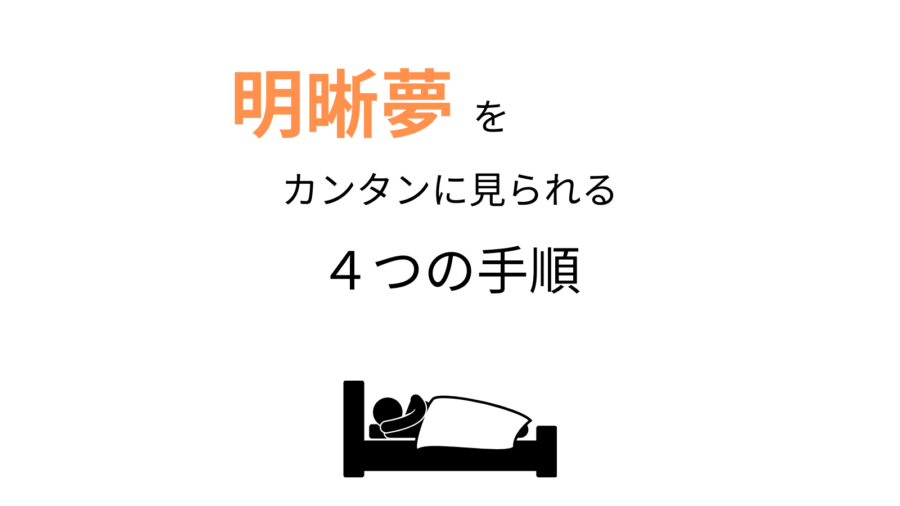なぜクマノミはイソギンチャクに刺されないのか?
海の中では、捕食と生存競争が日常茶飯事です。
そんな厳しい環境の中、クマノミとイソギンチャクは互いに助け合いながら生きています。
イソギンチャクは、毒を持つ触手を使って外敵から身を守ります。
この毒は「刺胞(しほう)」と呼ばれる小さな細胞から発射され、魚や小さな生物に対して強い神経毒を放ちます。
通常、魚がこの触手に触れると刺胞が作動し、逃げる間もなく麻痺してしまいます。
ところがクマノミはイソギンチャクの触手の間を自由に泳ぎ回ることができます。
この関係は、クマノミが外敵から身を守るためにイソギンチャクの庇護を受ける一方、クマノミがイソギンチャクの外敵を追い払ったり、餌を提供したりすることで成立しています。

これまで、クマノミが刺胞を回避する方法として、以下の3つの仮説が提唱されていました。
- 粘液バリア仮説:クマノミの皮膚を覆う粘液が厚く、刺胞の毒針が届かない
- 分子模倣仮説:クマノミの粘液がイソギンチャクの粘液と似た成分を持ち、外敵と認識されない
- トリガー回避仮説:クマノミの粘液には、刺胞を発射させる分子が含まれていない
特に3つ目の「トリガー回避仮説」は、近年の研究で有力視されていましたが、明確な証拠はありません。
そこで研究チームは3つ目の仮説を詳しく調査することにしました。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)