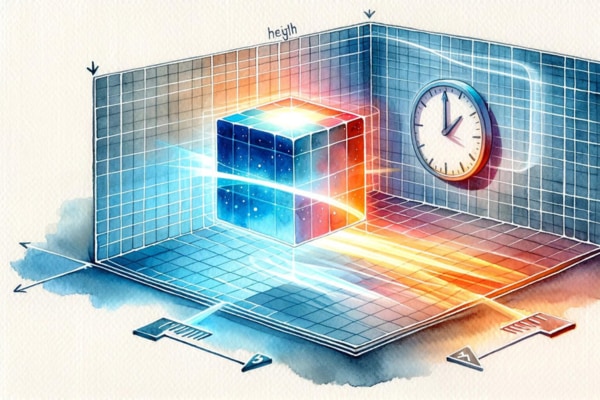SNSが心に与える“静かな毒”とは?

これまで、SNSとメンタルヘルスの関係については、主に「利用時間の長さ」が問題視されてきました。
SNSを長く使うほど、心の健康に悪影響を及ぼすのではないか——。
そうした仮説に基づいて、多くの調査やメディアの報道が行われてきました。
しかし近年、「時間の長さ」だけでは、心の問題を十分に説明できないという見方が広がっています。
実際、アメリカ・テキサス州の複数の医療機関が参加した研究プロジェクトでは、この視点に基づいた調査が行われ、従来の「時間重視」では見えてこなかった重要な知見が報告されています。
この研究では、うつ病や自殺念慮を抱える青少年のうち、40%以上が「問題的なSNS利用(PSMU)」をしているとされ、その人たちはそうでない若者に比べて、うつ症状や不安、自殺念慮のレベルが明らかに高いことが示されました。
ここで注目すべきは、「どれだけ使っているか」ではなく、「どう使っているか」という点です。
たとえば、SNSが見られないと落ち着かず不安になる、投稿を見たあと自己嫌悪や劣等感にさいなまれる、自分と他人を比べて「なんで私はこうなんだろう」と落ち込んでしまう——。
こうした心理状態に陥る人が急増していることが、さまざまな調査で報告されています。
つながりを求めて開いたSNSが、逆に自分を孤立させ、心を削ってしまう。
ここにはSNS特有の「比較のワナ」が潜んでいるようです。
華やかな日常、美しく加工された写真、成功して見える友人たち。
それらは、見れば見るほど「自分だけが取り残されている」という感覚を強め、気づかぬうちに心を蝕んでいきます。

スクロールしながら感じる小さなイライラや落ち込みの積み重ねが、やがて深刻な精神的ダメージとなる。
SNSは便利で楽しいツールである一方、扱い方を間違えれば、心をむしばむ“静かな毒”にもなり得る——。
そんな現実が、いま私たちの目の前にあるのです。














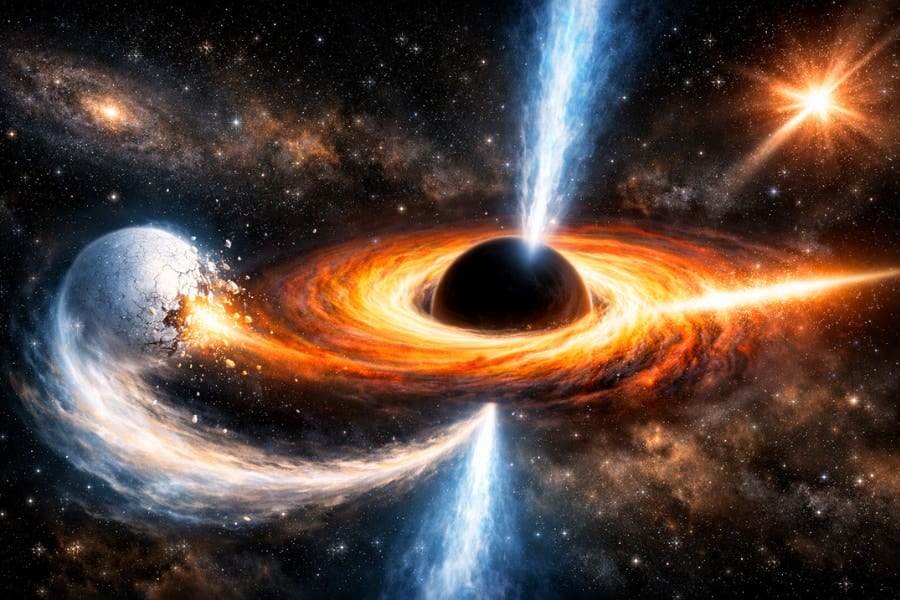

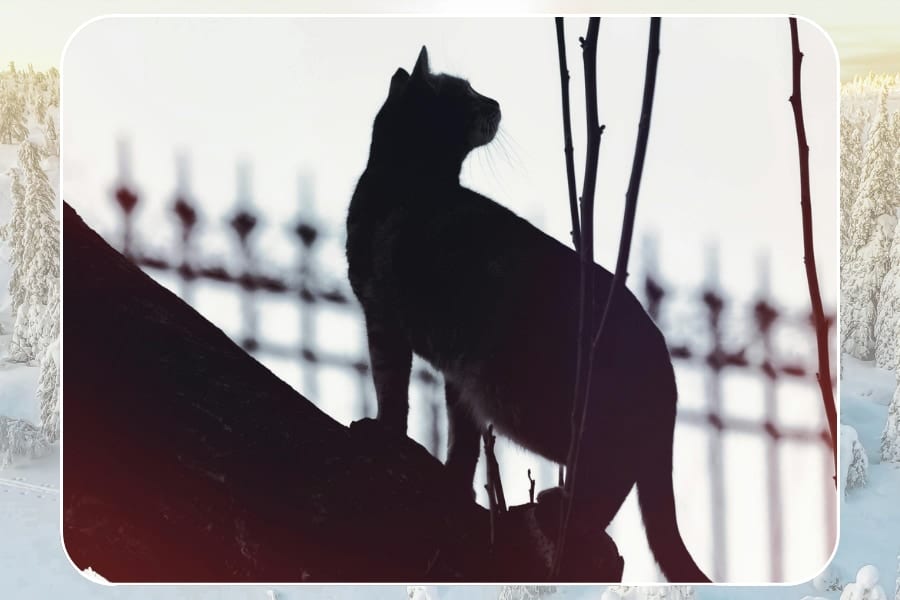




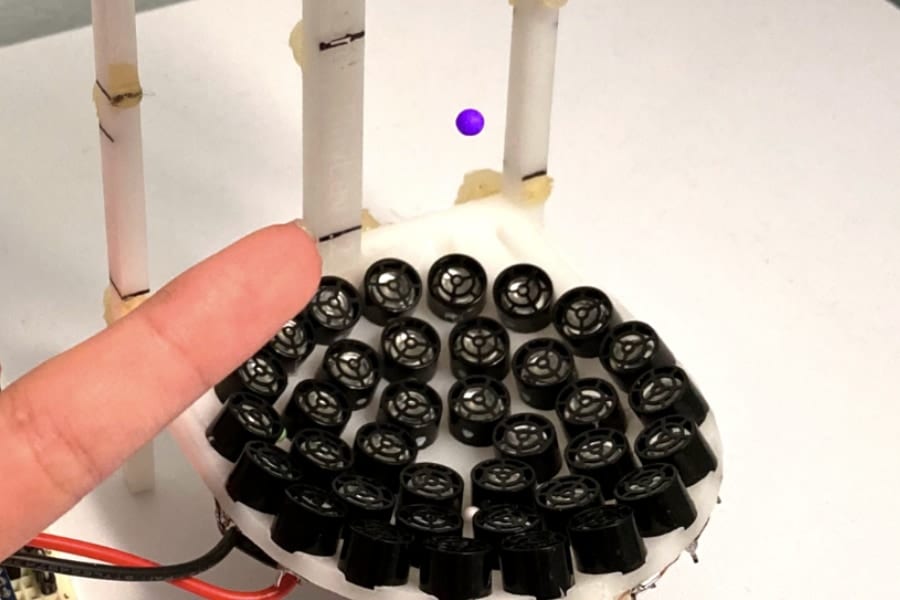









![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)