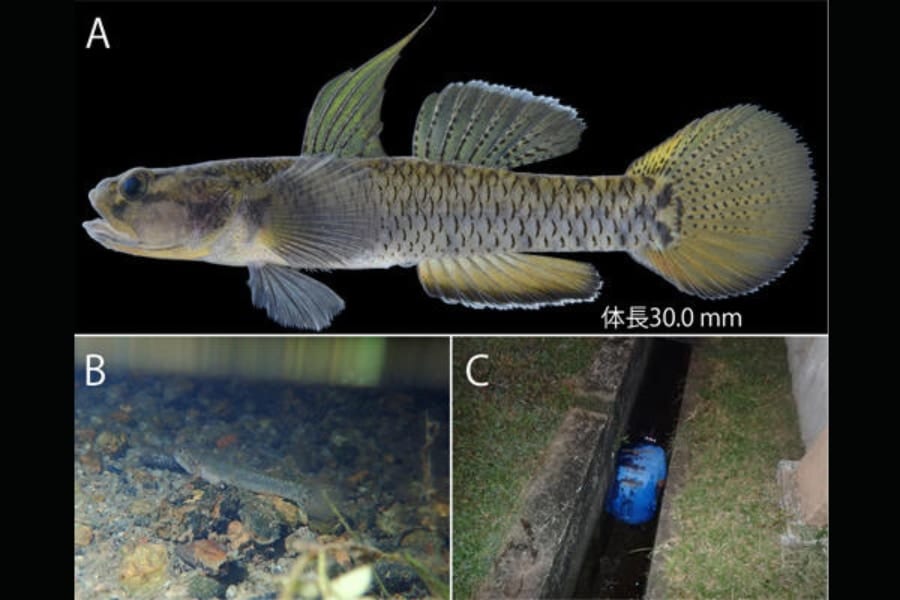内気な性格の持ち主が「イノベーション」を起こす?
今回の主役となるのは、実験用動物としても有名な「ハツカネズミ(学名:Mus musculus)」です。
研究チームは性格の違い、特に「大胆さ」と「内気さ」といった正反対の特性が、問題解決能力にどのような影響を与えるかを検証しました。
100匹以上のハツカネズミを対象に、野生の自然環境に近いセット(セミナチュラル環境)と、制御された実験室内のセットという2種類の環境で、問題解決タスクを実施し、ネズミの性格ごとの粘り強さやタスク成功率を比較。
その結果は驚くべきものでした。
問題解決タスクに繰り返し挑んだのは、大胆な性格のハツカネズミではなく、内気で物静かなハツカネズミたちだったのです。
大胆な性格のハツカネズミは一度問題に取り組んでうまくいかないと、二度は寄り付かない傾向が確認されました。
これと対照的に、内気なネズミは問題解決に失敗しても、後から再び問題解決に取り組み、これを何度も繰り返す傾向が見られたのです。
挑戦回数が多いほど問題解決タスクの成功可能性も高まるため、内気なネズミの方が結果的に成功率も高くなっていました。

この結果は、動物行動学における一般的な前提、つまりは「新しい問題を解決するのは、好奇心旺盛で大胆な個体である」という考えに一石を投じます。
内気なことは決してネガティブなことではなかったのです。
むしろ「内気さ」は「粘り強さ」や「慎重さ」と密接に関係しているのかもしれません。
研究主任のアレクサンドロス・ヴェジラキス(Alexandros Vezyrakis)氏は「イノベーションの発生は、大胆さや勇敢さよりも、どれだけ粘り強く何度も足を運ぶかということに、より強く影響されるのかもしれません」と話しています。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)