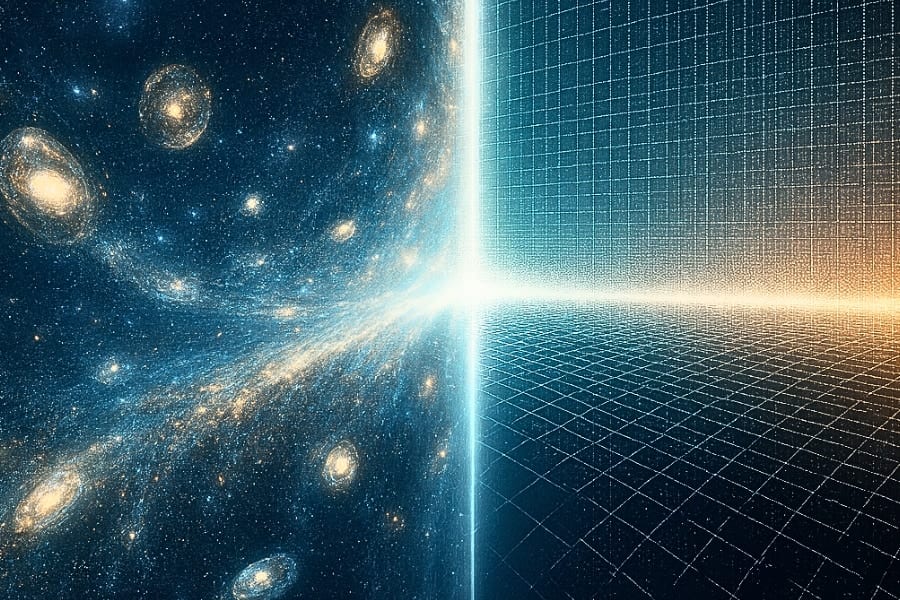2本の電極で“生体カノン” — 昆虫楽器、始動
では実際に、どのようにしてセミを“演奏”させたのでしょうか。
その手順はある意味シンプルですが、生き物相手だけに試行錯誤もありました。
まず研究者たちはオスのアブラゼミ数匹を用意し、発音筋に細い電極2本を挿入しました。
電極はセミの背中側から腹部内部に差し込み、発音筋の近くに届かせます。
セミは局所麻酔などできませんが、慎重に行えば電極挿入自体で即死することはありません。
セットアップとしては、セミのお腹に刺さった電極の先端を細いリード線で外部の回路と繋ぎ、そこから電気信号を送り込みます。
さらにセミが飛び立ったり動き回ったりしないよう、羽を固定し、マイクを至近距離(1cmほど)に置いて鳴き声を録音できるようにしました。
次に、このセミに対してコンピューターから様々な電気刺激を与えてみました。
具体的には、一定の周波数の電圧パルスを断続的にセミに送り、どの程度の電圧でセミが鳴くか、音の高さは入力通りになるかを調べました。
入力する信号の波形はデジタルな矩形波で、周波数はピアノの音階にならいA0(ラ音、27.5Hz)からC4(ド音、261.6Hz)までの範囲を試しました。
A0は人間にはかなり低い低音ですが、セミの筋肉の収縮スピードで理論上その程度まで鳴き声の間隔を遅くできるかもしれません。
一方C4くらいまで高速に筋肉を震わせられれば、人間にも聞こえる高めの音になります。
実験の結果、セミがきちんと鳴くためには一定以上の電圧が必要で、しかもその閾値は入力する周波数によって異なることがわかりました。
低すぎる電圧だとセミは鳴かず、徐々に電圧を上げていくとある値で「ジジジ…」と鳴き始めます。
しかし電圧が高すぎても問題で、安定した音にならず筋肉の動きが乱れてしまいました。
面白いことに、適切な範囲内の電圧では入力した信号の周波数通りのリズムで「ジッ…ジッ…ジッ…」と鳴き声を刻みます。
しかし刺激が弱すぎると入力の半分の周波数で鳴いたり、強すぎると入力の2倍の周波数で細かく震える鳴き声になったりしました。
研究チームはそれぞれのパターンに名前を付けました。
狙い通りの周波数で鳴いた場合をCFW(正しい周波数波形)、半分のときをHFW(半分の周波数波形)、2倍のときをDFW(2倍の周波数波形)、どれにも当てはまらない不規則な鳴き方はIFW(不規則周波数波形)と分類しました。
要するに、程よい電気刺激ならセミは狙った通りの音程で鳴きますが、刺激が弱すぎたり強すぎたりすると鳴き方が安定しません。
幸い、適切な範囲の電圧を見極めれば実用上ほとんどの音階をセミに鳴いてもらえることも判明しました。
実験した7匹のセミを総合すると、約27.5Hzの低音A0から約185Hzの高音F#3まで、各音階で安定したCFW鳴動が可能でした。
個体差はあり、性能の良いセミはF#3まで鳴けましたが、平均的にはC#3あたりが上限でした。
いずれにせよ、人間の耳に十分届く音域でセミの音階を実現できたのは大きな成果です。
では実際に音楽を演奏させることはできたのでしょうか。
研究チームはこのインターフェースを使い、有名なクラシック曲「パッヘルベルのカノン」から映画「トップガン」のテーマまで様々な曲の旋律をセミに鳴かせる実験を行いました。
その結果、セミは見事にコンピューターの指示通りドレミファソラシドと音を奏でてみせました。
実際の音色は「ジー、ジー…」というアブラセミ独特のものですが、よくよく聞くと音程が制御されているため、確かにあの「カノン」の調べに聞こえます。
まさに昆虫とコンピューターの合奏と言えるでしょう。
この成果には研究者たち自身も感銘を受けたようです。
第一著者の佃さんは「セミの中には逃げ出そうとするものもいましたし、『まあお腹貸しますよ』と言わんばかりにおとなしい個体もいました」と語っています。
電気刺激に対するセミそれぞれの反応の違いはあれど、多くのセミで音階コントロールが可能であることが示されました。
研究者たちは「中には演奏中に自分から鳴くのを止めてしまうセミもいてヒヤヒヤしましたが、それも含めて面白い発見でした」と振り返ります。
論文中には「セミは刺激されている最中でも自発的に動いたり鳴き止んだりできる」と記されています。
つまり完全にロボットのように操っているわけではなく、セミ自身の状態によっては演奏を中断してしまうこともあるのです。


















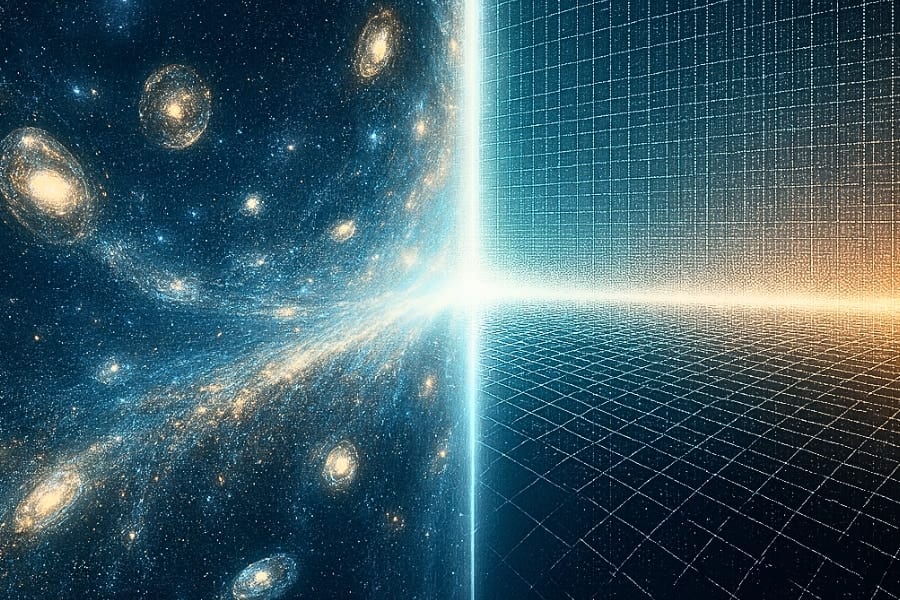


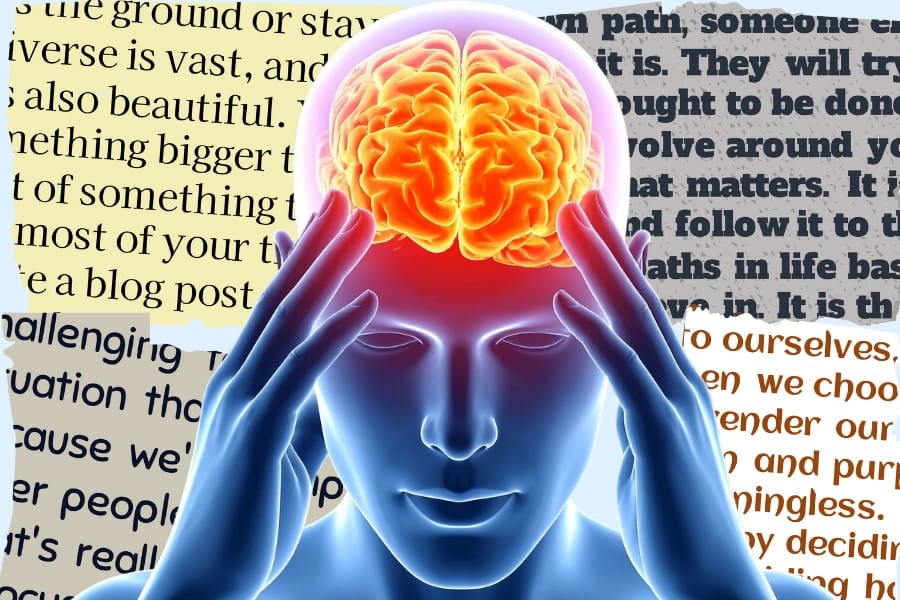







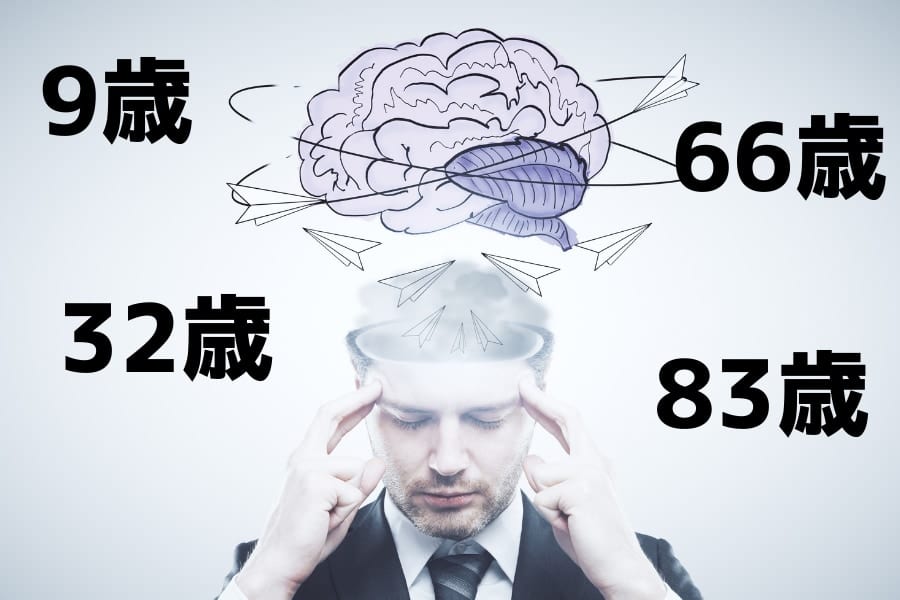


![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)