心理のトラップ──認知的不協和と努力の正当化
そして、いよいよ迎えた1954年12月21日。
彼らはマーティンの家の庭で祈りを捧げ、迎えのUFOを待っていましたが、当然ながら世界は滅びず、彼らを迎えに来るUFOも現れませんでした。
常識的に考えると、こうした状況に対して信者たちは失望して団体を離れるように思えますが、結果は全くの逆でした。
信者たちは「我々の祈りが神に届き、世界が救われたのだ」と解釈を変え、むしろ以前より積極的に布教活動をを始めたのです。
ただ、これはフェスティンガーの予想通りの結果でした。
では、なぜ世界の破滅が来るという予言がハズレたのに、信者たちの信仰心は逆に高くなったのでしょうか?
The Seekersの信者の多くは強い決意を持って入信しており、教団に参加するに当たって仕事や財産を手放していました。こうした状況で、教団の予言が外れるという現実に直面した場合、信者たちは自分の信念と現実との間に生じた矛盾に、強い精神的な不快感(不協和)を感じます。
この不快感を減らすためには、自らの誤りを認め信念を放棄するか、現実を再解釈するしかありません。
そして、The Seekersの信者たちは、これを解消するために事実を都合よく再解釈し、心理的な安定を得たのです。
当時、フェスティンガーはこの理論にまだ名前を付けていませんでしたが、後にこれは「認知的不協和理論(Cognitive Dissonance Theory)」と名付けられることになります。
この認知的不協和によって起きる現象は、その後、別の心理学実験でも詳しく示されています。
1959年、エリオット・アロンソンとジャドソン・ミルズは努力の正当化という実験を行いました。
彼らは女子大学生を対象に、性的な問題について話し合う架空のディスカッショングループに参加するための試験として、一部の女性(実験群)に恥ずかしい官能小説の朗読させるというかなり恥ずかしい課題を課し、別の女性(対照群)には性的な意味を含む単語を数語読み上げるだけの軽い課題を課しました。
その後、全員に動物の性行動についての録音された非常に退屈な議論を聞かせました。(これはわざとつまらない無意味な講義を聞かせています)
そして、その後にこの議論に参加した感想を参加者たちから集めました。
すると単語を読み上げただけの女性たちは、つまらなかった、退屈だった、参加しなければよかった、という感想が出たのに対し、なんと恥ずかしい試験を受けた女性たちは「有意義だった」「この議論には価値があった」と高く評価したのです。
これは参加に苦労や覚悟が伴うと、参加したことが失敗だったと感じる状況でも、人はその事実を無意識に認めず、その不協和を解消するために現実を歪んで解釈してしまうことを示しています。
これはビジネスにおいて会社の上層部が誤った経営判断を訂正できずに突き進んでしまったり、恋愛において恋人が問題のある人間だとわかっても離れられなかったり、投資やギャンブルにおいて引き際を見極められないなどの問題にも通じていると考えられます。














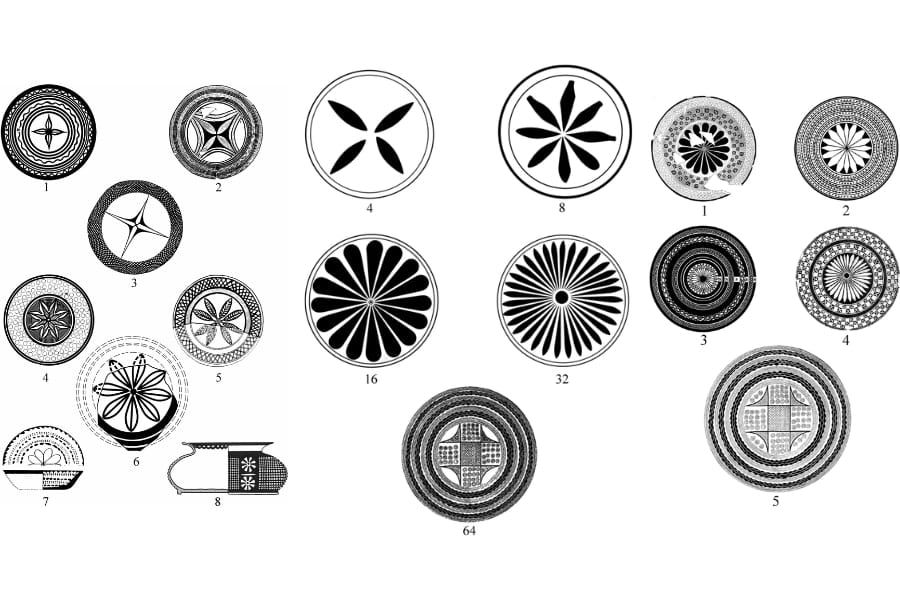


















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























